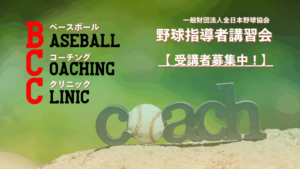第2回執筆者:アマチュア野球規則委員会 委員長 桑原 和彦
山中正竹・全日本野球連盟会長からボールを受けとったので、忘れられない思い出を紹介させていただきます。
東京六大学野球リーグの審判員になって間もないころ、ある試合で二塁塁審を務めました。9回1死一、二塁、ハーフライナーが遊撃手の手前に飛びました。当時は今と違って、二塁塁審は内野手の後方にいました。ボールを捕球した遊撃手が、私を振り返ってグラブを掲げてキャッチをアピールし、私は「アウト!」と右手を挙げました。実は、直接捕球したかどうか、後方からは見えなかったため確信はありませんでした。
そのままボールは二塁に転送され、ダブルプレーで試合終了。敗れた法政大学はその瞬間、優勝の可能性がなくなりました。
神宮球場は騒然とした雰囲気になりました。
法政大学の監督がベンチを出て、私のところに来ました。山中さんです。
「桑原くん、今のはショートバウンドじゃないか?」
「いえ、ノーバウンドです」
答えた私の顔は真っ青だったと思います。
「そうか、わかった」
山中監督はすぐに引き返し、選手たちに試合終了のあいさつに並ぶよう促しました。
しかし、ファンや関係者は納得がいかなかったようで、私は1時間以上も球場から出ることができませんでした。
もう審判員はやめようと決意し、帰途に母校の先輩審判員に電話を入れました。
「聞いたよ。実は山中さんからも電話があり、『学生が騒ぐからベンチを出たけれど、おれもベンチからよく見えなかったんだ。桑原くんに気にしないでくれと伝えて欲しい』と言われたよ」と先輩は教えてくれました。
救われました。もう少し審判員を続けてみよう。「桑原、うまくなったな」と、いつか山中さんから言われるように頑張ってみよう。そう思うことができました。
審判員をしていると、大変なこともあります。試合に対する責任の大きさはもちろん、仕事や家庭との両立などで悩むこともあります。
一方で、その何倍も素晴らしい経験や仲間ができます。
選手と一緒にグラウンドに立てるのは審判員しかいません。
プレーヤーとしては届かなかった舞台に立てるかもしれません。何らかの事情で高校や大学で野球ができなかった人でも、審判員として甲子園や神宮のグラウンドに立てる可能性があるのです。
野球が大好きな人たちが、審判員としてグラウンドに立つ――。
そのために必要な環境やシステムを整えるのが私たちの役割です。ご紹介したようなケースの判定は、ビデオで確認できる制度も少しずつ整えています。
現在、約3万6000人がアマチュア野球の審判員として活動しています。2015年にはライセンス制度がスタートしました。
まず、各都道府県で開催される講習会を受講すれば、3級審判員として認定されます。野球が大好きな皆さんに、ぜひ挑戦していただきたいです。
審判員の皆さんは、ぜひ若い人が憧れるような審判員になっていただきたいです。
「先輩、選手だったころよりカッコいいですね」 「そうだろ、君もやってみるか」
後輩たちと、そんな会話をして欲しいです。
若い人たちが審判員に興味を持っていただくにはどうすればいいか。皆さんと一緒に考えていきますので、ぜひご協力ください。
くわばら・かずひこ
1962年、群馬県出身。前橋高-立教大で外野手として活躍。主将も務めた。前橋市役所に勤務しながら29歳で東京六大学野球連盟の審判員となり、社会人野球の都市対抗や高校野球の甲子園大会、2008年北京五輪にも参加した。2023年からアマチュア野球規則委員長。
*審判員にご興味のある方はこちらをご覧ください。
「動画で見る審判基礎講座」