
野球の競技人口減少が顕著になったのは2010年代で、以降、関係者から危機感が叫ばれるようになった。
昭和の時代は多くの少年たちが野球をして遊んだが、平成から令和になって少子化や人気競技の多様化が進み、さらに携帯ゲームの普及、公園でボール遊びをできなくなるなど外的要因も複雑に絡み合い、野球をする子どもの数は減り続けている。
学童野球では、母親がお茶当番や送り迎えといった長時間に渡る手伝いを嫌がって子どもの入団に反対するなど、時代の潮流に合わない野球のあり方も目についてきた。
一方、中学校では教員の働き方改革も踏まえた部活動の地域移行が進められ、部員減少の顕著な中学軟式野球は新たなあり方を模索している。
野球が身近にある形をつくる
野球界は長らく、普及活動をおこなってこなかった。黙っていても子どもたちに選んでもらえたからだ。
競技人口減少に歯止めのかからない2010年以降、プロ球団やアマチュアの各世代が普及活動を行い始めた。
では、そもそも普及活動とは何を目指し、どんなことを行なっていくべきなのだろうか。
「僕も最初は目の前の子どもたちをチームに入れて、野球をしてもらうことに注目してきました」
そう語るのは、2013年から2023年まで神奈川県立川和高校の野球部を指導し、現在は川崎工科高校で数学科教師として勤務しながら、長男の所属する高校野球部のサポートを中心に小中高大のカテゴリーで指導している伊豆原真人氏だ。
「普及活動とは、目の前の子どもが野球を始めることだけではないですよね。継続的に野球が身近にある形にしていくのが普及活動だと考えるようになりました」
伊豆原氏がそう捉えるようになったのは、県立高校の教員として野球指導に携わるという立場も関係している。
川和では1学年で約25人の選手が入部してくるようになったが、必ずしも野球がうまい子ばかりではなかった。割合的に言えば、5〜10人がそこに該当する。
「でも、野球がものすごく好きという点では、うまい子たちと一切変わりません。下手な子たちって、小学校から中学校に上がるときに野球を続けるか迷いますよね。そういう子たちが『自分は野球が好きだから』と、野球をできる環境はすごく大事だと思います。今まではそれが中学の部活動であったはずだけど、今の世の中ではなかなか難しくなってきました。
それに今、そういう子たちに技術を教えることが軽視されている感じがすごくあるようと思います」
自己肯定感を持って卒業させたい
伊豆原氏は川和の監督時代、個にフォーカスすることを重視し、公立高校では珍しい三軍制を敷いたことを前回の連載で紹介した。
強豪私学の監督には、いわゆる「一軍」ばかりに注力し、実力的に劣る選手は他の指導者に任せるケースもあるが、伊豆原氏は二軍や三軍にも目を配った。チームの全員を満足させることに加え、「普及振興」という視点を備えていたからだ。
「野球をするのが下手だけど、すごく好きな子が指導者になるというケースもあります。選手たちには『できるかどうか』じゃなく、『知っているかどうか』というところで興味を持てるようにしてあげたい。誤解を恐れずに言うと、運動音痴な子は、教えたところでできないわけですから。
でも、『物理的に考えると、リリースはこうすればいいのか』と興味を持ち、オタクみたいになっていく子もいます。それはすごいことですし、『野球が上達した』ということだと思います。そこから物理学に興味を持ってもいい。そうやって先に先に発展していくような興味の持ち方、うまくなり方にはいろんな形があります。そういう子たちも拾い上げてあげるのが、本来の野球の一番大事なところだという気がします」
川和は文武両道を掲げる進学校で、野球部から東京大学に合格者も輩出している。なかには野球の実力が低くても、野球が大好きで仕事として関わっていきたいと考える選手もいるだろう。伊豆原氏はそう考えて、部員全員が野球をより好きになれる環境づくりに力を入れてきた。
「学年で野球の実力は一番低くても、『俺は誰より野球が好き』という子もいるかもしれません。別に下手でもいいじゃないですか。その子が大学を出た後にソフトバンクへ就職して、ひょっとしたら球団の幹部になるかもしれない。川和の野球部員たちは賢いので、そういう可能性を持っています。学年の25人全員が野球を好きで、『高校3年間で自分がうまくなった』という自己肯定感や成功体験を持ちながら、次の進路に行くという形を取りたいと思いました」

(写真:本人提供)
息子に技術指導しない理由
高校教諭の伊豆原氏は、三児の父親でもある。現在、高2・中1・小3の3人の息子たちにも野球の“普及活動”を行なっている。
まず意識したのが、野球を好きになってもらうことだった。
「小学校の入学時や、低学年など野球の入り口の部分では『いかに楽しいと思えるか』。これに尽きます。うまくなることを先に置いてしまうと、すごく辛いですよね。うまくなるためには楽しみがないと、“うまくなる”というところまで絶対たどり着かないので、まず楽しいと思えるか。これが圧倒的に大事です」
自分の子どもとキャッチボールをする父親は多くいるだろうが、伊豆原氏は長男にはそうできなかった。自身が高校野球の監督を務めており、時間的に余裕がなかったからだ。
その代わり、長男が幼稚園児の頃から高校野球部の練習に連れていった。すると、練習の隙を見てマネジャーや選手たちが遊んでくれた。
「私が技術的に何かを教えるというのではなく、息子を野球の観戦やイベントに連れていき、常に野球がある環境をつくり、親しみやすくなるような状態をつくりました」
自宅にはボールやバットが転がっていて、いつでも触れられるようにしておく。「やらせる」のではなく、「好きにさせる」。そうして伊豆原家の3人の少年たちは野球に没頭していった。
夜、帰宅した伊豆原氏は夫人に部員の話をする際、決めていることがある。必ずポジティブな話しか口にしないことだ。
「選手のグチをこぼさず、『これだけうまくなったんだよね』と、いいところをたくさん話すようにしました。『こんなプレーができるようになったよ』、『次の試合でこうできたら、あいつは本当に成長したな』って、ポジティブな話しかしない。息子たちもその話を聞いているので、彼らに対して環境を固めるという感じですね。勉強も一緒だと思います」
伊豆原氏は高校野球の指導現場から離れた今、中1の次男、小3の三男をバッティングセンターに連れていくことがある。技術的な指導は一切せず、ただ見ているだけだ。1回で300球程度、子どもたちは夢中で打ち込んでいく。
「そうすると、彼らのほうから『今のはどうだった?』、『このとき、良くなった?』と聞いてくるので、『あのときは良かったね』、『このとき、もう少しこうしたら、もっと良かったんじゃない?』と、聞いてきたからこそ答えてあげる。聞いてくるまでは、こっちから一切言いません。ずっと見ているので、お金はたくさん飛んでいきますけど(笑)」
周囲には熱心に我が子を指導する“お父さんコーチ”がたくさんいるが、伊豆原氏は黙々と見守るのみだという。
「技術的なことを言いたければ、もっと量をやってからです」
伊豆原氏は父親として、そして高校野球の監督として、大切にしていることがある。指導の「中身と目的、達成条件」を明確にすることだ。
※次回に続く
(文・撮影/中島大輔)




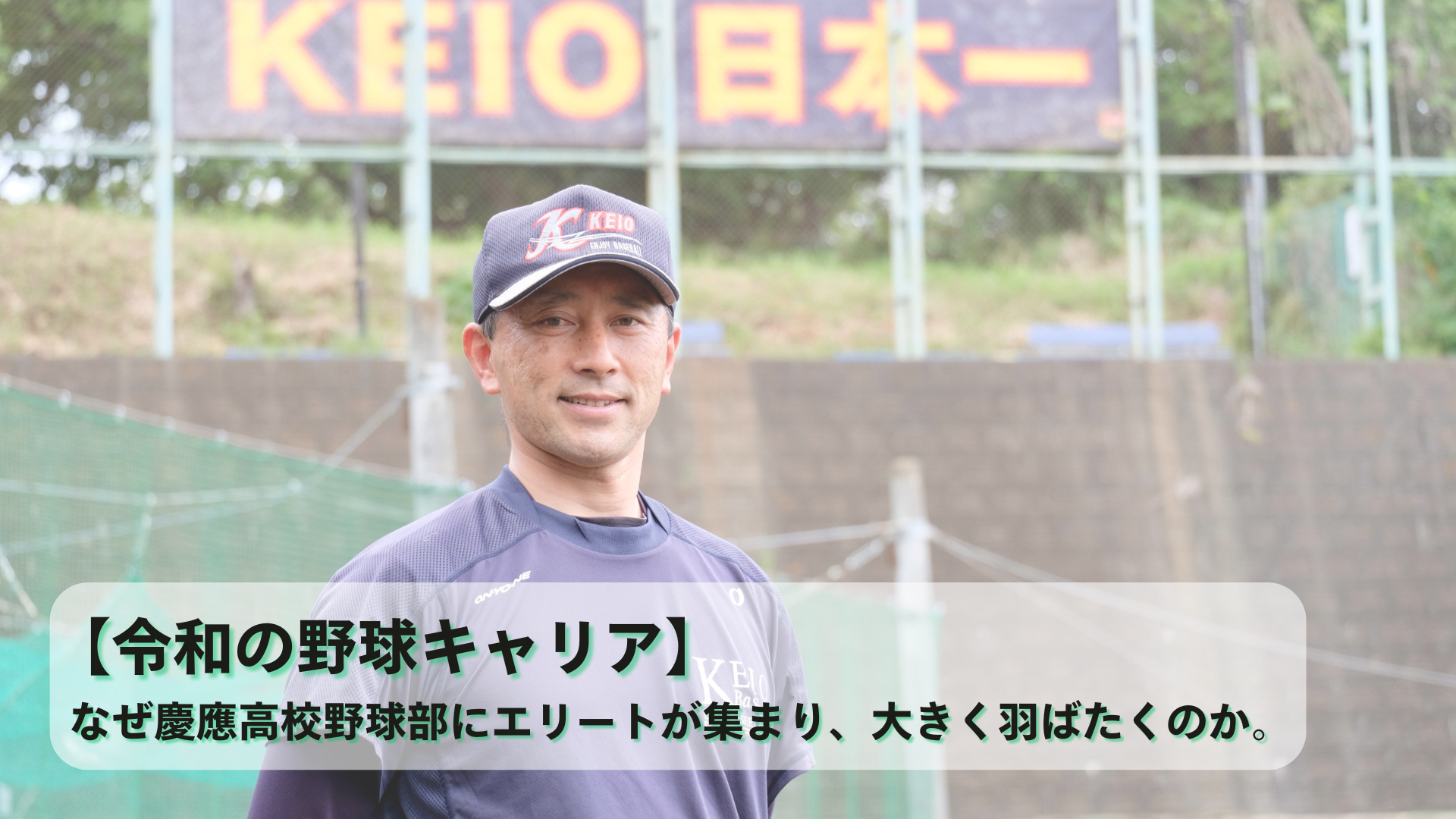

記事へのコメント