
ハイレベルの文武両道を実践する神奈川県立川和高校野球部の前監督で、現在は川崎工科高校で数学科教師として勤務しながら小中高大のカテゴリーで指導する伊豆原真人氏は、練習の冒頭で必ず伝えることがある。
「練習の中身と目的、達成条件」を明らかにすることだ。
例えば、置きティーをする際にはこんなことを伝える。
「今日はアウトコースに目をつけた状態から、内角高めを打つ練習するよ」
これが練習の中身で、続けて目的が以下になる。
「肩口から入ってきたスライダーは、外を待っていたところでも回れば飛んでいくからね」
なぜ、この練習をするのか。
「今日はこういうふうにバットの距離をちゃんと克服するための練習だから、それについての技術的な話をするよ」
そうして技術の話をして、「はい、じゃあやってみようか」と実践に移っていく。
指導者に重要な「対話」&「待つ時間」
伊豆原氏は数学の教師でもある。上記は授業を始める際とまるで同じ流れだという。
例えば、公式の説明をする場合だ。
「この公式はどうやって成り立っていて、こういうときのために使うんだよ」
公式について説明したら次に例題をやってみせ、演習問題に続く。生徒たちが演習に取り組む間、教師の伊豆原氏は黙って見守るのみ。わからない生徒がいれば、「先生、質問です」と自ら質問にやって来る。
以上が、自分で公式を自分で使えるようになるまでのプロセスだ。
「私にすれば、部活の練習も“野球の授業”をしているという感覚です。大事なのは演習ですね。選手たちが試行錯誤しているのをずっと見て、質問しに来るのを、答えが出るのを待っている。演習の途中で『それは違う』とこっちが言えば、選手は『今、やっている途中です』となりますよね。指導者には“待つ”というのがすごく大事な要素だと思います」
野球界には長らく“質問”を受け付けない指導者が少なくなかった。監督が上の立場にいて、「いいから、俺の言ったとおりにやれ」と選手から“質問”を受け付けなかったからだ。
監督の感覚が当てはまる選手ならいいかもしれないが、そうでないケースも少なくない。当然、選手たちには感覚の違いや個人差が存在する。
例えば10スイングで理解できる選手もいれば、100回振った後にコツをつかむ者もいる。あるいは100回スイングしてもわからない部員には、違うアプローチをしなければならない。
「それは対話があって初めて成り立つことです。だから、その対話ができるようになる段階まで指導者は待たなければいけない。となると、見ている時間が長くなりますよね」
目的と方法を伝え、演習へ
伊豆原氏が「小中学校の練習で多い」と感じるのは、練習の目的を明示しないことだ。
「コーチが『ノックやるぞ』と言って、いきなり始めます。そのゴロをどう捕るのか、練習でうまくなるポイントは一切伝えず、いきなりノックが始まり、『おい!バックハンド(逆シングル)は100年早いぞ!』という話になる。
最初から『正面に切り込んで入る練習だ』と言ってあげれば、バックハンドではなく、正面に入ろうとするじゃないですか。選手はしっかり捕ったのに、怒られるというパターンは一番よくない。最初に目的と方法を伝えてあげて、それを演習する時間をとるべきです」
どんな指導者も、練習の質をどのように高めるかと考え抜いているはずだ。
やみくもに数をこなしても、上達のスピードは上がらない。同時に頭でっかちになるのもよくないので、一定の量をこなして体で覚えることも大切だ。指導者に求められるのは、両者のバランスをうまくとってあげることである。
とりわけ昨今はラプソードやスマートフォンのアプリ、YoutubeやSNSなど選手自身で上達できる手段が増えている。
だからこそ、指導者は自身の役割を再認識することが不可欠だと伊豆原氏は語る。
「コーチの役割には『伴走者』という意味合いがありますが、それより最初に選手をしっかり分析できる人、『アナリスト』という要素が大事だと思います。道しるべをつくってあげることですね。精神的、肉体的に必要なものを数値目標として掲げ、それを達成するための具体的な道しるべを示す人がトレーナーです。ゴールにたどり着くためには運動生理学や、解剖学を含めた専門家も必要になります」
専門家の知見をうまく借りれば、選手はグンとレベルアップしていく。特にトレーナーの登用は高校野球でも進んでいる。

監督の仕事は評価&環境設定
では、監督はどんな役割を担うのか。伊豆原氏が続ける。
「掲げた数値は、はたして目標として本当に良かったのか。そこも含めた『評価者』が監督です。具体的には『これでは試合で使えないな』、『この球がいいので、こういう場面で使えそうだ』と評価しますが、そうすると次の課題が出てくる。それが『PDCAサイクル』です。
高校野球で言うと、監督が4つのサイクルにそれぞれの専門家をマネジメントする必要が出てきます。P、D、C、Aを達成する要素を監督が全部知っているなんてあり得ないので、そのサイクルをうまく回すための人材を集めることが監督には大事になると思います」
現在の高校野球で言えば、健大高崎の青栁博文監督や仙台育英の須江航監督が好例だろう。環境をうまく整えているからこそ、チームは定期的に結果を残し、部員たちは大きく羽ばたいていく。
昨今メジャーリーグでは各種コーディネーターや専門家がチームのスタッフに招かれているように、パフォーマンスアップの手段が精密化&高度化している。だからこそ、優秀な人材を集めることが重要になるのだ。
高校野球ではリソースの点で私立が有利だが、公立でも対抗する手段はあると伊豆原氏は言う。
「外部から有名なトレーナーを呼ぶとお金がかかりますが、トレーナーの“卵”を呼べばいい。学生や、社会に出て1年目で勉強したいという人はものすごくたくさんいます。そういう子は勉強しながら一生懸命やってくれるし、公立でも謝礼程度の額なら捻出できると思います」
当然、経験の浅いトレーナーは発展途上だ。だからこそ監督にも勉強になると伊豆原氏が続ける。
「若いトレーナーに監督の目的や方向性を理解させることも、指導者の資質の向上につながっていきます。年下のトレーナーに改善点を指摘されたくないので登用しないパターンもあるかもしれませんが、そもそも監督が自分のやりたいようにチームを運営するのではなく、どうすればチームがよりよくなるかを考えるべきです。部活動は子どもたちのためにやっているわけですから。それはチームが強い・弱いというより、充実した組織、指導者、部活動として、すごく大事なところだと思います」
どうすれば、選手たちが少しでも上達していけるか。そもそも、チームは何のために存在するのか。
指導者が多角的に考え抜くことで、私立でも公立でも、レベルアップを果たしていけるはずだ。
(文・撮影/中島大輔)





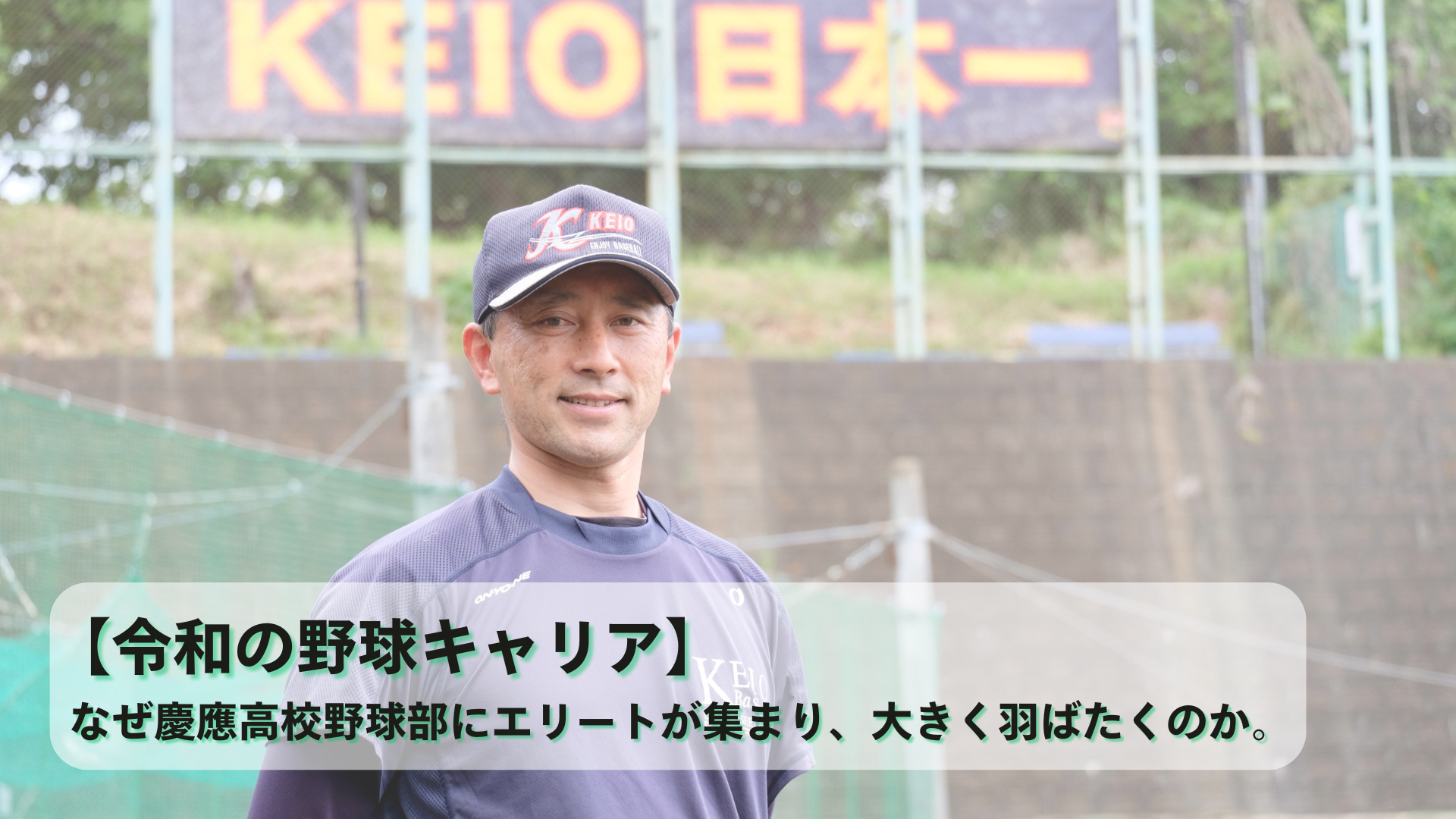
記事へのコメント