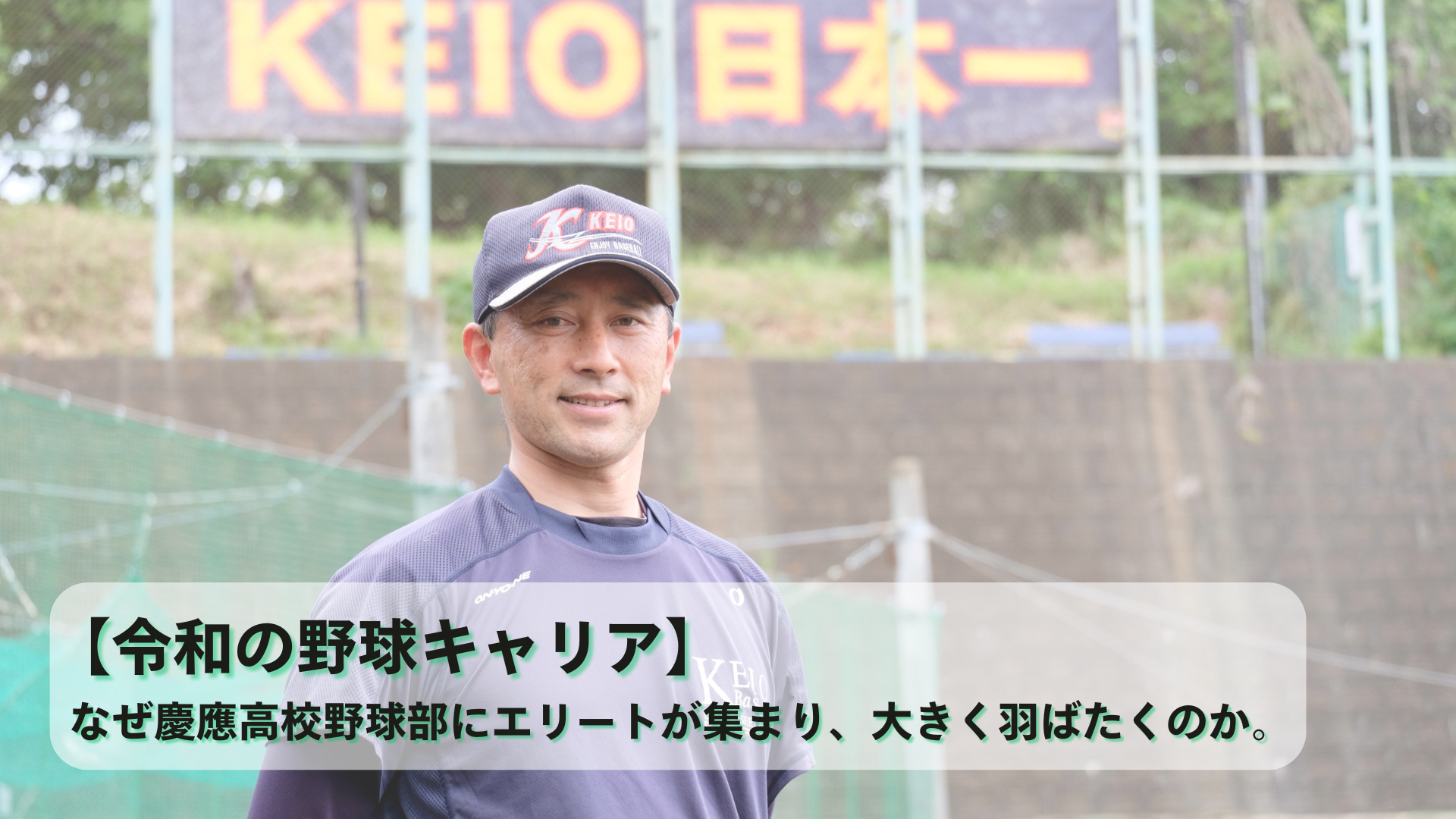
生成AIが高校野球の指導現場に広がり始めている――。
2025年夏の全国高校野球選手権大会の開幕を翌日に控えた8月4日、朝日新聞は1面でそう伝えた。
時代の流れを考えると、AIや最新テクノロジーを野球の指導に取り入れることは不可欠だ。トラックマンやラプソード、ブラストなど投球や打撃の動作を可視化するテクノロジーが登場し、うまく使いこなせば個人の成長が加速され、チームの勝利にもつながるからだ。
一方で機器を導入したのはいいが、どのように使っていいかわからず、無用の長物となっているというケースも少なくない。
また、トレーナーなど外部指導者が多くいるなか、誰に教えてもらえばいいのか決められないという声も漏れてくる。
「量から質」の時代へ
「情報処理能力が重要な時代になっているのは間違いありません」
そう話すのは、慶應義塾高校野球部の森林貴彦監督だ。
慶應大学在学中から母校の学生コーチを務め、2000年頃につくば秀英高校のコーチに就任、2015年から慶應高校を率いる同監督は令和の今、指導者に求められる変化を痛切に感じている。
「以前は選手、指導者ともに『量』がよりどころになっていたと思います。量をすることで安心できるというか。
でも最近は指導方法がたくさんあることを選手もわかっているので、『これが唯一の正解とは限らない』と、下手したら小学生でも思っている。
やみくもに量をやればいいというわけではないとみんなが気づき、質を求めるようになってきました。選手が『こういう練習をやったほうがいい』と納得しないと、主体的に取り組まないようになっています」
物事にいかに効率的に取り組むか。AIをはじめとするテクノロジーを使い、仕事はもちろん、余暇や趣味にもタイパやコスパを求めるのが令和の時代だ。
野球にも同じことが言える。やみくもな長時間練習は集中力を削り、適切な休養に反比例するため、身体的な成長につながらない。
甲子園に出場する強豪校の中には、『寝ないと大きくならない』として寮の消灯時間を早め、朝練をやめるチームも増えているほどだ。

「何を教えてくれるんですか?」という雰囲気
時代の変化とともに、選手の育成法も明らかに変わりつつある。プロ野球のあるスカウトが、近年のトレンドをこう語る。
「スポーツをする上でも、より良い環境が大事になっています。結局、時間とお金のある家庭に生まれたか。オーバーに言えば、デジタル化ですね。そういうものに触れる機会を持つ家庭に生まれたか。それが選手の“エリート化”につながっている」
エリート化の代表格は、高校野球で言えば早慶だ。
早稲田大学から日本ハムに2024年ドラフト5位で入団し、1年目から活躍している山縣秀は早大学院出身。チームメイトの清宮幸太郎は日本代表のラガーマンを父親に持つ2世アスリートでもあり、早稲田実業から鳴り物入りで日本ハム入りした。
一方、ソフトバンクには今年の交流戦でMVPに輝いた柳町達、廣瀨隆太、正木智也と慶應高校出身の野手が在籍している。
では、早慶出身のエリートにはどんな特徴があるのか。慶應幼稚舎の教員としても勤務する森林監督は、慶應の子どもたちはある意味で特殊な環境で育っているという。
「子どもの数が少なくなり、やりたいことのある子に親はお金をかけるようになっています。少年野球でも個人レッスンをしてもらったり、何万円もする高いバットを買ってホームランを打たせたりする。お金かけた人ほど、結果や能力に結びつきやすいのは確かだと思います」
現代社会を象徴する言葉が“課金制”だ。
学習塾と同じように、子どもの頃から野球スクールに通わせれば、周囲の選手より効率的に上達しやすい。都内という好立地にあり、裕福な親の多い慶應には、そうした環境で育った子が多いと森林監督は言う。
ただし、メリットばかりではない。森林監督が続ける。
「レッスンは『この1時間でいかにうまくさせてあげるか』が勝負になります。そうじゃないとリピーターにならないですから。そういうレッスンを受けた子が『お金を払っているんだから、はい、教えてください』となると、主体性と逆行します。
そうした習慣のついた子が部活動に来ると、『僕をうまくしてください』『ヒットの打ち方を教えてください』となりがちです。実際うちでも、『何を教えてくれるんですか?』という雰囲気は結構ありますね」
スマホの検索や、ChatGPTに質問すれば、一瞬で答えを教えてくれる。そうした機器を適切に使いこなすことは不可欠な能力になっている一方、自分で考えなくなるという問題も指摘される。
“遊び”から“習い事”化している野球も、同様のリスクをはらんでいると言えるだろう。

「エンジョイ・ベースボール」の誤解
ではなぜ、慶應高校の選手たちは上の世界で活躍しているのだろうか。森林監督が重視するのは、“指導者に依存しない=自立した選手”を育てることだ。
「指導者に教えてもらうのではなく、こちらが言いたいのは『あなたたち、一人ひとりは何をしてくれますか?』というところです。全部教えてくれると思ったら、大間違い。
逆に言うと、教えることはそんなに簡単ではない。みんなが打てるようになる指導なんて、ないですから。そこは現代の悩みというか……。教えられ慣れた選手たちなので、ズレみたいなものは感じますね」
慶應伝統の方針として知られるのが「エンジョイ・ベースボール」だ。2023年夏の甲子園を優勝したこともあり、広く脚光を浴びた。自主性を打ち出し、選手が自走する組織は確かに理想的だろう。
だが、世間のイメージには誤解も多いと森林監督は感じている。
「慶應では選手本人に任せて、一人ひとりが全部自分で考えてやっているとメディアで一面的に伝えられることもあります。逆にある高校は、指導者から全部を教え込まれているとか……。そんなことはないですよね。
うちにもティーチングの部分はもちろんあります。割合的に言うと、そのティーチングをだんだん減らして、コーチングというか、自分で走り出すように高校3年間で導いてあげたいというイメージです」
森林監督が見据えるのは、卒業後に羽ばたける人材育成だ。
「大学に行けば部員も増えるので、自律的に動いていかなければいけない。社会に出てもそう。『言われたことだけをやっておけばいい』とか、『誰かが全部教えてくれる』と思ったら大間違い。
でも今は、放っておかれると『面倒見が悪い』と言われるので、難しいところですね。教えてもらって当たり前という子たちに対し、自分でつかむという部分は残していきたい。そこのバランスは、いつも苦労しているところです」
個人の育成とチームの勝利のバランスを、いかにうまく取るか。高校野球において、難しいテーマだ。
それをなんとか両立させようとしているからこそ、慶應で野球をしたいと望む選手や保護者が多くいるのだろう。
(文・撮影/中島大輔)






記事へのコメント