
沖縄尚学高校の初優勝で幕を閉じた第107回高等学校野球選手権大会。
高校野球の魅力を改めて知らしめるような熱戦の連続となった一方、大きな社会問題に発展したのが、部内暴力により大会を途中辞退した広陵高校の一件だった。
はたして、高校野球や部活動は何のために存在しているのだろうか。今、改めてその意義が問い直されている。
高校野球は“本業”ではない
甲子園の舞台に立てるのは、選ばれし者だけだ。出場を決めた代表校にも、スタンドで応援する部員がたくさんいる。
大会ではベンチ入りの人数が限られる以上、補欠が生まれるのは致し方ないことかもしれない。
では、普段の練習ではチームをどのように運営していくべきだろうか。特に大所帯を率いる監督には、その方針が重要になる。
「今の時代は、個にフォーカスしていくのが大事だと思っています。もともと川和にいた頃から、取りこぼさないことがすごく大切だと考えていました」
そう語るのは、2023年まで神奈川県立川和高校の野球部を指導し、現在は川崎工科高校で数学科教師として勤務しながら、長男の所属する高校野球部のサポートを中心に小中高大のカテゴリーで指導している伊豆原真人氏だ。
川和は公立の進学校で、伊豆原氏は2013年秋に監督就任。当初は2学年で部員20人からのスタートだったが、勉強面では東京大学への合格者を輩出、さらに野球でも東海大相模と接戦を演じるなど実力を高め、最終的には3学年で70人を超える部員が在籍するまでになった。
そうしたチームで強化を最優先するなら、主力メンバーを中心に限られた練習場所と時間を使うのがいいかもしれない。以前のアマチュア野球では、それが当たり前の環境だった。
だが、伊豆原氏はそう考えなかった。
「もちろん上で活躍できる人材とか、プロ野球選手を育てるとか、野球がうまくなること自体は大事だと思います。でも、それが何かの犠牲の上に成り立つことは、川和高校ではあってはならない。なぜかというと、それが本業ではないからです」
幸福の人間が集まれば、チームも幸福に
高校野球は教育の一環である。日本学生野球憲章にもそう書かれている。
それにもかかわらず、勝利至上主義に陥り、「教育の一環」という面が疎かになるチームは少なからず存在してきた。
一方、川和を率いた伊豆原氏は毎週末のように泊まりがけで県外遠征を繰り返すなど野球の強化にも励んだが、部員を一人も取りこぼさないように心がけた。
「県立高校である以上、入ってくる選手のレベルはピンキリです。公式戦で背番号をもらえるかは別の話になるけど、毎年入ってくる20〜30人全員が必ずレベルアップしている状況をつくってあげる。レベルの低い子たちは球拾いで犠牲にしながら、うまい子の時間だけを取るというのは許されないと思っています。それぞれのレベルに応じて、すべてを拾い上げるという考え方を取るにあたって、個にフォーカスするのは大事なところだと思います」
個人とチームの関係はどうあるべきか。マネジメントにあたる監督にとって、両者をしっかり順序立て、立体的に考えることが重要になる。伊豆原氏が続ける。
「まず『チームがある』というのが、従来の考え方ですよね。もちろん『チームに貢献しよう』は大事なことだと思います。でも、チームのために個を犠牲にすることがあってはならない。
我々は『チームに貢献しろ』と言われてきた世代ですが、今の若い子たちはそうではありません。いかに自分の幸福度を高めるかにフォーカスしている。幸福の人間だけが集まれば、チームは幸福だよねという考え方です。イチローさんも言っていましたけど、僕はその考え方でいいと思います」

伊豆原氏(川和高校時代) (本人提供)
20人に機会をどう与えるか?
伊豆原氏は川和の監督就任時に“個にフォーカス”したチーム方針を打ち出すと、周囲から「お前のやり方は通用しない」と一蹴された。結果を早く求めるなら、監督を頂点にスパルタ式で支配したほうがいい。以前は当たり前のようにそう信じられ、恐怖で支配する指導が主流だった。
だが、伊豆原氏は性格的にそうできなかったこともあり、自分の理想を追い求めた。
改善を繰り返して徐々に結果が出るようになると、部員数は3学年で70人を超えるまでになった。そうして採用したのが“三軍制”だ。「県立高校で三軍制を敷いていたのは、たぶんうちだけだったと思う」と伊豆原氏は振り返る。
「普通の野球部では、20人くらいが1チームで動きますよね。練習試合では1試合目や2試合目に出る選手がいる一方、少ししか出ない選手もいるという形が多いです。でも極端な話をすれば、27人いたら3チームをつくれます。20人をAとBに分ければ2チームできるので、Aチームだけならスタメンを外れる残り10人も、同じ日に2試合経験できることになります」
20人を1チームのなかで競争させるか。あるいは20人を10人×2チームに分け、試合のチャンスを公平に与えて競わせるのか。
伊豆原氏がとったのは後者で、「チーム」ではなく「個」にフォーカスするための方策だった。選手たちをふるいにかけるのではなく、一人も取りこぼさないと心がけることで個々を成長させ、満足度を高められる。
結果、チーム内に競争が生まれて全体の強化にもつながっていく。
野球がうまいかは「些細なこと」
勉強では東大生を輩出し、野球でも打倒・強豪校を狙えるようになると、川和には多様な部員が門をたたいてくるようになった。
毎年25人の入部者がいたとして、「自分は上(大学や社会人、プロ)でやれる」と思っているのは15人程度。残り10人は、「中学の地区大会では1回戦で負けるけど、野球が好きで、勉強がよくできる子」だった。
伊豆原氏は前者を引き上げる一方、後者も輝けるような環境づくりを心がけた。
「いずれそういう子たちが父親になったとき、オヤジが野球を好きだと息子も好きになります。これから父親になっていく高校生たちを、野球をもっと好きになって卒業させる。
もし彼らが野球を生業にしたいと考えれば、選手以外にも指導者、スポーツメーカー、研究者など、野球関連の仕事はたくさんあります。野球が好きで、関連する仕事に就くのは幸せなことですよね。そう思って卒業してほしい。そう考えると、野球がうまいか下手かは結構些細なことだと思います」
大会のベンチ入りメンバーには上限があり、個人の力で変えられるものではない。
では、チームを率いる監督として何ができるか。
「チームに入ってくれた全員が高校野球をやって良かった、うまくなったという実感を持って進学してほしい。そう思い、どんどん具体的にフォーカスするようになっていきました」
高校野球はもっと個人にフォーカスしたほうがいい――。
伊豆原氏がそう考えたのは、本当の意味での「野球の普及活動」と向き合ったからだった。
(文・撮影/中島大輔)





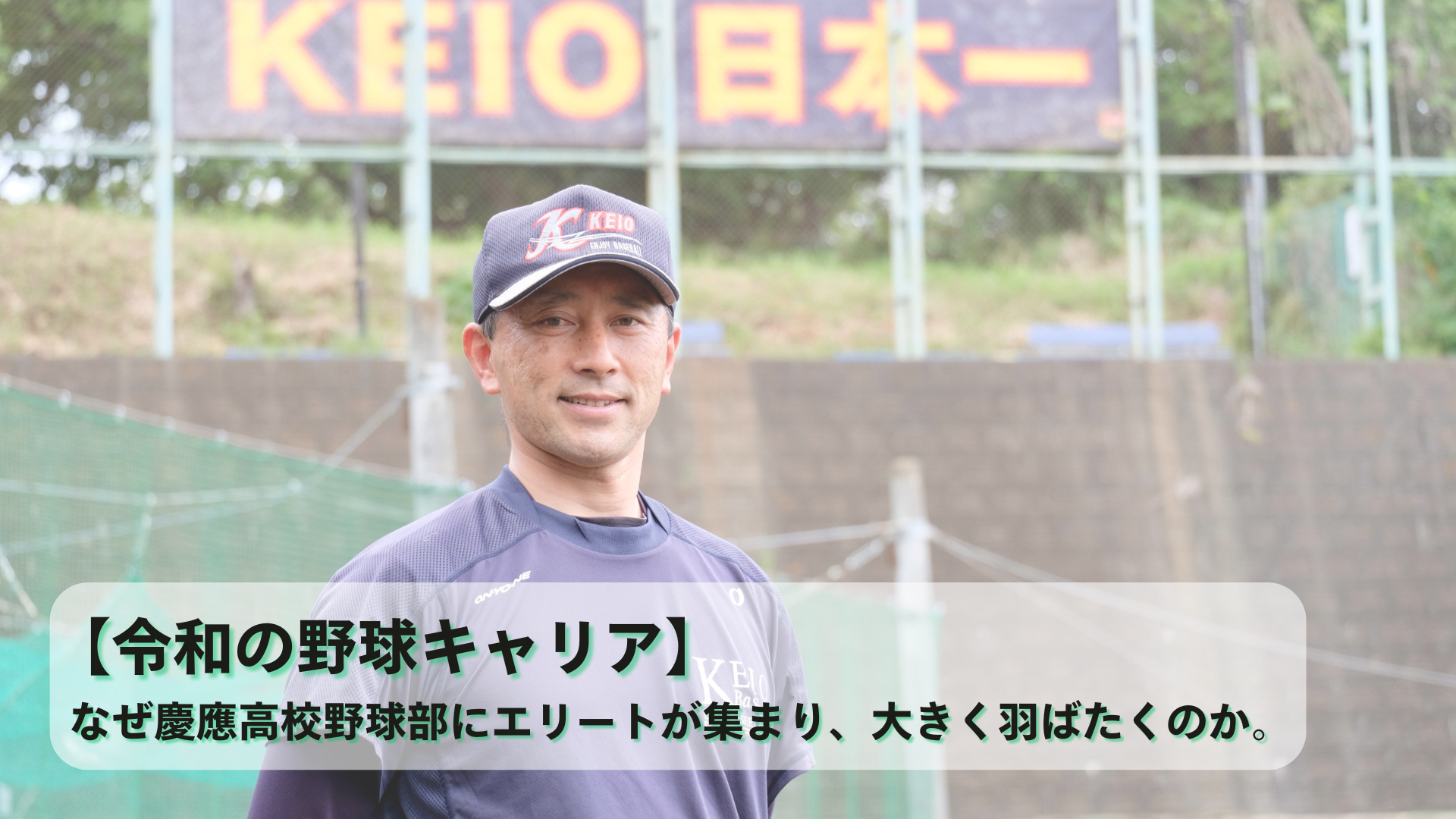
記事へのコメント