
全日本野球協会(BFJ)と日本野球連盟(JABA)の主催で2月22・23日に開催された第4回「野球データ分析競技会」。
最優秀賞に輝いたのが立命館大学大学院の影山敦紀さん、田原鷹優さん、渡部晴さんだった。
研究テーマは「タイミングをずらす変化球、評価できていますか?」。
プレゼンの冒頭で紹介されたのが、タンパベイ・レイズの左腕シェーン・マクラナハンの投じるチェンジアップの動画だった。
平均球速が約155km/hのマクラナハンはMLBを代表する豪腕左腕で、武器の一つがチェンジアップだ。球速140km/h台前半とスピードもあり、いわゆる「抜く」ような球種ではない。
まずはイメージを浮かべるために、こちらの動画などを参照してほしい(※動画の42秒、1分11秒などから投じられるのがチェンジアップ)。
プレゼンで示されたのが、変化量をプロットした以下の図だ。マクラナハンの投じるストレート(フォーシーム)とチェンジアップは、他の球種と比較して、似たような性質を持つことがわかる。

(本人提供)
それでも打者に対して効果を発揮するのは、ストレートとは約15km/hの球速差があり、「奥行き」を使ってタイミングを外すことができるからだ。
では、こうした変化球の価値はどうすれば適切に評価できるだろうか。

(本人提供)
上記の図にあるように、現在、投手の持ち球の評価は面積(二次元)で表される。
上図でもストレートとチェンジアップは近い位置に落とし込まれているが、面積では「奥行き」で勝負するチェンジアップを評価しにくい。
「平面上の面積で評価する方法だと、奥行きが見られないという問題点があります。それを現場レベルでは感じていました」(影山さん)
「空振り率」と「体積」の相関
そこで立命館大学大学院チームは今回、体積で評価する方法を試みた。ボールがリリースされてからホームベースに届くまでの到達時間を用いて、奥行きを評価しようとしたのだ。


(本人提供)
以下が分析の結果を表したものだ。

(本人提供)
体積と面積の相関関係を調査したところ、どちらで評価してもあまり変わらないという数字が出た。
だが、両者の空振り率との相関を調べると、体積のほうがわずかに空振り率との関連が強かった。

(本人提供)
空振り率を採用する理由は、「フェアゾーンに飛んだ打球の3割がヒットになるため、投手はフェアゾーンに打たせないことが重要になる。そのため空振り率が高いと、ヒットの確率を下げられる」からと説明された。
以上の研究による結果、「面積より体積のほうが投手の持ち球を評価する上で有効である可能性がある」と立命館大大学院チームは指摘した。
その上で、最後に出されたメッセージが以下だった。
「(変化量の)縦・横と合わせて、到達時間を含めて持ち球を評価することが重要です。現場に向けて言うと、変化量は小さくても球速差があれば、それも有効な変化球だと考えます」
「緩急」とは何か?
指導現場では「ピッチャーは緩急が大事」とよく言われるように、速いストレートと遅い球種(カーブやチェンジアップが代表格)をうまく組み合わせた場合、打者のタイミングを外しやすいと考えられている。
ボールの「速い」と「遅い」はイメージで捉えられがちだが、速球を基準に考えた場合、どれくらい「時間差」があるのかということだ。カットボール(Cut fastball)やツーシーム(Two-Seam fastball)も英語の表記を見るとわかるように、速球(fastball)を派生させた球種と言える。
冒頭で言及したマクラナハンのチェンジアップは140km/h台前半の球速が出ているものの、フォーシームと比べれば「遅い」。似たような軌道を描くが、球速差を巧みに利用して打者を打ちにくくさせているのだ。
以上のような現象を定量的に評価した立命館大学大学院チームは今回、見事優勝に輝いた。
「大学院に入学した頃からこの大会に出たいと話していたので、シンプルにめちゃくちゃうれしいです」
そう喜びを表現したのが、今大会への参加を提案した影山さんだ。現在はスポーツ健康科学研究科に在籍し、卒業後はバイオメカニストを目指しているという。
一方、立命館大学野球部で初代アナリストとして活動してきた田原さんは今回、3度目の出場で初めて最優秀賞に輝いた。

「1回目は予選落ちで、2回目は本戦に出場したけれども入賞はできませんでした。今回初めての最優秀賞で、『三度目の正直』に。一つ目標にしていたところなので良かったです」
田原さんは昨年のプレミア12にデータ担当として参加した経験も持ち、卒業後はオリックス・バファローズでアナリストとして活動していく。
かたや、渡部さんは立命館大学大学院のスポーツ健康科学研究科に所属。管理栄養士の立場から栄養や食事とパフォーマンスの関連性を研究し、2024年シーズンから立命館大野球部もサポートしている。卒業後はプロ野球に携わる進路を希望しており、今回、3人でのチーム結成に至った。
多士済済の立命館大学大学院チームは今回、現場で抱いた課題意識から研究をスタートさせ、見事に最優秀賞を受賞した。第4回「野球データ分析競技会」で新しい視点を提示した3人は、今後も野球界で大いに活躍してくれるはずだ。
(文/撮影:中島大輔)

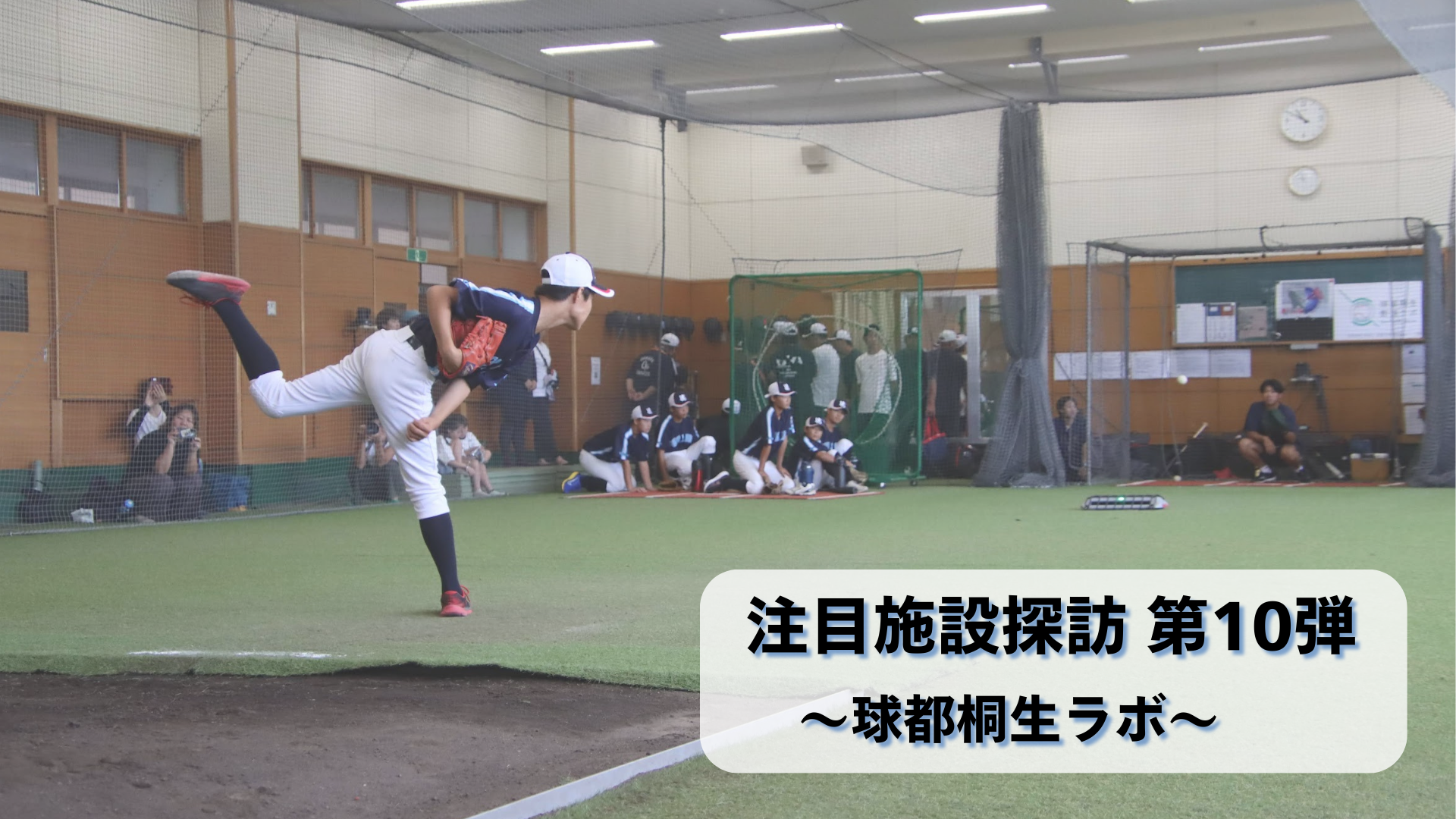




記事へのコメント