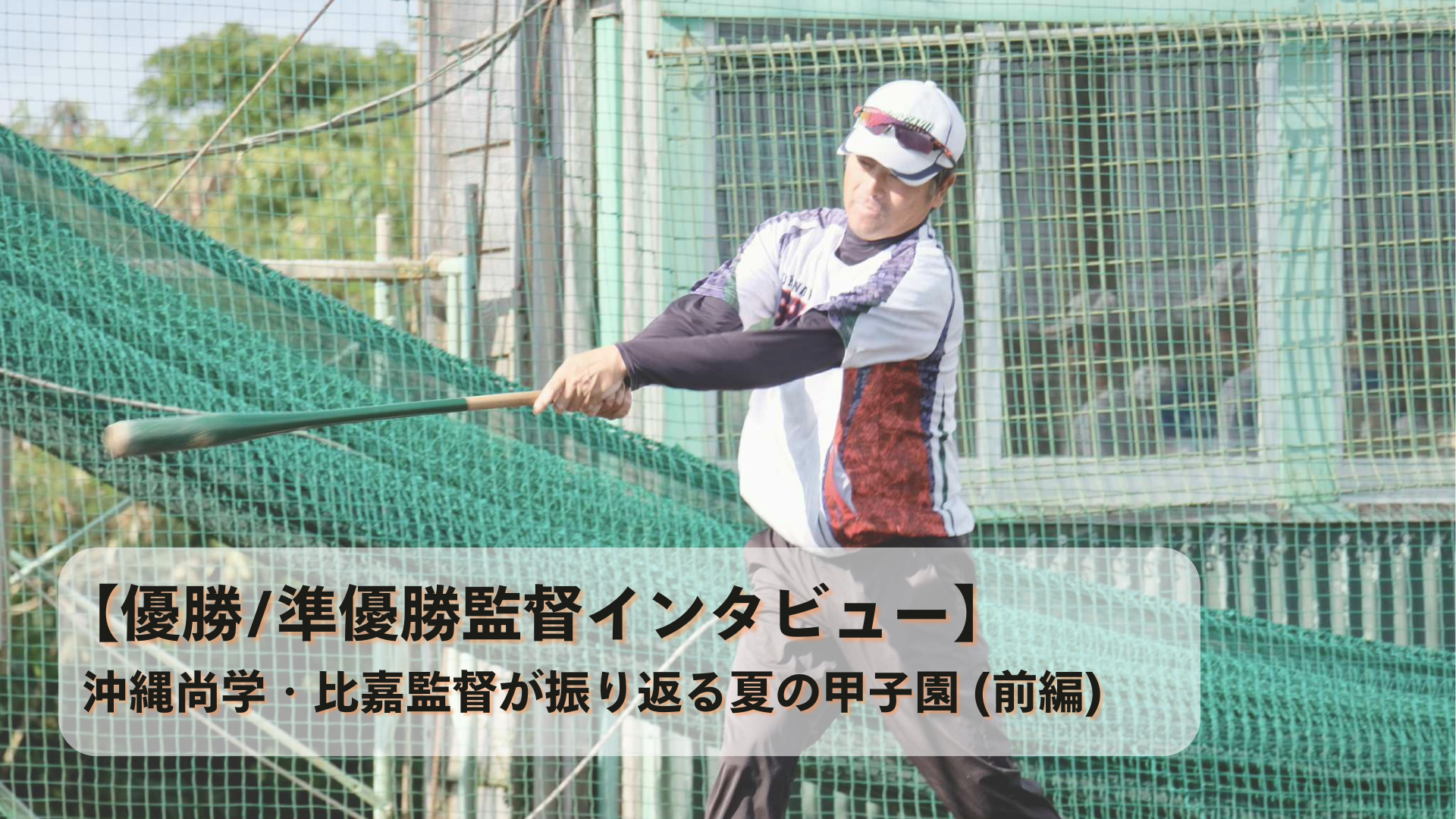
第107回全国高校野球選手権は沖縄尚学が初制覇を果たし、戦後80年の年に沖縄尚学が夏の頂点に立った。
1999年に選手としてセンバツ制覇、2008年には監督としても全国優勝を経験した沖縄尚学の比嘉公也監督はこの夏を「奇跡」と振り返っている。その戦いの中にはどのようなストーリーがあったのだろうか。
準決勝での「奇跡」の巡り合わせ
決勝戦では3-1で過去二度の夏制覇を誇る日大三を下しての優勝。投手力を軸にした堅い守備力が際立った初載冠だったが、大会前から沖縄尚学の下馬評が高かったわけではなかった。優勝に導いたのはそれこそ神がかったかのような比嘉公也監督のマネジメントだった。
なかでも、今大会のハイライトともいえたのが、準決勝の山梨学院戦だ。それまでエースとして引っ張ってきた末吉良丞を6回途中4失点したところで交代。3点のビハインドを背負ったが、その裏、一気に3点を奪って同点。7回裏に1点を勝ち越して逆転勝ちしたのだった。代わって登板した二番手の新垣有弦が3回3分の1を2安打5三振無失点の好投で試合を締めてみせた。
投手交代もさることながら、相手のお株を奪うような集中打は見事というほかなかった。
だが、そんな神がかった采配も就任して15年になる比嘉監督は笑ってこう振り返る。
「これが高校野球あるあるというんですかね。山梨学院戦は同点の前に2失点した時はエラーによる失点だったんです。その後のチャンスではエラーした張本人に回ってきました。取り返すチャンスが来て、左中間の適時打を打つという巡り合わせが来るのはやっぱり結果的にうちの方に(流れが)あったんじゃないかなと思います。4番の宜野座が甲子園に来て覚醒するかのように打ち出したので4番に置くことになったんですが、代わりに後ろに下げたのが安谷屋でした。その安谷屋にチャンスが回るあたりは奇跡としか言いようがないと思います」
実は、そのエラーをした三塁手・安谷屋春空はこの日から打順を降格させられていた選手だった。打順の変更をした選手がその試合のキーマンになり、沖縄尚学は勢いに乗った。今や百戦錬磨の監督の一人となった比嘉はそんな巡り合わせを「奇跡」と表現したというわけである。

カギを握った甲子園期間中の投手起用
もっとも、この大会を制した大きな要因の一つは投手力だ。エース左腕の2年生・末吉はストレートが最速150キロをマーク。スライダーも球速があり、見極めるのが困難だった。1回戦の金足農を3安打14奪三振の完封勝ち。2回戦では4イニングを救援した後、3回戦の仙台育英戦では延長11回に及ぶ死闘を一人で投げ抜いて、優勝候補を撃破した。
ただ、末吉の活躍だけではこれまでは来られなかった。2回戦に先発した同じ2年生の新垣を随所で起用した。末吉の休息のための起用のようにも見えたが、準々決勝からはフル回転。準決勝の山梨学院戦での好投はまさに安谷屋の一打と同じように今大会を大きく左右した。
「1回戦からうちが対戦した相手はエースを後ろに置くという戦略をとってきました。仙台育英さんと山梨学院さん以外はエースが先発じゃありませんでした。他校さんはそうして6試合を勝ち抜いていくための投手起用をしているんだなって感じたんですよね。うちは今大会は2人しか起用できませんでしたが、みなさんこういう考えなんだなというのは感じたところでもありました」
2回戦で新垣を先発させていたから、比嘉監督にも複数投手起用の考えがなかったわけではない。しかし、3回戦でエースの末吉が169球の完投。さすがにこれだけ一人を投げさせたら無理をさせられないと腹を括ったのだった。新垣―末吉の継投ばかりだった戦略から、準決勝で初めてエースを交代させるという決断に至ったのだった。
「言葉がいいかどうかわからないんですけど、賭けというか、これでダメだと仕方がないという半ば諦めの気持ちと言いますか。表現しにくい起用になるんですけど、選手の将来、怪我も可能性としてあるので無理させるわけにはいかないなっていうのは、正直なところありました。ここは負けたら仕方がないと思って、新垣のスライダーに(相手がハマることに)賭けました」
これが功を奏する。誰もが沖縄尚学=エース末吉という構図はここで一気に変わったのだ。
いわば、そうしたマネジメントの成功が今回の優勝に繋がったわけである。
それぞれの決断にあった比嘉監督の考えはどうだったのか。

功を奏した打順組み換えの意図
まずは打順の変更について。
「トータル的に見るとどの選手の状態がいいのかは1年間のなかでなんとなくは見えてくるので、そういった時に状態のいい選手がいるのに後ろに置いておく理由がないというふうに考えます。そして動かすことによって、逆に(下げられた選手は)奮起するというところもありますし、クリーンアップの責任から解放されて伸び伸びすることもあります。逆に打順が上がった選手は思い切ってくれればと思っていました」
状態がいい選手がいなければ打順変更の必要はないが、今大会は大きく変えた。準決勝は1番の新垣瑞を3番、4番の安谷屋を6番。5番だった宜野座が4番。3番の宮城は5番という変更ぶりだ。
山梨学院戦の3点ビハインド時は4番の宜野座が二塁打で口火を切り、宮城がチャンスを広げると安谷屋が2点適時打。エラーもあって同点になった。打順を落とされた選手は気が楽になり、奮起もしようする。調子のいい選手の思い切りと、そうした力が働いての成功だった。「状態がもう誰も変わらないのであればそのままで行くしかないが、明らかな違いがある場合にはどんどん変えていく」という指揮官の方針がはまった。
一方、投手起用については、
「投手は2枚・3枚いないと勝てないぞっていうようなミーティングはしている反面、負けたらこれで終わりだっていうところも現実的にはあるので、どうしてもエース頼みになってしまうんです。これまでの大会での僕自身の反省でもありました。ただ生徒たちも勝つために一生懸命やっているので、エースより力の劣るピッチャーに交代するのはどう感じるのかなと決断ができないことは多々ありました。今大会はそうではなくて、初めてエースを下ろして新垣を投入して好投してくれた。なんで今までそうしてこなかったのか。自分のこれまでの決断を恥じましたね」
反省を口にするところはさすがの比嘉監督であろう。どういう形であったにせよ、これらのマネジメントがなければ、下馬評を覆す事はなかった。ただ、比嘉監督はそうした采配やチーム力の背景にあったのは数多くの経験だったという。
神がかった比嘉監督が今大会で学んだことをこう総括する。
「大会の中ではピッチャーが2枚いたというところは大きいと思うんですけれども、その夏の大会の前に神宮大会やセンバツなどで、普段は練習試合をしないような相手と戦えたことが、『やればできる』とか『あまり相手を上に見過ぎない』という感覚にはなれたことが大きいかなと思いますね。センバツでは横浜と初めて試合してすごく強かったんですけど、その反面、横浜を上に見過ぎていたところが僕自身にもあったかなと。そういうのはすごく大きな経験でした」
取材する側から見れば、沖縄尚学は甲子園の常連だ。横浜と肩を並べているような存在に見えるが、本人たちからしてみれば遠い存在だったのかもしれない。これからは追われる立場になるだろう。そんな沖縄尚学がどのような存在になっていくのか。今や名将になった指揮官とともに楽しみなところでもある。
(取材/文:氏原英明、写真:中島大輔)






記事へのコメント