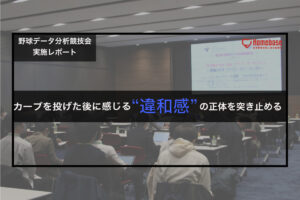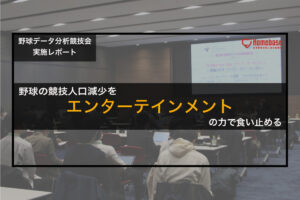トヨタ自動車・佐竹功年。言わずと知れた社会人野球のレジェンド右腕は、巧みな投球術と制球力を武器に、いまなおチームに欠かせない存在であり続けている。近年は、後輩たちにアドバイスを求められる機会も増えてきたというベテランは、これまでどのような指導を受けてキャリアを積み重ねてきたのか。自身の指導者論や、野球界の未来について思うこと、さらにはいち社会人野球プレイヤーとしての思いを聞かせてもらった。
“あの瞬間”をまた味わうために続けている現役 アドバイスに対する答えは「言い切らない」
1983年生まれの38歳。香川県立土庄高等学校、早稲田大学を経て、社会人野球の強豪・トヨタ自動車に入部したのは2006年のこと。そこから、15年目以上のキャリアを重ねてきた社会人野球を代表するレジェンドである。
「大会で勝って帰ったときに、会社の人たちが一緒に喜んでくれて、歓迎してくれるときの感覚は格別で、1回味わうとまたやりたいと思ってしまうんです。いつ引退するかは、周りが決める事だと思っているので、あまりフォーカスしていないです。勝ちたい、トヨタを強くしたいという気持ちはもちろんですが、いちプレイヤーとして、トヨタの価値を高めたいですし、社内でもより、野球部の価値を高めていきたいという思いでプレーを続けています」
チームのため、そして会社のため。ミスター社会人野球は第一線に立ちながら、まだまだ力を示し続けている。
言わずもがな、チームでは最年長の立場である。豊富な経験を持つだけに、後輩たちにアドバイスを求められることは少なくない。いち選手としてだけではなく、教える立場としても試行錯誤の日々を送っているという。伝える際に意識していることは、あくまで自分の考えとして線を引くことだ。
「聞かれたことに対して、自分の経験や率直に見たものの感想などは伝えますが、『それがすべて正解ではない』ということも併せて伝えるようにしています。相手が求めていることと、自分の知識が必ずしもマッチするかどうかはわかりません。ひとりの野球人が、ひとりの野球人に対して教えられる技術というのは、ほとんどないと思っています。技術論だけでもいっぱいありますし、さらにそこに選手それぞれに合う、合わないというのが重なってくる。なので、指導を仰がれた際にはあくまで自分の意見として伝えるようにしていますね」
フォームひとつをとっても、「こうした方がよい」という指導は難しい。例えば、全力疾走やカバーリング、牽制といった技術であれば教えられるが、アドバイスを求められることの中には“答えのない”ものも少なくない。十人十色の個性がある。だからこそ、あくまで、自分自身の意見であることを伝えることが、教える側の責任として、いまは捉えている。
練習は試合に向けての準備 大学時代に学んだ大事なこと
教え切らないことに至った経緯のひとつには、自身の経験が大きく左右している。というより、いろいろ経験してきた佐竹氏からしても、やはり技術論には答えがないという結論が根本にある。
「こうやって投げたら150キロ投げられるというのは全員に当てはまらないので、そういった指導はできないですよね。野球の技術に関して“絶対”はない。結局、ひとつの方法論を示すことしかできないんです。自分は、学生時代いろんな事を考えさせてもらいながらプレーをすることができていたと思います。考えさせられる材料を、指導者のみなさんが与えてくれたイメージです。結局、『自分で考えた事しか身につかない』のだなと。人から言われた事をやっているようじゃ身につかないということを、身を持って経験してきました」
長いプレイヤー生活の中で、数々の指導者の下でプレーをしてきた。その上でたどり着いた答えのひとつが、前述の「答え切らない」指導であり、「自分で考えることを促すこと」である。ただ、一方ではっきりと教えていいというものもあると感じている。ひとつは、自身が影響を受けた指導者のひとりである、早稲田大学で長らく監督を務めた野村徹氏の教えだという。
「準備の大切さ、1球目の大事さというのを常に叩き込まれました。正直、大学時代は理解仕切れていませんでしたが、社会人になって7、8年が経ったころに、こういうことだったのかとわかった気がしました。練習は、試合に向けての準備。これは、自分が伝えられることのひとつだと思います」
佐竹氏のいまにも活きているという野村氏の“準備”についての指導は、当時早稲田大でプレーした選手の多くが意識していると語っているほどに、根付いているものだ。多くの人にあらためて参考にしてもらいたい。

(佐竹氏は積極的に後輩とのコミュニケーションも取っている 写真:チーム提供)
トライしている今風のアドバイス 子どもたちに伝えてほしいこと
佐竹氏は、現役を続ける傍ら自ら野球専用のインスタグラムアカウントを制作し、DM等で技術論などの質問などに応えている。
「たくさん質問をもらっていて、いまのところは全部返しています。以前にやりとりした大学生が、自分が送ったアドバイスをもとに取り組んだ結果を動画で送ってくれたのですが、動画でみるだけでもすごく良くなっていて、少しでも力になれたのかなと感じてうれしかったです」
あくまで暫定的にはじめた取り組みだと話すが、野球界の発展のために、いち野球人としての発信をしていく覚悟だ。
「自分は社会人野球選手として、野球自体のさらなる繁栄はもちろんですが、会社のために野球部の価値を高められるようにしなくてはいけないという思いも持っています。SNSはその思いからはじめたものでしたが、野球人口が減っているという現実にも直面しています。なかなか指導やトレーニングに触れられる機会のない子どもたちの力に少しでもなれればよいなと思っています」
少しでも興味を持った方はぜひ、佐竹氏のインスタグラムからメッセージを送ってみて欲しい。
ベテランプレイヤーとして、いち野球人として、プレーを続けながらも指導と野球普及の課題にも取り組む佐竹氏。最後に、若い子どもたちに指導する立場の方々への思いを聞かせてもらった。
「ぜひ、愛情を持って接してあげてほしいと思います。私もいろんな方と会ってきましたし、僕たちの時代には厳しい指導はあったけど、最後に慕われるかどうかは愛情があるかどうかだと思います。どんなに厳しい先生でも、卒業後に慕われている先生はいっぱいいます。この選手を成長させたいと心から思っての行動は、厳しくとも指導を受けている側にも伝わるからです。それは、小学生を教える立場でも、社会人を教える立場でも変わらないと思っています。自分の為ではなくて、生徒がうまくなるために力を注ぐ事が大事だと思います。理不尽ではなく、愛情を捧げてもらえたらと思います」