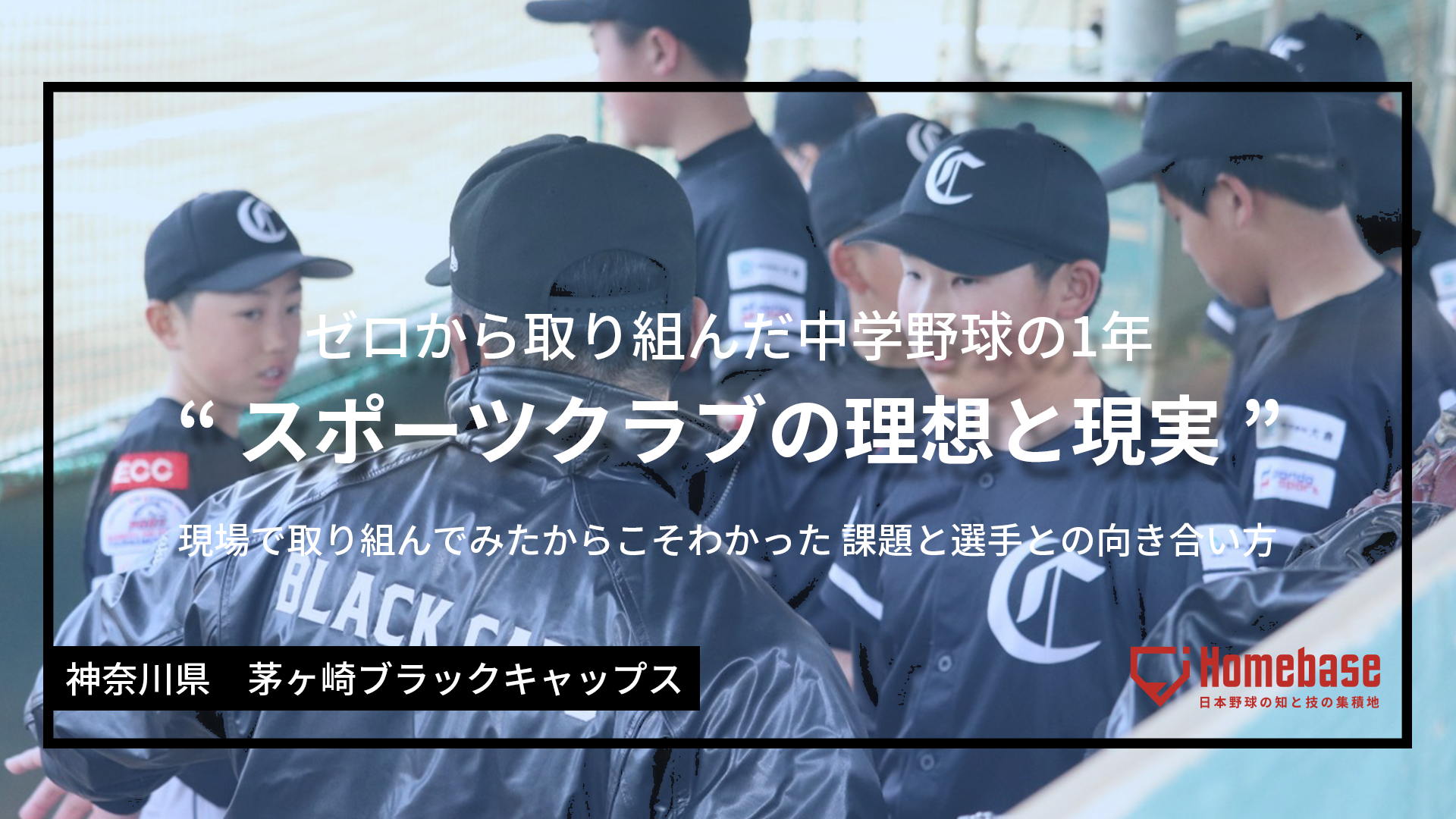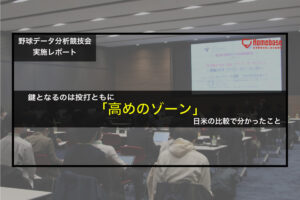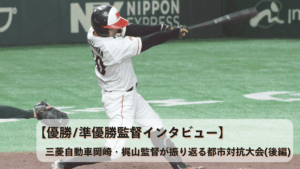総合地域スポーツクラブとして経産省の「未来の教室」プロジェクトにも採択された茅ヶ崎ブラックキャップスだが、きっかけは現在の中学校の部活動制度の現場での問題点だった。問題は主に以下の3点。
1つ目が先生の就労問題。通常授業の後や休日での活動は、就労時間の観点で見ると明らかにオーバーしてしまい、労働環境改善の対象となってしまう点。2つ目は顧問の人材不足。競技の経験者が、顧問になれればいいが、未経験者や希望していない人材が顧問になるケースも多い。そうなると指導者はレベルの差が大きくなり、公立の学校では、指導の質が担保できず、安定した指導も得られない現状となっている。そして3つ目は、少子化による所属部員の減少。高校野球でも夏の大会に合同チームでの参加が増えており、中学の野球部ではさらに深刻な状況だという。
現在、文科省を中心として、休日の部活動を外部指導員へ移管する取り組みも行われているが、受け皿として成立するのかを検証する目的で採択されたのだ。
この過程とチームの立ち上げ時の様子を見ているとを見ていると、チームづくりは順調のように見えるが、実際の運営は現実と違う部分も多かったという。今回は、チーム発足からの1年間での苦労や成果についてお話を伺った。
発足1年目に感じたチーム運営の難しさとチーム拡大へのハードル
実際に年間を通してチーム運営を経験してみて、わかった事は多い。チーム全体の取組としては順調で計算としては強くなると確信はしているが、まだ1年目が終わったばかりで取り組みの効果の証明ができていない。2年目を迎えるにあたって、新1年生の入団募集を開始し体験会も実施したが、結果的には1年生の入団を見送った。茅ヶ崎ブラックキャップスの代表である竹下雄真さんは言う。
「現在の14名の選手は、ある意味身内のところから集まった選手ですが、今回の新1年生は外部から引き入れることになります。いろんな方が体験会に来てくださり、違った価値観との出会いもあり、非常に良い機会となりましたが、チーム全体を考えたときにまだスケールするタイミングではないと考えました。」
また、1年間さまざまな媒体でプロモーションを行ったことで実際とは少し違ったチームの印象を持たれてしまうこともあったという。人数が増えることで、選手たちの考えや目標がバラバラになりやすいタイミングだったからこそチーム内ルールはブレないように考えていたという。
「うちのチームは、楽しくかっこよくをモットーにはしていますが、決して”ゆるい”チームではないんです。選手たちにも伝えてますが、どれだけ本気でできるかを常に追及しています。土曜日は参加できないけど、日曜は試合出してくださいとか、他の習い事やってるのでそっち優先でもいいですか?みたいな体験会参加者の方もいたんです。ただ、それだとチームとしては、試合に出る選手として計算できない。試合には出せませんよ。という話が出たこともありました。」

また、ポニーリーグという所属団体での長所と短所とも向き合うこととなった。ポニーリーグは中学野球の主要4団体の一つで後発のリーグである。本部はアメリカで、2020年には選手ファーストの考えを提唱する「SUPER PONY ACTION 2020」を制定し、フォームのロングパンツOKやスパイクのカラーも自由など今までの野球界の常識にとらわれない施策を進めている。
「ポニーリーグは、いわゆる個性を認めるリーグです。日本の野球界の良い伝統とストーリーがある中で、縛られることなく選手のために変えられるところは積極的に変えていこうという団体だと感じています。我々が加盟する時にもいろんな意見交換をさせていただきました。中学硬式野球主要4団体で人数が1番少なくレベルも低いと思われがちですが、プロ野球選手も巨人・高橋由伸選手やオリックス・宮城大弥選手などそれなりに輩出していますし、そこまで他のリーグと大きく差があるとは考えていません。」
と言うとおり、さまざまなメリットがあると確信しながらチームの加入を決めたが、ここでも運営する中での壁に当たる。
「ポニーリーグの特色のひとつに各学年ごとの大会があります。学年ごとの試合を行うことで選手たちは年齢に縛られず試合経験を得ることができ、選手たちの戦術理解や試合の流れを感じる洞察力は早くから習得できます。一方で指導者のリソースの点で考えると、各学年で大会に参加するとなるとチームごとに監督が必要になり、コーチも比例して必要となるので指導者の根本的な必要人数が増えるという問題が出てきます。これが、新学年の加入を決断できない一つの理由でもありました。」
こういった、さまざまな理由が混ざり、2022年は総合的に判断し、新入生の入団は見送ったブラックキャップス。ただ、今後の選手加入方針は固めておらず、今の選手たちを卒業まで届けて終わりということではなく、目に見える成果を出し、モデルを確立できることができれば新しいチームの形としてなりうるだろう。モデルケースだからこそ、現実的な判断をその度に行っている印象だ。
チームビルディングで考える多様性という名の”選択肢”
「チームの方針はそれぞれなので、これをやれって言うものはないと考えています。ウチが新たな選択肢になればいいかなと思っています。」
竹下さんへ令和のチームのあるべき姿について伺った時の言葉だ。続けて、竹下さんは自身の想いを口にした。
「正直、他のチームがどうなるべきだなんて大それた事は言えません。結局、人生って選択の連続です。ウチのチームのビジョンとして、今まで経験したことのない特別な体験をして、ジャイアントキリングを成し遂げたい。と言う明確なビジョンがあり、このビジョンとチームの雰囲気に賛同してくれる人でチーム運営をしていければ良いと思っています。私自身、スポーツクラブマネジメントの修士もとっていますし、マネジメントのプロだと自負しています。クラブの活動に必要なルールを作り、そこに賛同する人たちが集まる。シンプルですよね。その方針に共感できるかできないか。そこは個人の選択だと思っています。入ってみて合わないなと思ったら、辞めてもいいんです。それぞれのスタンス、スタイルが重視されている世の中になってきてますから。」
竹下さん自身も高校野球経験者で、野球の素晴らしさを感じているからこそ、チームのストーリーを作っていくことが、野球界の歴史を繋ぐことだと考えている。
「野球や甲子園が発展した歴史をみても、ストーリーしかないですよね。昔の強豪校みたいに、信じられないくらい自分たちを追い込んで、正直意味わからない理不尽にも耐えてみたいなチームは見ててかつ野球だし面白いです。苦しみを乗り越えた仲間の絆は見てて感情的になりやすい。もし、出場校みんなが同じ時間しか練習しなくて、みんな髪伸ばして、自由に野球しますってチームばっかりだと面白くないんですよ。不良軍団が頑張って勝つとか田舎のハンデ抱えた高校が強豪校を倒すとかそういうストーリーがあるから面白い。チームの数だけストーリーを作る。なので、うちもその多様な選択肢の一つになればいいなと思っています。多様性の時代になるからこそ、チームを選ぶ選択肢が増えることが重要だと思います。」

子供たちと常に接するからこそ意識している「中人前」
茅ヶ崎ブラックキャップスでは、子どもたちへの接し方も意識していて、子供扱いも大人扱いもしないという。
「言葉にすると難しいんですが、いい加減ではなくちょうど良い加減に接していきたい。今の時代、自由に育てる風潮になりつつありますが、放任ではなく、必要な時は叱ることも必要だと考えています。」
実際、叱る行為は労力が必要であり、叱った後に、その子がどう感じているか、どう変わっていくのか。そこまでフォローしてあげることが「叱る」行為になるという。
「叱らない選択肢もあると思いますが、それは大人が楽をしてるだけじゃないか?と考えてしまうんです。ただ一つ言えるのは、彼らはもう小学生じゃないしある程度苦労して一人前の大人になっていくべきです。私は彼らと「中人前」として接するようにしています。」
チーム運営をしていく中で、成長を感じる一つの印象的なエピソードがあるという。ある試合の日、スタメンで出ていた選手が、試合序盤でランナーと軽く接触して、試合に出るか出ないかの判断をする場面があったという。
「トレーナーが彼の様子を見た時に、外傷もほとんどなく腫れや熱も持っていない状況の中、本人にどうするって聞いたら、交代したいって言ったんです。だから交代はしたのですが、本当は出続けて欲しかった。試合に出ている以上、試合の流れやチームの士気については、考えて欲しいと思っています。スタメン選手がここからって時に、簡単に『痛いので変わります』って言ってベンチでしょぼくれてたら、どうしてもムードは変わります。本人としては、チームに迷惑をかけられないという心理も働いたのだと思いますけど、チームとして最善を考えて欲しかったので、試合後に試合の流れの部分の補足説明も兼ねて説教をしました。たまたま試合観戦にきていた保護者にも、こういう意図で色々と話をしたのでフォローあればしてやってくださいと伝えました。翌日、その選手は普段通り練習に来てやらせてくださいと参加していきました。おそらく自宅で保護者の方とお話ししたと思うんですが、切り替えて練習に取り組んでくれました。このような経験をすることで、人間として成長していくと思いますし、それも中学生を預かる身としてやっていくべきことではあるなと思います。」
エピソードの一端からも、選手のために最善な指導を行うことを意識していることがわかる。全てが指示ではなく、任せるところは任せつつ考えるきっかけを与える。中学生という多感な時期の選手たちが指導対象となるため、ひとりひとりに合わせた対応方法にも繋がっているのだと感じる。

これまで、実際に運営してみてのお話を伺ってきたが、最後に今後の目標を聞いてみた。
「やっぱりジャイアントキリングですよね。小学校の時に学童チームで1番上手だった選手が進んだチームに勝ちたい。子どもたちにとっても1番身近な目標になりますからね。エリートじゃなくても正しい努力をすれば戦えるんだ。やれるんだ。って言う痛快な体験をみんなで成し遂げたい。それが一つの証明になって、みんなの希望にもなると思うんです。」
そう言った竹下さんの目には、子どもたちが3年生になった時にジャイアントキリングを達成する光景が浮かんでいる様だった。茅ヶ崎ブラックキャップスのストーリーは、このあとどんな展開を見せるのか。野球人として見届けたい。