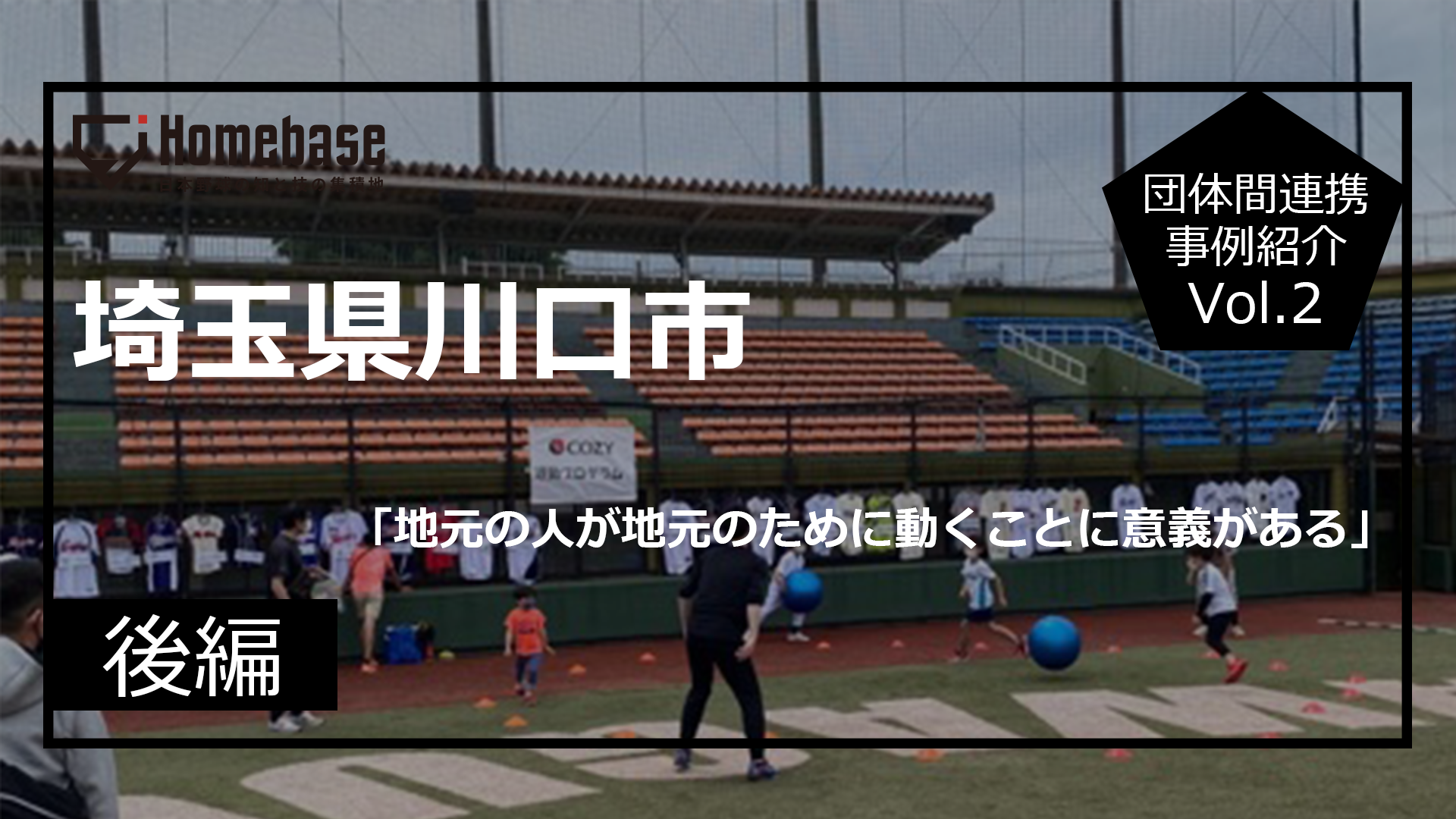埼玉西武ライオンズと連携して第1回目の「埼玉ベースボールフェスタin川口」が川口市営球場で行われたのは2019年のことです。翌20年に北スポーツセンターで行われた第2回は雪が降る悪天候にも関わらず300人が集まり、第3回はコロナ禍で中止。そして今年は、2年ぶりのフェスタが5月14日に川口市営球場で開催されました。
フェスタ開催と同時に発足されたのが、各団体が一堂に会して野球界の発展を考える「川口市ベースボールサミット」。発足当初は各連盟や団体間で意思の疎通を図ることは難しかったそうです。埼玉県高野連とはサミットの考え方について意見が食い違うことも……。
「市内の高校の高野連の先生に、川口市でサミットを開催したいと話したところ、『少年野球や中学の野球教室のイベントに参加した子たちの高校野球継続率調査ではいい結果が出ている、それと同じですね』と言われました。野球経験者向けに野球教室をしたら継続率が上がるのは当然のことです。しかも野球教室に行けるのは特定の学校の生徒でした。熱心な先生の所に来る熱心な子たちは、自然と野球を続けます。そういう機会に恵まれない子に野球をやってもらう場を設けたいのに、そこがなかなか分かってもらえなかったですね」
川口市をモデルケースに、19年には新座、志木、和光、朝霞の4市でも合同開催するなど、フェスタのすそ野は埼玉県全域に広がりつつあります。越谷市では「野球の町・越谷」というプロジェクトを立ち上げ、まさにフェスタをきっかけとして野球中心に地域がまとまりを見せています。今後は春日部市や熊谷市などの地区でも同様のフェスタを試みようと検討しているそうです。
地域ごとで行われるプロジェクトにおいて大切なのは、地元の人たちが地元のために動くことだと、武田先生は言葉に力を込めます。
「僕たちはきっかけを提示するだけで、実際にやるのは地元の方たちです。地元の人が地元のためにやらないと意味がない、と思っています。このフェスタをやることで作りたいのは地域のまとまり。さまざまなことを進めやすくするために『埼玉県野球協議会』を立ち上げましたが、実際には地区ごとに課題があるので、地区を動かすためのまとまりを地区単位で作っていかないといけない。僕は次に川口市の野球協議会を立ち上げたいと思っているんです。ボーイズ、シニアも含めて川口市全体で。硬式野球チームと選手の取り合いをしても仕方ないですから。地元が地元のために動くことに意義がある。そこが重要だと思います」
少子化や教員の働き方改革問題に伴い、中学校の部活動の在り方が大きく変わろうとしている今、地域間のまとまりはさらに重要度を増しています。
日本中学校体育連盟(中体連)は2023年度から全国中学校体育大会(全中)について、学校単位だけでなく、民間のクラブや団体としても出場できるよう、参加要件の緩和を議決しました。部活動の総合型スポーツクラブなどへの移行を推進するスポーツ庁の方針もあり、中体連も方向転換を求められたものです。参加要件の緩和によって「全中の出場選手は部活に所属する前提がなくなり、部活動が学校単位でなくてもいい」ことになります。しかし、実際にはクラブチームの全中への加入には多くの問題が山積しています。教員の負担はさらに大きくなり、自分の教え子が出ていない教員が全中を指揮するという矛盾も生じてくるでしょう。
「現在の中学校の部活動ガイドラインでは活動時間などの制限があって野球をやりたい子たちが十分にできない現状があります。そうなればクラブチームに行かざるを得なくなる。軟式野球の衰退は日本にとって大ダメージ。部活動のクラブ化と簡単に言いますが、すべての部活がクラブ化されるわけはないので、当然、部活動が精査されていくんです。この地区では野球はこの学校でといった具合に割り振られていく。単純に考えればチーム数は半減される。そうなってからでは遅いので、今野球をやっている子たちの環境を整えることを優先して、教員の手でクラブチームを立ち上げました」
このままでは野球をやりたい生徒たちの環境はどんどん奪われてしまう、危機感を抱いた先生たちが指揮を執って活動するのが中学生軟式野球クラブチーム「川口クラブ」です。現在、武田先生は同クラブのGM兼コーチを務めています。「川口クラブ」は2020年より中学生を取り巻く環境の変化に合わせ、野球をやりたい中学生に応える新しい運営方式に進化しました。現在は部活動に加入する生徒でチームを作り、市内で200人程度が加盟。それを4つの支部に分類して、4つの中でトップ、ミドル、フューチャー、育成とカテゴリー別に活動しています。
「地域スポーツクラブ的にしたい。野球だけでなく、他の部活動も賛同してくれれば、川口クラブの中でサッカーやバドミントンがあってもいいと思っています。野球の現状で言えば、各チームでかなりのレベル差があるので、初心者が多いチームにいる上手な選手たちがすごく苦しんでしまう。逆の状況も起こり得ます。せめて土日のどちらかは各自のレベルに合ったチームで活動させてあげたい。トップの子は切磋琢磨するし、ミドルの子は普段は自信がなくても活躍すれば自信を持てる。技術的に足りない子たちは練習を中心にやっていく。その中から代表チームを引っ張り、最終的には全日本につなげていくという形でやっています」
全国を目指す生徒もいれば、そうではない生徒が目指せる目標も作る。それぞれのニーズに合う環境を子どもたちに提供しているのです。市内の全中学校(25校)が加盟し、各学校の教員同士で連携可能なのも強み。「全中予選は各学校単位で出ようとか、足りないところは合同でクラブとして出ればいいんじゃないかという議論もできる。いろいろなチームが混在すると選手の取り合いも生まれるわけですが、それがないのがメリットです」
県事業部部長など、数年間にわたって数々の組織をけん引してきた武田先生ですが、ある程度の基盤ができた後は役職を後任に引き継ぎ、「川口市の土台を早く作って、『川口クラブ』で目の前の子どもたちを何とかすることに一番エネルギーを使いたいですね」と、目を輝かせます。野球を続けていく道は一つではない。その道しるべを、子どもたちに示すことへの情熱は尽きません。〝子どもたちファースト〟で真摯に取り組む川口市のような事例が全国に広がれば、野球人口減少の危機を食い止める光が見えてきそうです。
(取材・文/斎藤 聖己)