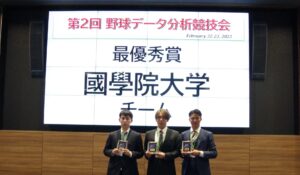来月開催される第95回記念選抜高校野球大会の21世紀枠最終候補9校に残った稚内大谷は日本最北端の北海道宗谷地区に位置する。1年の半分は土の上で練習できない大雪国だ。高校球児にとって過酷な練習環境をもたらす雪だが、稚内大谷の選手たちはその雪を通して宗谷地区の高齢者とコミュニケーションをとっている。「道北の子どもたちで甲子園へ!」を合言葉に創部して53年の野球部には昭和から続く伝統の活動がある。さらに「高校野球のために高校があるんじゃない」と語る本間敬三監督に高校野球の役割について伺った。
「今、雪かき終わったばっかりです」。1月末、本間監督の取材はこの言葉から始まった。この日は暴風雪警報が発令されたために学校は休校。稚内では決して珍しいことではなく、1年に2,3回あるという。日本最北端の北海道宗谷地区は降雪量だけでなく、風も強い。選手が駆け回る土のグラウンドは10月で姿を消し、以降は雪の上を駆け回る。「10月1週目に北海道大会から帰ってきて、上手くいけばそこから1,2週間グラウンドで練習できるかな。雨が降ると寒くてグラウンドが乾かない。秋風がすごく吹いてグラウンドの土も大変な状況になってくるので。11月から4月2週目くらいまで約半年、土の上では練習できないですね」。特に、11月と12月の2カ月間は「凍りあがっていない」ために、ボールを使った練習はほとんど行わず、走り込みや振り込み、基礎トレーニングに時間を充てる。“凍りあがる”とはグラウンドが完全に凍ってしまう状態の事で、そうなってしまえば土台がしっかりできるため、上の積雪をある程度雪かきして踏み固めれば白いグラウンドが完成し、ノックなどボールを使用した練習が行えるというわけだ。「ダイヤモンドだけはなんとか出して。当然土は雪です。外野で雪上ダッシュして雪を踏み固めたり、内野は濡れてもいいレインボールがあるのでそれを使ってノックやったりボール回しやったり。北海道は冬休みが長いので1月はみっちりそういう練習をやって、学校が始まったら週末は時間があるのでそういう練習に充てています」。土は見えなくても出来る限り本来の環境に近い状況で練習し、ボールとの距離感が鈍らないようにするなど感覚を失わないようにしている。野球部専用の雨天練習場もある。横20メートル、縦40メートルで「小学校の体育館ぐらいはある」。マシン2台並べて打撃練習し、ブルペンも2カ所確保できる。雪の時期は午前中がグラウンド、午後から雨天練習場での練習が日常だという。

室内練習場で打ち込む選手たち 写真=チーム提供
「早く土の上で野球をやらせてあげたい」という本間監督は、毎年3月上旬に北海道外に遠征へ行く。しかし、対外試合をするのも、かなりの時間と費用が必要となる。「稚内に空港はあるけど、風や視界不良で欠航が多かったり、どうしても交通費もすごくかかる。バスで6時間かけて苫小牧までいって、そこからフェリーで20時間揺られて福井県に入る。そこからバスで2時間くらいかけて京都に入ります」。移動だけで約1日半。この移動時間も遠征の大事な目的の1つである。「ただスマートフォンを触って眠たい時に寝るんじゃなくて、常にコミュニケーションをとりなさいっていうのは言っています。家に帰るまでが遠征だから試合しにいくだけじゃないんだぞと。例えばポジションが近い者同士が近くに座ったりとかそういった工夫をさせながら、移動時間を使っています」。

春先の遠征では、学校ではなかなかできない実戦練習や試合を集中して行う 写真=チーム提供 京都峰山球場にて
コミュニケーションを大切にしているのは部内だけではない。創部53年を数える稚内大谷は「道北の子どもたちで甲子園に」を合言葉に発足した。現在の部員28名も宗谷地区の選手たちで、漁師の息子などが集まっている。「地元の子をしっかり育てて甲子園にいこうってスタートして、社会貢献活動も昭和からずっとやっているんです」と本間監督が話す活動の一つが、独居老人宅の除雪ボランティアだ。昭和61年から継続して行い、地元の人でこの活動を知らない人はいないほどの伝統となっている。「社会福祉協議会から名簿を貰って、最低限の個人情報をいただきます。基本的に冬休み中に1回で、降雪状況をみて雪がバーッと降ったら、『よっしゃ明日行くぞ』っていって除雪に行きます」。除雪ボランティアの日は朝8時30分にスタートし、お昼休憩を挟んで午後3時ごろまで活動する。先日は野球部のジャンパーを着た部員が6班に分かれて、1日で110軒の高齢者宅を訪問した。「地域に支えられて活動させてもらっているので、困っている人をお助けしたい。お年寄りの方に『頑張ってね』とか『ありがとう』とか、そういう言葉をかけてもらって(この活動を通して)我々も色々なことを感じています。しっかり感謝して野球をやっていこうと」。稚内で開催される大会には応援にかけつけてくれたり、学校に『結果どうだった?』と連絡が来たりするほど地元の人に応援されているといい、これはまさに本間監督が目指す「温かい拍手を貰える野球部」である。

複数人のチームを組んで訪問をする 写真=チーム提供
「高校でのゴールは希望進路を達成して卒業していくこと。その中に野球というのがあるんだぞ、野球だけを考えてやっていてはいけないという話は常々しています。好きな野球をするためにはしっかり学校のこともクリアしないといけない。クラスメイトにも思いやりの気持ちを持たないといけないとか、そういう指導は野球の技術指導よりもすごく多いのかなという気はしています。勝てばいいんだろうではないですね」。お腹いっぱい大好きな野球をやるためには、その環境を自らつくらないといけない。本間監督は入学前にこのような指導理念や社会貢献活動の意義などを理解してもらえるまで説くという。「高校野球のために高校があるんじゃないんですよね」。順序を間違えないように、希望進路を達成してさらにその先につながる指導を心掛けている。近年では地元企業から「(稚内)大谷の野球部で誰かいないかい?」と声がかかるという。
思うように練習ができなくても、選手が1つ1つの意図を理解しながら取り組めば成長も著しい。全員が中学校の軟式野球部出身だが、昨秋は北海道大会ベスト16に進出した。「何か目標とかを生徒たちに常に見出してあげたり、叶えたいというものを与えてあげるとそこに向かって頑張れるのかなという気がしています。地理的困難でもコツコツやっていればやれないことないんだぞって。ハンデだと思ったら全部がハンデになってしまうので」と本間監督は過酷な環境をマイナスに捉えないよう選手たちを引っ張っている。野球部や学校関係者だけでなく、宗谷地区みんなの想いの詰まった野球部。今春、極寒の地に吉報は届かなかったものの、地元の人たちと温かい関係を育みながら既に夏を見据えている。