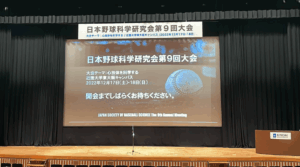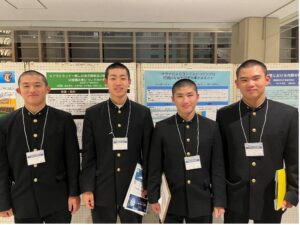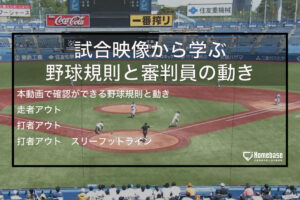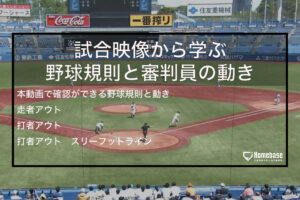アンパイアスクールの朝は早い。6時~7時頃に朝食を済ませると、7時半には移動開始。8時20分には野球場に戻り、準備体操とGo-Stop-Callで2日目のカリキュラムが始まる。Go-Stop-Callも変則的な球審バージョンが取り入れられた。
本日のカリキュラムのメインは、走者ありの場面での二人制メカニクスである。昨日と同様にまずはNPB若手審判員によるデモンストレーション、その後4班に分かれての練習を行う。4班のうち1班は投球判定を行い、ローテーションで4班が全カリキュラムを消化できるようになっている。二人制メカニクスでは1人・1プレイごとに、投球判定では1人ごとあるいは1球ごとに講師が受講者に声を掛け、個別のアドバイスを行う。当然、待ち時間もあるが、特に二人制メカニクスの練習においては、ノッカーの放つ打球や走者の走力、エラーの発生などで全く同じプレイが繰り返されるわけではなく、他の受講生が順番のときでも目が離せない状況が続く。
正午過ぎ、昼食休憩をはさんで、午後からはキャンプゲームと二人制の補講(抗議への対応や審判団協議の仕方など)が行われた。キャンプゲームでは、ボーク、妨害、ボールデッドの対応、故意落球やインフィールドフライなど様々なケースの練習が行われる。

マニュアルは全日本野球協会のサイト(https://www.baseballjapan.org/jpn/umpire/doc/campgame_manual_ver3.pdf)に掲載されているが、マニュアルを読んだだけで、実際にそのプレイが起きた時に素早く正しいジャッジをするのは至難の業。実際に練習し、時には失敗もすることで技術が身についていく。
キャンプゲームの練習の際には、稀に講師が監督役で審判員に抗議を行う。カテゴリーによっては監督が審判員に直接抗議をせず、選手を介して説明を求めるということもあるが、明確且つ簡潔な回答をして試合を長引かせないようにすることは共通。アンパイアスクールでは熟練の講師が審判員の動きをしっかり見た上で抗議を行うので、受ける側の受講生も大変だが、このような経験も役立つことがあるだろう。
最後に、各班代表者による模範演技と、Go-Stop-Call(集中力養成ドリル)でアンパイアスクールの全カリキュラムが終了となる。模範演技では、1日目と見違える動きで他の受講者を驚かせる受講者もいた。
今回のアンパイアスクールでは、初めて参加する受講者も多かったが、これまで何度も受講している方も多数であった。アンパイアスクールでは、動きの多い二人制メカニクスをメインとしていることと、若手審判員に機会を与えることを目的に、受講年齢に制限(通常は55歳まで。今回のみ3年ぶりの開催となったので57歳まで)を設けている。本レポートの最後に、今回が最後の受講となった吉永敏雄さんから事務局へいただいたメッセージをご紹介したい。
「12回参加させていただきました。今回が定年で最後になります。最初こそ審判経験ほぼなしで参加しましたが、大勢の方にしっかり教えていただき今では地元の学童連盟で審判長を務め、社会人県大会にも年に何回も出していただけるまでになりました。アンパイアスクールで教えていただいたことを励みにし、それを何回も練習したことが本当に生きております。まだまだ足りないところも多く今回が最後になるのは残念ですが教えていただいたことを振り返りながら審判を続けていきます。最後になりましたがアンパイアスクールと皆様のご健勝とご発展を心よりお祈り申し上げます。ありがとうございました。」
BFJでは受講した皆さんの声をもとに内容をアップデートしながら、NPBと共催のアンパイアスクールを継続・発展させていく。
(Homebase編集部)