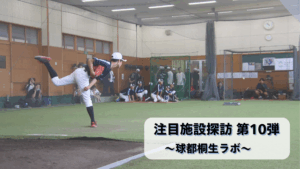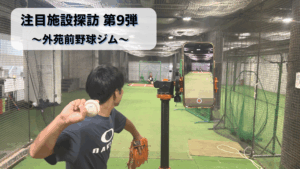前後編の後編。前編を読む
小中学生に自分の感覚で教えるのではなく、物理法則と身体の動作法則に沿って教えることを心がけている「Be Baseball Academy」の下広志コーチだが、初めから今のような指導法をできていたわけではない。
習志野高校野球部で3年夏の千葉大会で準優勝、大学時代はクラブチームでプレーした後、教える側に回ったのは卒業後に野球スクールを運営する会社で勤務し始めてからだ。
「最初は自分の感覚で教えていましたが、やっぱり行き詰まりました。引き出しに限界があるので、毎週同じようなアプローチしかできない。どうやってこの子に接していけばいいのかとわからなくなり、『今日もうまく教えられなかったな……』と自己嫌悪に陥りました」
下コーチは20代前半で壁にぶつかり、なんとか打破しようと論文や本を読み漁った。
「そのうち、『こういうフォームにすることで体のこういう機能が働くはずだ』と、動きの共通事項や根拠をなんとなく考えられるようになりました。『筋肉がこういう働きをするから、こういう場面ではこんな動きになったほうがいい』とか。それが肉付けされ、原理原則が大事だと行き着きました」
「上からたたけ」をどう解釈する?
物理や身体動作の法則は、地球上にいる全員に当てはまることだ。対して、自分の感覚が他者に当てはまるとは限らない。下コーチは揺るぎない根拠を持って教えるようになり、子どもたちの成長にも幅広く貢献できるようになっていった。
「例えば100人いたとして、感覚的な指導でも合う子はいます。5人くらいはポンと伸びるけど、残りの95人はそうではない。それが原理原則に沿って教えることで、全体が拾えるようになりました。
独特の感覚やクリエイティブな発想を持った子に対して、以前は『何言ってるんだ?』というのが少しあったけれど、原理原則をわかると『こういう動きになっているから、そういう感覚なんだろうな』と予測がつきやすくなりました」

野球の指導では、感覚的な表現が多くある。代表格が「上からたたけ」だ。その真偽にはさまざまな意見があるだろうが、重要なのは言葉の真意を捉えることだ。下コーチが続ける。
「本当に『上からたたく』とスイング角度がマイナスになり、長打はおろかヒットも打てません。でも、動作的にこういう動きを出したいなら、『上からたたけ』という言い方になるんだろうなと理解できます。『二枚越しで打つ』もそうですよね。事実と紐づけることで、そうした言葉で伝えたいことが解釈できるようになりました」
小学1年生も「わかりやすい」表現
「Be Baseball Academy」で練習を取材中、小学5年生の小杉蓮君に下コーチが「スイングプレーン」の話を始めた。バッティングにおける原理原則の一つだ(スイングプレーンの詳細は「スポチューバーTV」のHPでの下コーチの解説を参照)。
https://spotuber-tv.com/swing-plane/2577

「スイングプレーンはみんなにまず伝えます。バッティングで一番大事な概念なので。バットを振ったら、体の軸に対して90度になるのは物理現象です。それを一つ覚えておくと、例えば自分のスイングをチェックしたときに原則に沿っているか、外れているかという視点で判断できるようになります」
取材日の前日、下コーチは小学1年生への個人レッスンでもスイングプレーンについて伝えたという。
「手をぶらぶらして回ったら、大体90度になるでしょ? 回るのが遅いと手は下にあるけど、速く回ったら上のほうで回るよね。バットでも一緒だよ」
どうすれば、小学低学年にも伝わるのか。下コーチは言葉選びを大切にしている。
だからこそ、スクール生は「わかりやすい」と言うのだ。
教える相手が中学生になると、伝え方も変わってくる。
「相手に理解してもらう手段として、言語か、見せるのか、感じてらもらうか。その割合を変えていきます。中学生ならあえて言葉ばかりにして、『これってどういうこと?自分で表現してみて』と聞く。説明するためには自分のイメージを言葉に1回変換しないといけないので、どこまで理解しているかがわかります。逆に言葉で表現できていれば、動作の改善は近いはず。
もし理解できていない場合、あるいは理解できていても表現できていなかったら、練習をガンガンやらなければいけない。割合を変えてコミュニケーションを取りながら、子どもたちの様子を観察しています」
東京ならではのアプローチ
東京メトロ丸ノ内線の本郷三丁目駅から徒歩3分という好立地にある「Be Baseball Academy」だが、動けるスペースは50平米弱。限られた空間で野球スクールを開くのは、じつは社会課題を解決したいという下コーチの思いも込められている。
「東京はどこも狭いから、十分に動けないじゃないですか。公園でもバットを使えないですし。そうなると、自宅でできるメニューを提供してあげないと、そもそも自分で練習できない。昔と違って遊びの中で自然に能力が発達していくようなことがあまりないと思うので、今のやり方に至ったところもあります」

下コーチは現在の指導法にたどり着く上で、背中を押された言葉が二つある。
「原理原則はプロでも小学生でも変わらない」
前編でも紹介したが、トレーナーとしてプロ選手も指導する白水直樹氏や高島誠氏に言われた言葉だ。二人からそう聞き、下コーチは考えていたことが確信に変わった。
逆に言えば、小中学生こそ“立ち戻れる場所”が重要だ。だからこそ下コーチは物理法則と身体の動作法則に沿い、ラプソードを使った測定を大事にしている。トレーニングやドリル練習をうまく回すのもそのためだ。
もう一つの言葉は、前述の高島トレーナーに「一畳のスペースでもうまくなれますか?」と聞くと、「全然できるでしょ」と即答されたことだ。誰しも環境は限られているなか、どのように上達を目指すのか。そこにこそコーチの腕が問われている。
「隣の豊島区では十分な広さのグラウンドが一つしかありません。東京は環境的に限られているなか、東京なりのやり方を確立していかないといけない。そうしないと人はたくさんいるのに、いい人材が育たない土壌になってしまうので。
うちのスクールくらいの広さでも十分にうまくなれる知見を蓄え、東京の環境を整えていきたいというのが今の野望です」
誰にも訪れる、成長のタイミング
左打席から鋭い打球を飛ばす五十嵐幹太君は、下コーチに教わりながら自信をつけている。小学3年生で通い出した当初はスクワットを3回行ったら疲れた素振りを見せていたが、今は「きつい」と言いながらも回数を重ねられるようになった。
下コーチは成長を見守りながら、しっかり後押ししてあげられるように努めている。
「頑張れるようになったのは成長の証です。そういうシーンをどれだけフィードバックしてあげられるか。『頑張ろうね』と声をかけながら、粘り強く継続していくのが大事だと思います。そうやって野球がうまくなり、好きになっていけば、どこかのタイミングで自分に自信を持てるようになるはずです。
打球速度の計測もその一つです。打球速度が100km/hを超えてくると、子どもたちは『やった!』となってもっと打ちたがるので。幹太にも今後、そういうタイミングがどこかで来るだろうなと思っています」

指導者の接し方や教え方次第で、子どもたちの成長は大きく変わる。下コーチは自身の経験の中でそう感じ、一人でも多くの生徒を前向きにプレーできるように取り組んでいる。
その上で大切にしているのが、揺るぎない根拠を持つことだ。野球に関わる物理法則や身体の動作法則をわかりやすく伝え、子どもたちに身につけてもらいたいと著書『少年野球がメキメキ上達する60の科学的メソッド』を上梓した。
「基準点をちゃんとつくってあげることで、個人のやり方だったり、優れた感性や感覚だったりを磨けるようになると思います。科学で判明していることや、すでに当たり前にわかっていることはまず押さえてほしいですね。先人の知恵を踏まえたほうが、圧倒的にアップデートが早くなるので」
なぜ、「Be Baseball Academy」のスクール生たちは伸びていくのか。その背景にあるのが、下コーチの大切にする根拠だ。
(文・撮影:中島大輔 写真提供:下広志)