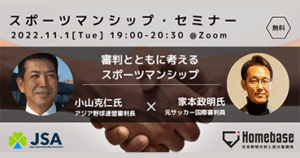かねてから話題になっていた中学校の部活動に関する問題。
今年の7月に文部科学省の教育課程部会の中で、「運動部活動の地域移行について」という資料が配布資料として参加者のもとへと渡った。
この「運動部活動の地域移行について」という資料はスポーツ庁が作成したもので、現状の中学校の部活動で検討されていることが記載されている。今回、Homebase編集部では改めてこの中学校の部活動に関する問題の沿革を整理し、記事という形で皆様にお伝えすることとした。読者の皆様が部活動をやっていた頃とは全く違う様相になっているという現状をまずは理解し、子供たちの未来のために我々に何ができるかを考える一つの材料になれば幸いである。
ここ5年で部活動を取り巻く問題について、以下の通り様々な議論が行われてきた。
①運動部活動の在り方に関する総合的なガイドライン(H30.3)①運動部活動の在り方に関する総合的なガイドライン(H30.3)
②新しい時代の教育に向けた持続可能な学校指導・運営体制の構築のための学校における働き方改革に関する総合的な方策について(H31.1)
③公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法の一部を改正する法律案に対する付帯決議(R1.11)
④学校の働き方改革を踏まえた部活動改革について(R2.9)
⑤運動部活動の地域移行について(R4.7)
運動部活動の在り方の抜本的な改革に取り組む必要性あり
平成30年3月にスポーツ庁から「運動部活動の在り方に関する総合的なガイドラインが発表された。
これまで、学校の部活動は学校教育の一環として行われ、日本のスポーツ振興を大きく支えてきた。体力や技能の向上を図る目的以外にも、異年齢との交流の中で、生徒同士や生徒と教師等との好ましい人間関係の構築を図ったり、学習意欲の向上や自己肯定感、責任感、連帯感の涵養に資するなど、生徒の多様な学びの場として、教育的意義が大きい、とされてきた。そんな中、少子化等の様々な問題によって、学校や教師だけで解決することができない課題が増えている。ことさら運動部活動においては、これまでと同様の運営体制では維持は難しくなってきており、学校や地域によっては存続の危機にある。(上記:ガイドライン抜粋)
といった現状と危機感のもと、将来のために、運動部活動を持続可能なものにする必要があると考え、運動部活動の在り方に関して、抜本的な改革に取り組む必要があるという動きになってきた。そんな中で策定されたのが本ガイドラインである。
以下の項目がガイドラインの中で明記されている。
①適切な運営のための体制整備
②合理的でかつ効率的・効果的な活動の推進のための取組③適切な休養日の設定④生徒のニーズを踏まえたスポーツ環境の整備
⑤学校単位で参加する大会等の見直し
①の適切な運営のための体制整備の部分では「生徒や教師の数、部活動指導員の配置状況を踏まえ、円滑に運動部活動を実施できるよう、適正な数の運動部を設置する。」という文言が記載されていた。
また、④の生徒のニーズを踏まえたスポーツ環境の整備の部分では更に、地域との連携という部分で「生徒のスポーツ環境の充実の観点から、学校や地域の実態に応じて、地域のスポーツ団体との連携、保護者の理解と協力、民間事業者の活用等による、学校と地域が共に子供を育てるという視点に立った、学校と地域が協働・融合した形での地域におけるスポーツ環境整備を進める」という文言が入っていた。

教員の長期労働と部活動
上記ガイドラインが策定されてから1年と経たない平成31年の1月にまた一つ議論となることがあった。
その議題が「新しい時代の教育に向けた持続可能な学校指導・運営体制の構築のための学校における働き方改革に関する総合的な方策について」というもので、これからの時代を迎えるにあたって、子供たちを指導する教員の働く環境を整備しようということである。
教員の勤務時間の長時間化には様々な理由があれど、その中の一つに部活動の指導時間が以前より長くなっているという指摘があった。この問題を解消すべく、スポーツ庁からは部活動ガイドラインの遵守を条件とした部活動指導員の配置促進を一つの策として挙げている。
また、この資料の別紙として中央教育審議会から文科省への依頼事項として挙げられていたことが、学校の業務の整理に関する資料である。
この中で、部活動は”学校の業務だが、必ずしも教師が担う必要のない業務”という整理がされている。しかし現状は業務の区分けはできておらず、教員が顧問として指導にあたってるケースが多い。そこで本資料の中では、
「特に,中学校における教師の長時間勤務の主な要因の一つである部活動については,地方公共団体や教育委員会が,学校や地域住民と意識共有を図りつつ地域で部活動に代わり得る質の高い活動の機会を確保できる十分な体制を整える取組を進め,環境を整えた上で,将来的には,部活動を学校単位から地域単位の取組にし,学校以外が担うことも積極的に進めるべきである」と述べている。
法律からのアプローチも進み、令和1年の11月には「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法の一部を改正する法律」が可決され、同法の附帯決議の中に「政府は,教育職員の負担軽減を実現する観点から,部活動を学校単位から地域単位の取組とし,学校以外の主体が担うことについて検討を行い、早期に実現すること」という文言が記載された。

部活動改革について
これまで様々な議論が行われてきた中で、スポーツ庁は一つの方策を示した。それが「学校の働き方改革を踏まえた部活動改革」である。この改革の中では大きく3つの方向性が示されている。
・部活動は必ずしも教師が担う必要のない業務であることを踏まえ、部活動改革の第一歩として、休日に教科指導を行わないことと同様に、休日に教師が部活動の指導に携わる必要がない環境を構築
・部活動の指導を希望する教師は、引き続き休日に指導を行うことができる仕組みを構築
・生徒の活動機会を確保するため、休日における地域のスポーツ・文化活動を実施できる環境を整備
次回の記事では、この示された改革についてそれぞれの詳細を改めて整理することにする。
今、中学校の部活動を取り巻く問題の解消に向けて、少しずつ形を変えてはいるものの確かに動き出している。そんな中、指導者として求められる役割も変わっていくことも大いに考えられる。Homebase読者の皆様もまずはこれまでの議論と現状をまずしっかり理解すること。そして、自分たちが大事に預かっている選手のことを考え選手ファーストの気持ちで選手たちと接してもらいたい。