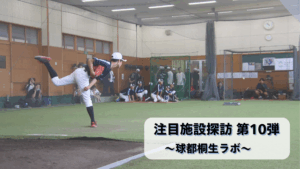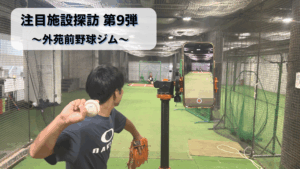東京都文京区本郷三丁目に「予約がとれない」と評判の野球スクールがある。「Be Baseball Academy」だ。
「バッティングがうまくなりたくて教室を探しました。動き方の説明をわかりやすくしてくれます」
そう話したのは、小学5年生の山本力輝君だ。
一方、同じく小学5年生の小杉蓮君と五十嵐幹太君は声をそろえる。
「下コーチは難しい言葉ではなく、子どもでもわかりやすい言葉で説明してくれます」
好評発売中の『少年野球がメキメキ上達する60の科学的メソッド』の著者である下広志コーチは、習志野高校野球部出身でダルビッシュ有(パドレス)世代だ。長らく都内や埼玉県のバッティングセンターで子どもたちを教え、昨年12月に「Be Baseball Academy」をオープンさせた。
同施設はマンションの地下1階にあり、動けるスペースは50平米弱、高さは3m強。スクールは基本的にマンツーマン型で、小中学生が中心だ。同じ学童チームに所属する小杉君と五十嵐君は隔週で一緒に受講している。
トレーニングも技術練習の一部
練習を見学していると、「Be Baseball Academy」の人気の理由が伝わってきた。
「膝が内股になるから気をつけて!」
山本君がウォーミングアップでスクワットを始めると、下コーチは留意点を簡潔に伝える。
「体のどこにテンション(張力)がかかっているかも大事だよ」

毎回、冒頭で欠かさずに行うのがトレーニングだ。スクワット、片足スクワットでは「縦方向の重心をきれいに使おう」と意図を説明する。
次はサイドランジで、「横方向に重心をきれいに使おう」と下コーチは呼びかけた。
自分の体を適切に動かせるように、上記のメニューは毎回必ず行っているという。
「子どもたちに『こうすると力が入るよね』とわかってもらうことに加え、できないことを体感してもらうことも大事です。例えば体の上のほうで2kgのおもりを持つと、足元がガタガタだとふらつきます。腕がすごく疲れちゃいますし。股関節、膝、足首が直列になった状態のほうが自分の体を支えやすい。
実際にやってもらうと、『そのほうがいい』とほとんどの子が体感できます。『スクワットのときも股関節、膝、足首が真っすぐに向くと、この姿勢ができやすくなるよ』と伝えると、技術練習からトレーニングまでが一本化されます」
ケトルベルを持ってサイドランジを行う山本君に対し、下コーチは「トレーニングも技術練習の一部なんだよ」と言った。
「 『股関節、膝、足首が直列関係の意識を持っておくと、バッティングやスクワット、ドリル練習でも全部いい動きができる』と説明します。そうすると要点を一個に抑えた上でいろんな練習ができるし、自分の指標にもなっていきます」

1時間のレッスン後に下コーチが保護者と話していると、自ら鏡の前でスクワットを始める生徒もいるという。
「その子の頭の中には『膝が内側に入っていないかな』、『スクワットのときにも動きがしっかりできているかな』と、今までになかった基準点がインストールされたのだと思います。鏡の前でスクワットをしながら、『ちゃんとできているかな』と自分の感性と対話していたのでしょうね。しめしめと思って見ていました(笑)」
「プロでも小学生でも、原理原則は変わらない」
下コーチが指導で重視するのは、物理法則と身体の動作法則に沿った動作だ。
バッティングやピッチングで理にかなった動きをできるようになるため、「トレーニング→ドリル→実際の練習」というサイクルを回していく。
ちなみにトレーニングは「フォームを習得するために、身体機能を上げる練習」、ドリルは「特定の動作を身につけるためのフォーム習得練習」を意味する。
スクールではウォーミングアップが終わると、山本君がバットを振り始めた。下コーチはスマホで撮影して体の使い方をアドバイスしていく。
「後ろに体重があるのに回っているから(腰が後方で)クッとなり、力が前に伝えられていないね」
下コーチはそう言うと、山本君にウォーターバッグを持たせた。体でうまく回転しながら、力を前に伝える感覚を体感させるためだ。

今度は右手でケトルベルを高く持ち、適切に支えられる場所を体で覚えていく。山本君はバットを持つと、収まりのいい場所で構えられるようになった。

バットをうまく振れない子どもたちに対し、どうやってできるようにさせていくか。スクール生たちが「下コーチの教え方はわかりやすい」と口をそろえるのは、上記のサイクルが機能しているからだろう。
つまりトレーニングで感覚をつかみ、ウォーターバッグなどを使ったドリル練習で動きを体に染み込ませ、最後は実際の練習で落とし込む。そうして打てるようになっていくわけだ。
「プロでも小学生でも、原理原則は変わりません。トレーニングをしてドリルを行い、普通の練習をするというサイクルを子どもの頃から回していく。野球人生は短いじゃないですか。10歳から始めて、大学までプレーしても12年くらいしかできない。
だからこそ目標をしっかり持ち、できるだけ無駄なくすごしてほしい。そういうサイクルを回せるようになるのは早いほうがいいと思い、子どもたちに伝えています」
計測で「目指すべき場所」が明確に
ドリル練習が終わると、下コーチがボールを投げてスクール生が打ち返していく。「前足がめくれないように」などと下コーチが注意点を伝えると、山本君、小杉君、五十嵐君は鋭い打球を弾き返した。
「今のは打球速度94km/h、打球角度21度だから、ギリギリ長打になるね。あと5km/h出れば100km/hくらいだから、外野オーバーになりやすい」
室内練習場にはラプソードが設置され、打球の速度と角度がモニターに表示される。バットのグリップには、スイング軌道などを可視化するブラストが装着されていた。

メジャーリーグではバレルゾーンという長打になりやすい打球速度と角度が示されているが、下コーチは計測をひたすら繰り返して小学生版、中学生版をつくった。それをスクール生たちに伝え、彼らは長打になりやすい数値を目指していく。
「自分の成長が記録で見られるのでわかりやすい」
小杉君と五十嵐君はそう話した。二人は競い合うように、より良い数値を出そうとスイングを繰り返す。下コーチはトスを投げながら、嬉しそうに見守っていた。
「計測して現在地を知れば、『これくらい打たないと長打にできないから、もっとトレーニングしよう』とモチベーションになります。単純に『今日は90km/h出た!』と自分の数値を見るだけでも面白いですよね。
今後アプリやデバイスはどんどん進化していくと思うので、小学生の頃から触れておいてほしい。中学生になると自分のスマホで動画を見返したりしているので、『スローモーションや遅延再生のアプリを入れるといいよ』と伝えています」
自分のプレーを計測することで、現在地がわかる。目標の打球角度や速度を示すことで、目指すべき場所が明確になる。「Be Baseball Academy」の子どもたちは日々の成長を実感できるからこそ、練習やトレーニングに前向きに取り組めているのだろう。後編へ続く
(文・撮影:中島大輔 写真提供:下広志)