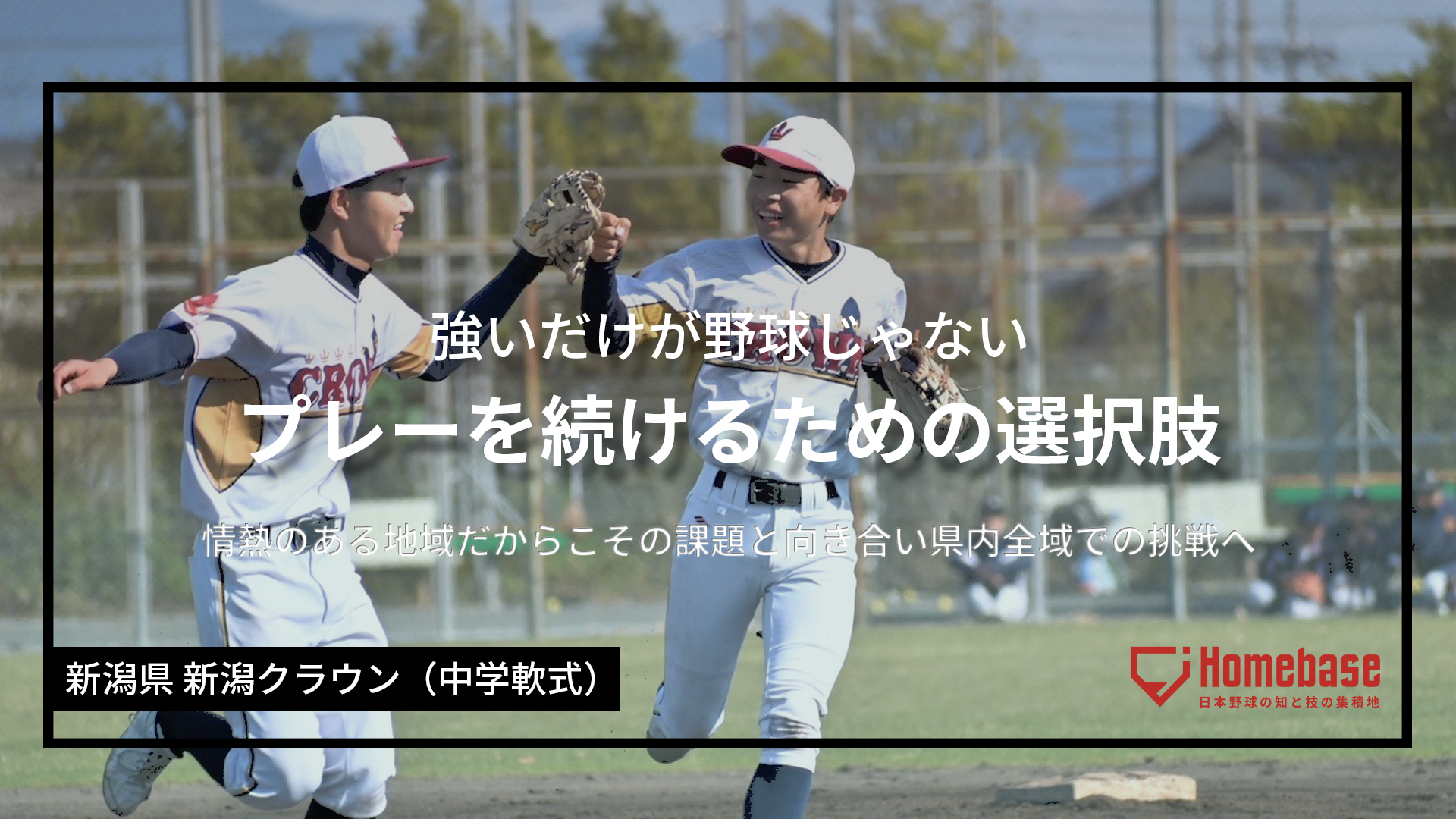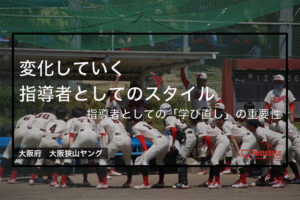「部活動問題」。これもまた、少子高齢化の日本において、スポーツ界が向き合わなくてはいけない問題のひとつである。指導者の数の少なさや、そもそも選手数が確保できないなどの要因が挙げられるが、新潟県ではまた違う課題を抱えているという。野球教室運営を通じて、新潟の課題と向き合い、新たに軟式クラブチームを立ち上げるに至った、新潟クラウン代表・江藤大雅氏に話しを聞いた。
情熱はある地域だが、やめてしまう子が多いという課題に
新潟県新潟市。古くから野球が盛んな地域のひとつであるが、例に漏れず、野球人口減少の課題と向き合っている。ただし、少し他の地域とは事情は違うようだ。
「新潟県は少年野球のチームも多いですし、野球をやる子ども自体は決して少なくありません。昨今話題となっている部活動問題についても、新潟の中学校の先生たちは情熱を持って指導されている方が多いですし、『新潟メソッド』と呼ばれる指導要領もあったりします。そういう意味では、“整っている部分”はあると思います」
そう語るのは、2019年より新潟県内で初の中学軟式クラブチーム『新潟クラウン』を立ち上げた江藤大雅氏。環境はあるものの、特に中学生指導における課題は深刻だという。
「とても情熱を持って指導をされる先生方がいる一方で、小学生はクラブチームでプレーをしながら、中学生になるタイミングで野球を辞めてしまう生徒の数が非常に多いのです。いろいろと話しを聞くと、地域柄、多くのスポーツに触れられる地域というのもあって、ステップを上がるタイミングで別のスポーツを選択してしまうということ。そしてそういう子どもたちの多くは小学生時代に野球を通じてあまりいい思いをできなかった子が多くて、部活動で続ける思いが持ちづらいということがわかりました」
江藤氏は、2012年から全国的に展開されている『ジュニアバッティングスクール』の指導員として、少年野球指導の現場に従事。15年に新潟県に異動し、そこから新潟県の野球少年・少女たちの実態に向き合ってきた。情熱のある環境がありながら、早くからリタイアしてしまう子どもたちが多いという地元の課題を改善すべく、行ったのが『新潟クラウン』の立ち上げだった。

続けさせてあげられる環境を用意するのが指導現場の役割
「2015年に新潟に異動して、翌年に独立したのですが、親御さんたちから中学生向けのクラブチームをやってほしいという声をたくさんいただいていました。理由は、部活動で野球を続けることへの不安などが大半でした。地元の指導が熱心だからこそ、中学校に上がって続けていく自信がない選手や親御さんがたくさんいたんです。表現が難しいですが、指導現場の実態と、子どもたちが続けるための環境がマッチしていない部分があったということだと思います」
江藤氏が新潟クラウンを立ち上げた2019年当時は、県内には軟式のクラブチームはひとつもなく、軟式野球を続けるには中学校の部活を選ぶほかなかった。身体の小さい選手で続けたいけどもう少しステップを踏みたいという選手や、ある程度進学先が定まってしまう義務教育の環境下において、進学先の野球部の熱量の差に不安がある選手たちからの声を目の当たりにした。「地区ではじめてなので、立ち上げは大変でした(苦笑)」と振り返りながらも、地元の指導現場で聞いた声を元になんとかスタートしたチームは、現在、20名近くの選手を抱える。
「卒団した選手が高校野球を続けてくれて、夏にはベンチ入りしたというような報告を受けるようになって、チームを初めてよかったなと思いますね」
地元の指導が熱ければ良いというものではない。野球が盛んな地域だからこそ、さまざまなレベルの選手を受け入れてあげる“選択肢”が必要になる。野球が好きな子どもたちに、続けさせてあげるための環境を用意してあげるということは、決して指導力を向上させることだけではないという事例と言えるだろう。

ちなみに、新潟クラウンでは指導の現場においても現場の“実態”に合わせた取り組みを重視している。
「うちのチームでは木製のバットを使っています。理由はいくつかありますが、ひとつは金額的なところですね。ご存知のとおり、軟式のいわゆるハイブランドのバットは一本4〜5万円ほどします。消耗品としては高い金額だと思いますし、私としてはさらに次のステップに進んで欲しいという思いもあり、難しいとされる木製バットでのプレーを推進することに決めました」
さらに、指導の方針も独自路線だ。
「選手たちを型にはめるような指導はしません。たとえば、小柄な選手だったら打球を転がすとかですね。中学生は3年間で身体も大きくなりますし、いまの段階で選手たちのタイプを指導側が決めるべきではないと考えています。それこそ、ある程度熱量を持って指導される部活動だったりすると、進学してくる選手たちは勝ちたいという思いを持っている選手も多く、そうなると勝つための自分の役割を演じなくてはいけないこともあると思います。それが悪いとは言いませんが、あくまで我々としてはそうではない指導にしたいなという思いですね」
選んでいるのは地元とはあえて“逆”の路線。結果的に、それが選手たちの個性を強く生み出すことにもなるかもしれない。
「強ければよい」からの脱却。いま求められる指導
19年に新潟クラウンを立ち上げ、現在は「クラウングループ」として、新潟市に隣接する三条市を中心とした、『県央クラウン』というチームも立ち上げた。「まだまだ地元の人の認知が低くて、選手が少ないですが、これから増やしていきたいです」と、同じ課題を持つ地域の中で、県内初のクラブチームブランドとして、指導をしていく覚悟だ。

「勝つための指導はもちろん大事ですが、それが全てではないと思っています。実際に中学指導の現場に携わってみて、県内外の強いチームの試合を目にすることもありますが、中には熱心ではありながらも、例えば少し相手チームに対して野次ったりするような雰囲気のチームや、声を荒げて指導しているような場面を目にすることもあります。全てが悪いとは言いませんが、私が向き合ってきた小学生たちの実態や、いまの野球界全体を考えると、“昔はよかったけど、いまはそうではない”ということも多いと思うんです。そういった指導とは真逆な方針なので、受け入れられない親御さんもいるかとは思うのですが、我々もブレずに取り組んで、野球を幸せに続けてくれる子たちを増やしていきたいですね」
いまどきの指導とは、型にはめることなく、選手たちの自主性を伸ばしていくこと。型にはめないというのは、指導の現場側にも言えることで、地域性やひいては選手個々に向き合ってひとつひとつ描くべきものである。
求められる場所で、求められる形でチーム運営をする。クラウングループは令和の時代の新たなクラブチームのスタイルといえるだろう。