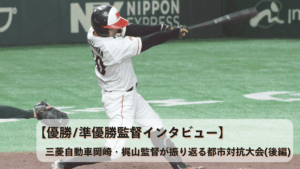野球人口減少が進む昨今、球界全体で課題とされているのが指導者の育成だ。
ロッテの外野手として活躍後、2025年3月まで「マリーンズ・ベースボールアカデミー」の校長兼コーチを務めた武藤一邦さんは67歳を迎える2026年、新たなチャレンジを始めた。「指導者や保護者が野球を学べる場をつくりたい」と、オンラインや対面で野球の技術や考え方などを学べる「BSC(ビスク=Bright Sprout for Coach)」というコミュニティをオープンさせたのだ。
「選手や保護者に選ばれるチームの監督やコーチは、どんな指導をしているのか。自分自身を振り返ったとき、そういう指導ができているという自信がありませんでした。それなら、もっと学ばなければいけない。そう考えて、指導者が集まれるコミュニティをつくることにしました」
“甲子園の魔物”が味方に
武藤さんの原点にあるのは秋田商業2年時の1975年夏、監督の“指導力”で人生が大きく開けた甲子園での経験だ。
「雪国のチームに地元の兵庫が負けるわけがない」。5年ぶりの出場となった秋田商業に対し、兵庫県立洲本高校の監督は新聞の取材にそう話した。当時、雪国の代表校は劣勢を強いられることが珍しくなく、率直な胸中を表したのかもしれない。
秋田商業の選手たちが対戦相手を強く意識させられた一方、今川敬三監督は本番までに万全の策を打った。甲子園で行われた各校の試合に出向き、選手各自に自分のポジションに近い席から観戦させたのだ。武藤さんが振り返る。
「僕はファーストの近くに座りました。サードからボールが来ると見にくいんです。当時の観客は色のついた服ではなく、白いシャツを着た人が多くて、ボールとかぶるんですよね。ちゃんと見ないとダメだなと、観戦しながら気づきました」
秋田商業の宿泊先は西宮球場のすぐそばにあり、プロ野球のナイターも見に行った。「プロのボールってこんなに速いんだ」。地方から出てきた秋田商業の選手たちは、本番までに目が慣れていった。
迎えた初戦は初回に5点を奪い、9対0で快勝。大方にとって予想外の結果となり、朝日新聞は「甲子園の魔物」と表現した。今ではお馴染みの言葉が、誕生したのはこの試合だった。
「事前に一生懸命準備して臨み、“甲子園の魔物”が僕らに味方してくれました。一つの試合に対し、ここまで緻密に臨まなければいけないんだなと。指導者はここまで選手のことを思ってやってくれるんだなと感じました」
武藤さんにとって、その後の野球人生に大きな影響を及ぼす一戦となった。
「練習は世界で一番ヘタだと思ってやれ」
翌年、夏の地方大会を前に秋田商業に激震が走った。今川監督が交通事故で逝去したのだ。
武藤さんは恩師の遺影を持って2年連続の甲子園に出場し、大会後には高校日本代表に選ばれた。そして秋のドラフト会議では南海(現ソフトバンク)からドラフト1位で指名されるも、これを拒否する。今川監督から「早稲田大学に行って、六大学でプレーしてからプロに行け」と、遺言を残されていたからだ。
受験で早稲田は不合格となり、法政大学に進んだ武藤さんは1年時からベンチ入りを果たした。初めて4番に座った2年春の初戦では初打席初本塁打を放ったが、以降は長いスランプに陥る。「俺はドラフト1位だ」、「高校ではオールジャパンに選ばれた」、「六大学でも初打席初本塁打を放った」と過去の栄光にとらわれ、自分自身とうまく向き合えなかった。法大には指導に来てくれるOBもたくさんいたが、武藤さんは教えを請いにいけなかった。
3年春になってもトンネルから抜け出せないなか、転機となったのがリーグ戦を終えた後、ボクシングの三迫ジムに2週間通ったことだった。当時の武藤さんは腰痛を抱え、同ジムの関係者で元広陵高校野球部員からトレーニングに誘われたのだ。
己の拳で成り上がろうとする若手ボクサーたちは、ハングリー精神の塊だった。ロードワークでは街中であえて人混みのなかに飛び込み、ぶつからないようにかき分けていく。目の前の練習にどう取り組めば、最大限の成果を得られるか。自身と必死に向き合うボクサーたちを目の当たりにし、武藤さんはハッと我に返った。
その際に思い出されたのが、今川監督から亡くなる前にかけられた言葉だった。
「これから野球をやっていく上で、練習は世界で一番ヘタだと思ってやれ。逆に試合では、『俺がここまでやってきたんだから一番うまい』と思って打席に立ちなさい」
自分は一番ヘタだと思って練習に取り組むから、甘えや妥協が消える。ボクシングジムの若手選手は倒れ込みそうになるまでミット打ちを続けるなど、常にハングリーだった。
毎日修練を重ね、いざ試合ではそれまでの努力を自信に変えて臨む。そうして持てる力を存分に発揮せよというのが、今川監督の教えだった。
武藤さんは法大3年秋、ついにスランプから抜け出し首位打者に輝く。異なる環境に身を置き、発想や取り組み方が変わった成果だった。
「ボクシングジムに行った後、スイングの量を500回から1000回に増やして首位打者を獲ったわけではありません。人の性格は変わらないけど、考え方、やり方を変えることによって、成績は絶対に変わります」

プレー上達の“近道”
ロッテの外野手を経て、昨年春まで30年以上マリーンズアカデミーの校長兼コーチを務めた武藤さんは、指導者によく問いかけていることがある。
「子どもたちに、練習の目的をちゃんと話していますか?」
同じメニューに取り組むのでも、練習の目的を意識するか否かで取り組み方が大きく変わってくるからだ。
例えば、キャッチボールの目的は何か。武藤さんは小学5年以上の場合、直接問いかけている。「肩をつくること」という答えはすぐに出るものの、さらなる答えを求めると、口をつぐむ子が多い。
「いい?投球と送球は違うよね?」
子どもたちが自分で考えられるように、武藤さんは思考の方向性をアドバイスしていく。
「投球は、バッターに対してピッチャーが投げるよね。打たれたくないから、いろんなボールを投げてくる。でも送球は、アウトにするために味方が味方に投げるボールだよ。4年生の子が2年生の子にピューって速いボールを投げて、捕れないボールだとアウトできる? できないよね。それではキャッチボールの目的が違うよね?」
自分の送球を相手が捕球し、初めてアウトになる。そう考えたら、ワンバウンドでもいいから捕りやすい球を投げたほうがいい。キャッチボールの目的を理解すれば、アプローチも変わってくる。
「指導者がそう話せば選手の考え方や意識が変わり、プレーも絶対に変わります。だからこそ、目的をはっきりさせてから練習に臨む必要がある」
指導者がどんな声かけをすれば、選手は上達していけるか。意識や考え方をうまく刺激できれば、子どもたちは自然とうまくなっていくはずだ。
「指導者はよく『プレーを速くしろ』と言いますが、『ゆっくり正確に覚えなさい』と言うほうが確実で近道です。それがのちに、無駄をなくすことにつながっていく。プレーは黙っていても速くなる。速くするのではなく、速くなるんです」
子どもたちに上から教えるのではなく、同じ目線からアドバイスする。武藤さんが目指すのは、好影響を与えられるリーダーのような存在だ。
(文・中島大輔)