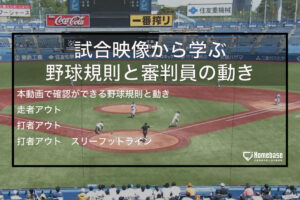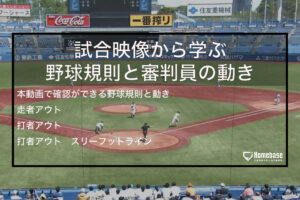みなさんは野球における審判ができた背景をご存知だろうか。野球の起源を知っていても遡って野球の審判員がいつからできたか詳しく知っている方は意外と少ない。
ここでは野球の由来となるスポーツの誕生とルールができた背景、そして審判の役割を30年以上審判員として活動してきたアジア野球連盟審判長ならびに、全日本野球協会アマチュア野球規則委員会副委員長の小山克仁氏に解説いただく。
アメリカで誕生したベースボールは、中世のイギリスで行われていたラウンダーズと呼ばれるスポーツが原点と言われています。それがアメリカに渡り、タウンボールと呼ばれる子どもたちの遊びとして広まっていきました。
後にタウンボールは大人も楽しむようになったことで、より紳士的な遊びにしようと1845年にニューヨーク・マンハッタン近郊で銀行員をしていたアレクサンダー・カートライトがルールを考案したと言われています。
彼は、銀行員として働く傍ら、消防団を組織して仲間と火災の際は消火活動などにも尽力しており、その仲間たちとタウンボールを楽しんでいたそうです。
アレクサンダーが考案したタウンボールのルールは以下の20項目となります。
1 時間厳守
2 審判を1名指名し、規則違反した行為を書き留める
3 会長から指名されたキャプテン2人は技量が同じになるようチームを決める
4 塁間は、42ペイス
5 練習日は対外試合を行わない。
6 試合開始にメンバーがいなくても他のメンバーを参加させることができる
7 試合後にメンバーが現れたらお互い同意すればメンバーに加われる
8 試合は21点で終了、アウト数は同じ
9 投手は下手投げで、打者の打ちやすいところに投げる
10 打者が一塁、三塁の線外に打ったらファール
11 投球を3回空振りして捕手が捕えたらアウト
12 チップを捕えたら打者アウト
13 走者は塁につく前に塁上の野手が捕球するか、タッグされたらアウト。走者にボールをぶつけてはならない
14 守備を走者が妨害したらアウト
15 スリーアウトで攻守交代
16 打者は順番に打つ
17 取り決め以外は審判が裁定。抗議は認めない
18 ファールは進塁はなし
19 投手がボーク・走者は一つ進塁
20 打球がワンバウンドでグラウンド外に出たらワンベース
このルール内には、審判を1名指名するという項目が含まれて入ります。つまり、ルール誕生と同時に審判という役割も生まれたことになります。
当時、審判に指名された人は、街で生活する人のなかで信頼がおける人が選ばれていました。弁護士や保安官、町長、校長先生などが審判を任されていたと言われています。
審判は、タウンボールの試合を和やかかつフェアに進行することが重要な役割となっています。そのため、野次を飛ばすような選手がいたら罰金を徴収していたそうです。
これは、アメリカの野球博物館に残されている最古のスコアブックにも記載されています。また、20項目の中には「取り決め以外は審判が裁定。抗議は認めない」とも記されています。
しかし、審判がどうしても判断がつかないというケースもあったようで、その場合は試合を見ていた観衆から意見を聞いて裁定をくだしていたと言います。
このことからも、審判が以下に試合進行において、重要な存在であるかがわかってもらえると思います。
次に、ストライク、ボールのコールが誕生した背景を紹介します。紳士的な遊びに進化していったタウンボールですが、プレーする側にとっては勝敗があるため、どうしても勝ちたい気持ちが強くなっていきます。
するとバッターは、自分のタイミングでバットを振りたいという意識が強まり、ボールを見逃すケースが増えていきました。
そこで、審判はスムーズな試合運びをするために、「Good Ball Strike」(良い球じゃないか、打ちなさい)とコールするようになったといいます。
これは1858年のことだと言われています。それから5年後には、バッターに打たれないために、わざと打てないボールを投げたピッチャーに対して、「Unfair Ball」(打てない球は投げるな、ずるいよ)というコールが認められたそうです。
このストライク、ボールの精神は、ストライクゾーンで打ち取るというメジャーリーグにもしっかり根付いていると言えるでしょう。