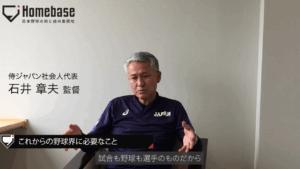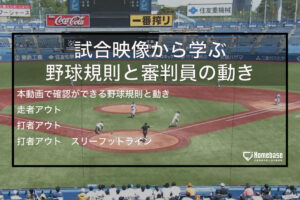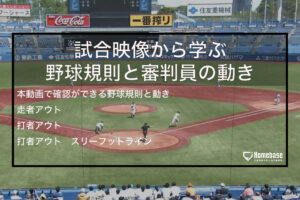このコーナーでは、アマチュア野球界で活躍している審判員に登場していただき、審判に対しての思いを語っていただきます。第1回目は、ルール誕生の歴史などの解説にもご協力いただいた小山克仁氏です。
国内のみならず国際大会でも数多くの試合に携わってきた小山氏に、30年以上の経験をもとに、審判とは何かを語っていただきました。
当サイトの「審判にも必要となるスポーツマンシップの心構え」のコーナーで、スポーツマンシップに欠かせない「尊重」「勇気」「覚悟」という3つの心構えを説明させていただきました。
これを踏まえた上で私自身、数々の経験の中から、野球の審判に置いてはこの3つの心構えを「リスペクト(尊重)」と「ジャスティス(正義感)」に置き換えられると考えています。
私の審判人生の中で、常に心がけてきたことは、打って、走って、投げてという野球の原点を楽しんでもらうこと。なぜなら、アレクサンダー・カートライトが定めたタウンボールのルール20項目にも集約されていることをベースにプレーすれば誰もが楽しんでプレーできると思うからです。
現在、野球のルールは200ページもの冊子にまとめられるほど多くなっていますが、元を辿れば、アレクサンダー考案の20項目にいきつきます。
野球が進化する過程で、選手の技術も上がっていき、さまざまな工夫がこなされてきました。その中には、ダブルプレーを阻止するために、セカンドゴロを一塁ランナーが取ってしまったり、盗塁を阻止するために、ピッチャーが偽投したりというケースが生まれてきました。
このようなズルが横行してしまえば、円滑な試合進行ができないだけでなく、みんなが楽しめるスポーツではなくなってしまいます。すべては全員がフェアに戦えるように、技術の進化とともにルールの変遷が行われているわけです。
その歴史背景を踏まえて、今のルールを尊重して、選手たちにプレーを楽しんでもらうかというのは大切なことです。
ルールの変遷の中で、私が印象深いと感じたのは、逆走が禁止になった事例についてです。1911年にメジャーリーグの試合でこんなことがありました。
ランナー一、三塁の場面で、一塁ランナーが盗塁。その後ランナーは三塁ランナーをホームへ返すため、途中で一塁に戻る仕草をして、挟まれようとしました。
しかし、キャッチャーは送球せずに、結果二、三塁となったのです。どうしても点を取ろうと考えた二塁ランナーは、次の投球で一塁に走って、キャッチャーに送球させようとしたそうです。それでもキャッチャーは全く反応しなかったといいます。
見ている側としては、こんなプレーが繰り返されると、まるで茶番劇をみているかのようで楽しめませんし、フェアなプレーでもありません。これが原因で逆走を禁止するルールができたと言われています。
勝ちたいからといって、アンフェアなプレーをしてはいけない。それを諭すのが審判の役割になるので、ジャスティスという正義感が生まれていくのかもしれません。
私自身もアンフェアなプレーを目の当たりにすると、これは許せないという気持ちが湧いてきます。その場合はすぐに、確認をして正しい方向へと指導をしています。
指導する際には、あからさまに行うのではなく、さり気なく選手に諭すよう「そういうプレーをすると、お互いに楽しめなくなると」といった具合に言葉をかけています。すると、多くの選手が気づいてくれます。
そんな経験も踏まえて私自身、審判として大切なのは「リスペクト」と「ジャスティス」なんだと思うようになりました。この2つの心構えを忘れずに試合を進行していけば、プレーする選手はもちろんですが、試合を見ている観客にも楽しんでもらえる審判になれると思います。