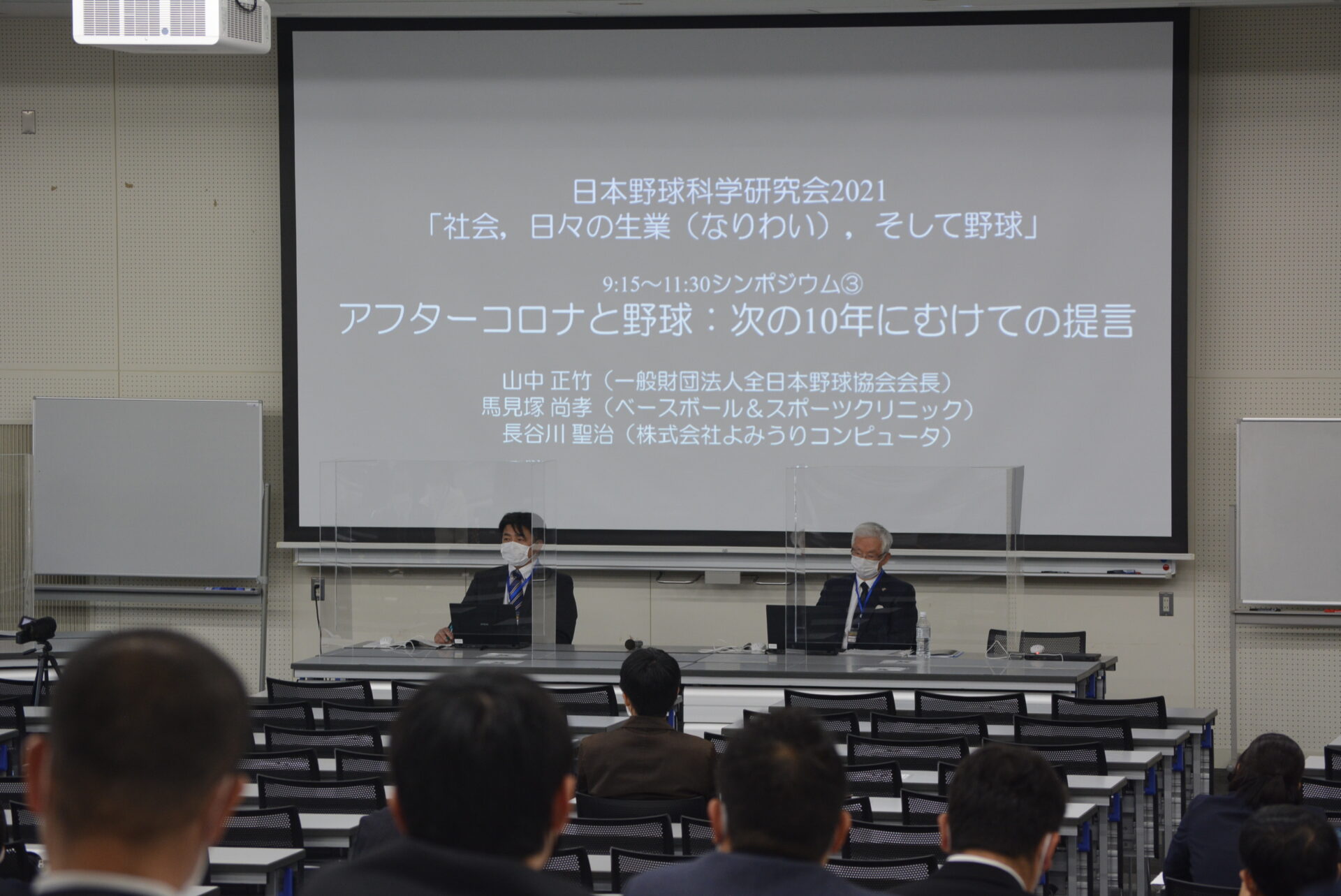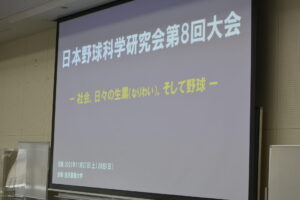2021年11月27、28日の2日間、石川・金沢星陵大学にて日本野球科学研究会第8回大会が開催された。
全日本野球協会会長の山中正竹会長、ベースボール&スポーツクリニックの馬見塚尚孝医師、株式会社よみうりコンピュータの長谷川聖治副社長がシンポジストとして登場。
「アフターコロナと野球:次の10年にむけての提言」をテーマにしたシンポジウムを振り返る。
競技人口減少問題解決には、医科学思想は欠かせない
主要大会の中止や無観客試合、練習の制限など、新型コロナウイルスの感染拡大は、野球界にも大きな影響を与えた。
完全な収束が見えない状況は続いているが、侍ジャパンがオリンピックで悲願の金メダルを獲得したことをはじめ、野球の力を世にアピールする出来事も数多くあった。
シンポジウムの司会を務めた長谷川氏は、冒頭で読売ジャイアンツ終身名誉監督・長嶋茂雄氏が文化勲章を受賞されたことにも触れ、「野球が文化であることが証明されたのではないかと思っている」と発言。
そして「今後、野球の魅力をどう伝えていくか、野球人口減少をどう克服するかを、医科学の観点を生かしてくることが重要なのではないか」と、今回のシンポジウムの意義を説明した。

本題では、最初に山中会長が、「野球に学び、野球から学ぶ」ことをモットーに野球人生を過ごしてきたことを紹介するとともに、自身が強化本部長も務めた侍ジャパンの回顧、野球界の組織や競技人口減少について、日本野球協会の使命などを説明。その中でも、山中会長の野球に対する思いの発言は印象的だった。
野球とは
野球は人生を豊かにする 最高級の遊びである
→楽しい遊びから真剣になる
→真剣だから学び・得るものが多い
→学び・得るものが多いから人として成長する
このような考えのもと、山中会長は「74歳までずっと野球と関わっており、まだまだ学びたいと思うからこそ今後も野球界とつながっていたい」と発言。
そして「指導者たちには、野球はこんなにすばらしいということを、自分の口から子どもたちに発信できるようになってもらいたい。それが大事」と自身の思いを語った。

山中会長の後には、馬見塚氏が「アフターコロナと野球、次の10年」をテーマに、自身の見解を発表。
「体育・スポーツの意義のなかの人材育成のポテンシャルが野球にある」として、自身の経験などを踏まえながら、今後野球界に必要なことを説明してくれた。
その中で、アメリカのやり方をそのまま取り入れてはいけないと前置きした上で、ロースター制度が用いられ、競争、選抜、淘汰が激しい中でも再チャレンジの場も用意されていることで、選手自身が良き判断をするトレーニングを受けられる環境にあると説明。
これが「コーチングにおける日本とアメリカの違い」として明確にあるなかで、日本野球の“令和の常識”をどう作っていくかが課題となると話した。
それぞれの発表への感想を述べた後、司会の長谷川氏が2人に質問をしていく。
ここでは、「野球は指示待ちのスポーツのイメージが強い。人材育成の観点でみると他の競技に比べて難しいのではないか」という質問が出た。
これに馬見塚氏は「日本は監督から選手へとトップダウンのやり方になっていますが、すべて監督が命令しているわけではないですし、コーチングにおいてマイクロマネジメントは良くないことは言われています。
人材育成のベースをどう形成していくかは、スポーツ社会学専門の方もいるこの研究会をはじめとして、野球界の中でも議論していく必要がある」と述べた。

最後にはシンポジウムに参加した人たちとの質疑応答も実施。
ここでは、幼稚園、小学校低学年の野球教室を行っているという参加者から、「今、野球は保護者から選ばれないスポーツになっている。特に母親から。そんな中で母親たちに向けたアプローチは考えていますか」という質問が出た。
これに対して山中会長は「母親の影響は大きいのは共通認識として持っています。また、練習時間が長い、保護者の役割分担が多いなど負のイメージが強いことも認識しています。それを払拭する意味でも医科学を活用して対策する必要がある。これは大きなファクターであり、そこを強く訴えていく必要がある」と、今後の展開を示してくれた。
少子高齢化に伴う人口減少の中で、いかに野球へ興味を持ってくれる保護者、子どもたちを増やしていくか。今回のシンポジウムを聞いて、今後の野球界発展には、各協会や連盟、研究会が策を考えていくのはもちろんだが、野球に関わる人々も含めて、いろんな意見を発信していくことが重要なことだと気付かされた。