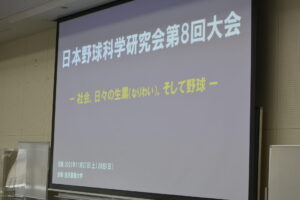2021年11月27、28日の2日間、石川・金沢星陵大学にて、日本野球科学研究会第8回大会が開催された。
今大会では、5つのシンポジウム、2つの教育講座、ランチョンセミナーが開かれ、さまざまな視点からの野球研究の内容が紹介された。
ここでは、その中から、元慶應義塾大学野球部助監督で、現在は朝日大学保健医療学部健康スポーツ科学科の准教授を務める林卓史氏が「野球における定量的データをもとにしたサポート」をテーマにしたシンポジウムを振り返る。
重要なポイントは選手自身がデータから何を感じるか
プロ・アマ問わず、さまざまなデータが測定されるようになった現在の野球界。そして測定したデータをどのように選手やチームの成長に役立てていくかが問われる時期に入っているといえるだろう。
今回のシンポジウムでは、林准教授のこれまでの研究だけでなく、慶應義塾大学野球部助監督時代の経験なども踏まえて定量的データが選手、チームの成長につながったかの成功例が数多く紹介された。
シンポジウムは、以下の内容で進行。
①投手へのサポート事例
②打者へのサポート事例
③定量的データを用いる副次的効果
④セイバーメトリクスを用いたサポート事例
⑤定量的データを用いたコーチングについて
⑥ディスカッション・質疑応答
いずれも興味深い話だったが、中でも投で紹介された関東第一高校・市川祐投手が成長を遂げた事例。
本来の投球ができていない市川投手の状態を見るために、Rapsodoで測定してほしいという依頼があり1度目の測定を行ったという。
その際に出た数字を見て、市川投手は、測定をしたことで自身の数値の物足りなさを自覚し、夏の大会へ向け、フォームの改善、指のトレーニング導入などを取り入れた。そして、夏の大会直前に2度目の測定をしたところ、平均球速が4km/hアップするなど球質が向上。
市川投手の成績向上の背景には目標設定の方法である「SMART」
Specific<具体的か>
Measurable<測定できるか>
Attainable<達成可能か>
Related<長期目標や自分の最終目標と関連しているか>
Time-bound<締切が決まっているか>
にマッチしたことも影響していると説明した。林准教授はこの成果を見て「自分自身もすごく勉強になりましたし、サポートしているこちら側が学ぶことが多かった」とも話していた。
また、自身が助監督をしていた2018年春の大会で慶應義塾大学が優勝できた裏には、セイバーメトリクスを用いたチーム分析の成果があったという説明も、会場に集まった野球関係者には役立つ情報であったに違いない。
2017年秋の大会でも優勝を成し遂げたが、そのときは強力打線が最大の武器だった。しかし、その軸を担っていたのが4年生ということもあり、新チームでは打力が落ちるという予想はされていた。
そこで、セイバーメトリクスで具体的にどれくらい打力に変化が出るかを予測し、18年春の大会をどのように戦えばいいかの分析を行った。その成果が見事に表れて2季連続の優勝につながったという。
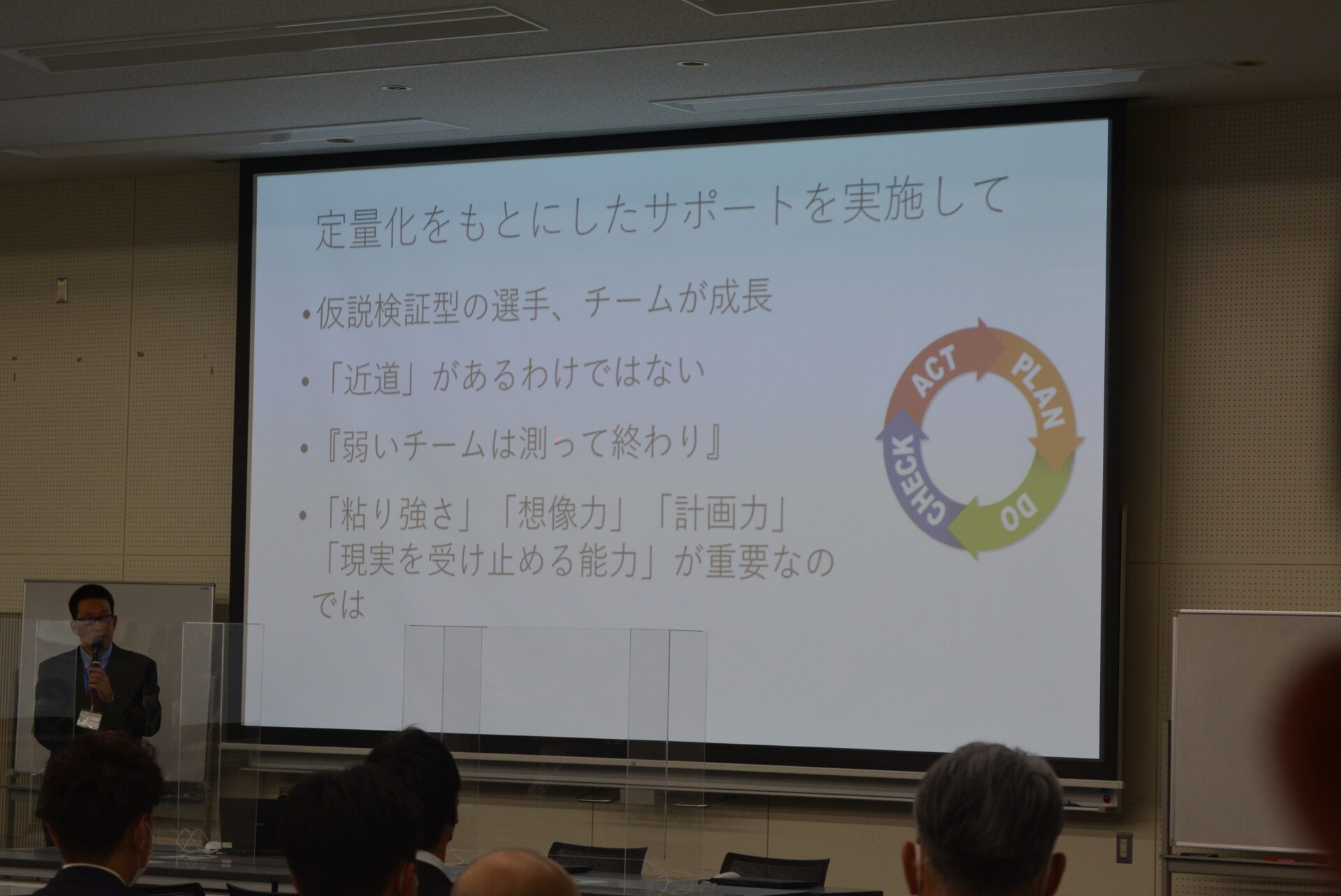
シンポジウムで紹介されたのは成功例となるが、失敗した例も多いという林准教授。
質疑応答の際、「自分がもっとできる、もっとやれるんだという自己効力感がないと、なかなか響かない。そこをどう育てるかはむずかしい。定量的データをフィードバックした際の雰囲気で伝わっているか、いないかを判断することも重要」とも話してくれた。
Rapsodoをはじめ、さまざまな計測アプリが使えるようになった今。このシンポジウムを聞いて、データをどう生かしていくかは、指導者だけでなく、選手自身の取り組みや考えで大きな違いが出ることは明確になったといえるだろう。