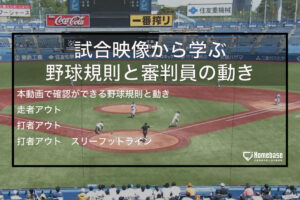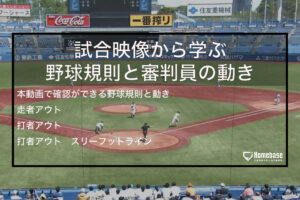野球を含め、さまざまなスポーツの試合を行う上で欠かせない「審判員」。試合を陰ながらまとめ、進行し、数々のドラマを見届けている審判員には、プレイヤーとはまた違った魅力とやりがいがたくさんある。
今回は、国際審判員の資格を持ち、国際大会や甲子園大会など、アマチュア野球における数々の実績を持つ山口智久氏に、そんな審判員の魅力について語っていただいた。
現役審判員が語る、選手との関係性、ジャッジそのものに対する考え方とは——。審判員の“リアル”に迫る。
-本日はよろしくお願いします。まずは山口さんが審判員を始めたきっかけをお聞かせください。
私が審判員を始めてから今年でちょうど20年になります。現在、母校である明治大学が所属している東京六大学野球連盟で審判員を務めています。
審判員になったきっかけは、私が会社員として働いていた時にちょうど明治大学の先輩審判員の方がご勇退されるということで、善波達也さん(明治大学野球部元監督)にお声かけを頂いたことでした。
東京六大学野球連盟の審判員は、所属校の野球部OBかつ各大学4人までという条件と定員が設けられています。
当時は仕事や家庭もあり、審判員を始める決断には悩みましたが、母校のために少しでも恩返しができればと審判員を務めることを決心したのがちょうど30歳の時でした。
当時務めていたホテルの会社を辞めて、お誘いいただいた善波さんの会社に転職し、社業の傍らで東京六大学連盟の審判員を務める生活がスタートしました。
大変ありがたいことに、会社や家庭の理解を得ながら、東京六大学以外にも甲子園大会や都市対抗野球大会、国際大会でも審判をする機会をいただくことができました。
-審判経験が豊富な山口さんが考える審判の魅力はどこにあると思いますか。
個人的な考えになりますが、野球の審判員はオーケストラで言うところの指揮者のような存在だと思っています。審判員の「プレイ」という声かけから野球の試合はスタートします。
試合の主役は選手ですが、その選手たちをリードして試合を進めていく立場に当たるのが審判員です。
「審判員は黒子であれ、厳格であれ」というイメージが強いと思いますが、“選手と一緒に試合を作り上げていく”という魅力はなかなか経験できるものではありませんし、非常にやりがいを感じます。
-プレイヤーをされていた経験は、審判をするのにも活きていますか?
直接ジャッジに活きていると感じることはあまりありませんが、元プレイヤーとして選手と同じグラウンドで時間を共有できることは嬉しいですね。
高いレベルの試合でジャッジすることで、私自身もっと上手にならないといけないなと感じますし、審判員の仲間と技術や心得を高め合おうという意識があります。
-審判員として、心掛けていることがありましたら教えてください。
最近では、選手への“声かけ”を強く意識しています。審判員の中では考え方が異なる方もいらっしゃるかもしれませんが、試合において初回の入りと、7〜9回は特に意識して選手への声かけを行っています。
特に7〜9回の試合終盤は、野球競技では大事な場面が多く、試合が動くことはよくあります。
負けているチームの場合ですと、ベンチ全体がひっそりと静まりかえっているケースも見受けられ、攻守交代のスピードも遅くなってしまいがちです。そんな時に選手を鼓舞する目的で声かけをしています。
私はあえて控え選手に「ベンチ全員でいくよ!守備からリズムを作っていくよ!」といったような声かけをすることもあります。控えメンバーの中には、チームの盛り上げ役のような選手がいることもよくありますし、そういった選手がチーム全体に声かけすることで雰囲気が変わることもあります。
審判員としては、試合が無事に終了し、最後に両チームの選手が礼をして、良い試合ができた喜びで握手できるような雰囲気の試合を作りたいと思っています。
-山口さんが選手に対して声かけをする様子は、一部のファンの間でも話題になっているようですが、球場で見ていても印象的です。
声かけの全てが正しいわけではありませんが、選手と一緒に試合を作っていくという考えを持っているうちに自然にそうなっていました。
加えて意識していることで、試合の中で“時間を貯めておく”ということがあります。なかなかご理解いただけない言葉かもしれません。私も当初は全く言葉の意味が分かりませんでした。
しかしながら審判員を続けていくうちに、少しずつ言葉の意味を理解できるようになっていきました。「試合が動く終盤に向けて時間を作っておく」という意味になります。
例えば、高校野球では伝令の選手がマウンドに行ってから、投手を含む内野手で話し合う時間は決まっています。
決まった時間については、バックネット裏にいる控え審判員が時間をカウントしていて、指で残りの秒数をグラウンド内にいる審判員に伝えています。球審は背中側でそのアクションが起こっているので、直接振り返って見ることはできません。
その場合、二塁塁審がそれを確認して球審にアイコンタクトやジェスチャーで伝えてくれます。球審は集まっている選手たちに「そろそろ行こうか!」と声かけをします。
試合終盤の大事な場面には、マウンド周辺で選手たちが監督からの指示や守備位置の確認を行うシーンや、目をつむり集中力を高めるシーンなどがよく見受けられます。
そんな大事な場面の時に、急かすように「そろそろ時間だから行こう」とはなかなか言いにくいものです。
個人的な考えですが、試合序盤で無駄な時間を省くことによって時間を貯めておき、その貯めておいた時間をこのような場面で使用することは、スポーツマンシップの実践であり、これによって大人としてより常識的で人間性のある審判員に近づけると考えています。
審判員は、選手が悔いなく最後まで全力プレイをして、いつでも選手ファーストで試合が行われるように必ず意識していると思います。