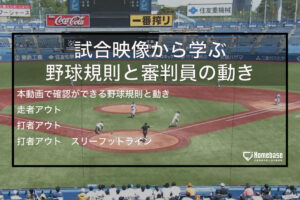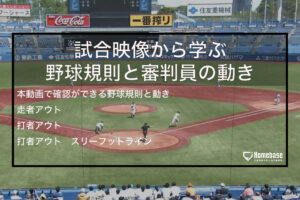野球を含め、さまざまなスポーツの試合を行う上で欠かせない「審判員」。試合を陰ながらまとめ、進行し、数々のドラマを見届けている審判員には、プレイヤーとはまた違った魅力とやりがいがたくさんある。
審判員として20年のキャリアを持つ、山口智久氏が語る審判員の“リアル”。第三回は大学野球での事例を中心に正確なジャッジについて迫った。
-山口さんは現在、東京六大学野球連盟に審判員として登録されていますが、印象的なジャッジや試合はありますでしょうか。
東京六大学野球連盟の試合ではありませんが、私自身が裁定したジャッジにおいて、とても印象的なものがあります。2021年の明治神宮大会、大学の部の決勝戦でのことになります。慶應義塾大学 対 中央学院大学の試合でのことでした。
この試合、私は、一塁塁審を務めていましたが、9回表1点を追う慶應義塾大学が1アウト1・2塁とし、一打同点のチャンスを作りました。その場面で打席に入った萩尾選手が放った打球は、投手正面に転がりました。
ダブルプレイのケースでしたが、萩尾選手が懸命にヘッドスライディングをした結果、私の目には一塁手の捕球よりも打者走者の手が一塁ベースに着くのが早く見えました。私は目の前で起きたプレイに忠実に、セーフというジャッジをしました。
しかし、中央学院大学の選手はダブルプレイの成立を確信していたのか、ベンチにいた選手がサードのファウルラインギリギリまで飛び出してきていたのです。その様子を見て、私自身は誤ったジャッジをしてしまったと瞬時に思ってしまいました。
試合後もずっとそのジャッジをしたことで、反省の気持ちを引きずっていましたが、その日の夜に懇意にしている審判の方から一枚の写真が送られてきました。
ファーストを守る選手のミットにボールが収まる前に、打者走者の手が先に触れているという一枚でした。とても安堵した瞬間でしたね。
普通に考えれば、容易にダブルプレイで試合終了になるプレイでしたので、頭の中ではアウトコールを連想してしまうことがあります。しかし、ジャッジするにあたっては先入観を持ってしまうことはとても危険なことです。
最後のプレイで落球する可能性もありますし、足がベースから離れてしまうこともあります。大事なことは目の前に起こるプレイに対して忠実にジャッジをすることです。
もちろんプレイの予測はとても大事で必要なことですが、やはり見たとおり忠実にジャッジができるようになることが理想です。
-プロ野球ではリクエスト制度の導入も進み、MLBのマイナーリーグではロボット審判を試験的に導入しているところも出てきました。
リプレイ検証は、審判員にとっても精神的には楽になるという側面もあります。序盤に裁定したジャッジを試合中ずっと引きずることになるのは、審判員としては良くないことですからね。
かつては、一度裁定したジャッジはなかなか変わらないということもありました。最近では、当該の審判員がジャッジした後、その裁定に疑問があれば他の審判員で話し合った上で、そのプレイが良く見えている審判員の意見を確認し、その判断に基づいてジャッジが変わることもあります。
野球やソフトボールの審判員が、他のスポーツの審判員と比べて相違点があるとすれば、それは一球ごとに対してジャッジを行う点です。
また球審を含めた試合のクルーは、起こったプレイに対して、フォーメーションを変えながらジャッジをしています。
ロボット審判は、基本としてストライクとボールを判定するだけですが、すべてのプレイをロボット審判がジャッジするには、まだまだ時間がかかるだろうというのが個人的な感覚です。
実際、卓球やテニスといった競技において審判員は、定点からジャッジをしています。しかし、野球やソフトボールでは審判同士のカバーリングも存在します。
専門的な用語ですが、クロックワイズメカニクスという動きがあります。例えば、3塁が空いた際には球審が空いた3塁のカバーリング動いて、他の審判員も時計回りに動くことがあります。
審判員間のコミュニケーションも必要ですし、その場での臨機応変な対応が求められます。
ロボット審判にこのような動きができるのかも含めて、今後どのように導入されていくかはとても気になる事案ですね。