昨年11月に著書「球速の正体(東洋館出版社)」を出版した、林卓史(たかふみ)・朝日大学教授のインタビュー後編。
慶応義塾大学の助監督だった2017年に「Rapsodo(ラプソード)」を日本で初めて導入して以降、データ計測の重要性を全国各地に足を運び発信し続けてきた。
本編では、中高生がラプソードをどう活用するとパフォーマンスアップにつながるか、そして今後どんな指導者が一流とされ得るかなど、林教授の考えを語っていただいた。
(取材協力:ラプソードジャパン、写真 / 文:白石怜平)
林教授が送るラプソード活用のアドバイス
ラプソードでは投手の場合、回転数や回転効率といった10種類のデータを計測できる。その項目は中学生や高校生にとっても理解が難しいものがほとんど。
より中高生の選手たちがラプソードを活用してパフォーマンスを上げるためには、どこに着目をすれば良いか。林教授がそのポイントを解説してくれた。
「回転効率(※)が大事になります。中学から高校の前半あたりですとまだ体の成長過程にあると思うので、”指にかかったボール”を投げられるのが望ましいです」
(※)ボールの回転数全体のうち、動きに影響を与える回転数である「有効回転数」が占める割合のこと
回転効率の高いボールを投げるというのはどういう状態を指しているのか。中高生にもより伝わりやすいよう、ボールを手に説明した。
「遠投で遠くに投げられるであったり、ワンバウンドするかなと思ったボールが相手に届くような球です。キャッチボールで下に沈まず相手の胸に行くことですね。真っ直ぐの場合、両方の指を同時に離すことができれば、回転効率が高い球を投げることができます」

ボールを使って”回転効率の高い球”を解説した
また、投げるボール以外にも計測の際に大事なことがもうひとつあった。林教授はこう付け加えた。
「特に高校生の子たちは、球速を上げるといった具体的な目標設定をして練習を続けると、必ず上達するんですよね。3km/h〜5km/hmほどは一冬越えると速くなると思いますが、それに伴って回転数も増える。記録を取っておくと『このくらい上がった!』という自信に繋がります。
あとは、”気づき”ですね。同じ130km/hでも投げた感覚と実際の球質が全く違うというように、自分のイメージと計測時のギャップを知ることも必要だと思います。
ただ、現時点でアドバンテージだったものがそうでなくなるといった残酷な部分も出てくるかもしれないですが、ここから工夫してレベルアップするためにも、本当の原因を突き詰めるプロセスとして大事なことだと考えています」
一流の指導者は「定量」と「定性」の両立
中高生に向けた活用法を語った林教授。では、指導者の方たちは計測を通じてどう指導に活かしていけばいいか。この点についても伺った。
まず、「数字が出てきて、”130km/h出た、次132km/h”などとフィードバックするだけでは意味はないです」と前提を置き、林教授にとっての”優れた指導者”をこう言語化した。
「計測した数字の部分と、数字以外の両方を見極めてアプローチできる人が優れた指導者なのではないでしょうか。
『データとイメージを比べてなぜ、この結果だったのか』・『であれば次に何をトライするか』といった、数字が量だとしたら質の部分=定性的な部分もとても大事です。
その両方を読み取ったりできる方が、今後さらに必要とされていくのだと思います」

定量だけでなく定性も必要と述べた
定量とは対称になる定性的な部分。この言葉をさらに嚙み砕いていくと林教授の考える”優秀な指導者像”がさらに見えてくる。
「図ってみて例えば球速145km/hの選手が今日は140km/hも出ない。それが彼女と喧嘩したのか、それとも首を寝違えてしまったのかなどと数字の背景まで考えられること。
それは、中高生を指導する際にも現状のポテンシャルからの伸びしろを見つけられることにもつながります。
『今は球速118キロだけど、すごくいい球質を持っているから、たくさん食べて早く寝て体をしっかりつくろう』といったアドバイスを送れる指導者が一流だと思います」
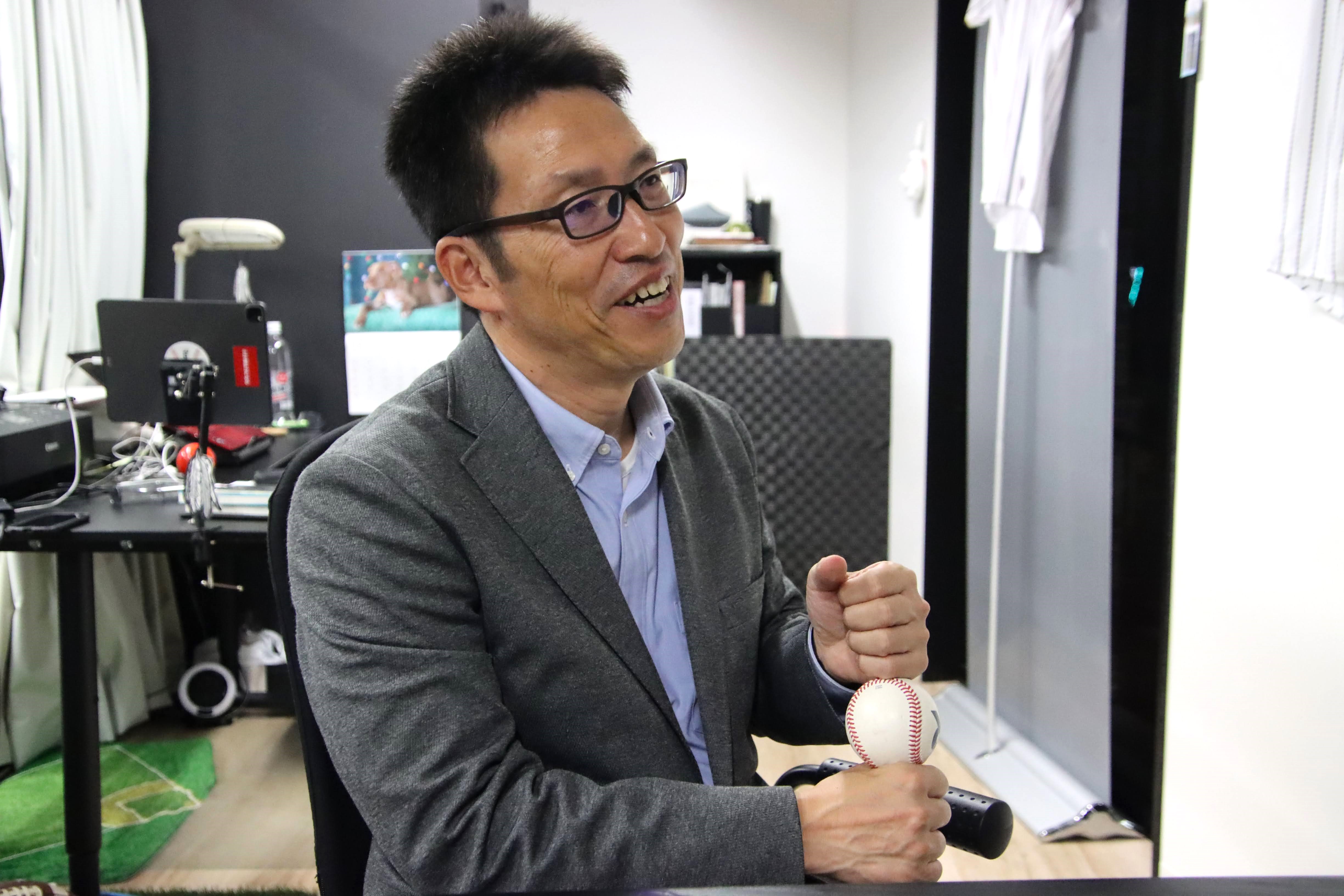
定量だけでなく定性も必要であると話した
林教授が”一流”と考える指導者は定量と定性を追い、両立させている。自身がユニフォームを着て共に過ごし、研究面でも取材を重ねてきたからこそ記せるものだった。
「本にも書かせてもらいましたが、慶応でもご一緒させてもらったENEOSの大久保(秀昭)監督が、計測データを活用して科学的に選手を伸ばす”Baseball”とゲームメイクをして試合に勝つ”野球”という表現を用いていました。
つまり、定量と定性の2つを追いかけて両立させているんです。愛工大名電の倉野(光生)監督も同様のことを仰っていましたね」
野球科学発展に向けた提言
前編で林教授が講演で訪問した際に『すでに機材がある学校が多い』と語ったように、ラプソードを始めとした計測は浸透しつつある。
まだまだ伸びしろがある一方で、これから野球科学のさらなる発展に向けての課題もある。インタビューの最後にこう提起した。
「今懸念しているのは情報の”二極化”です。東都大学や六大学リーグではトラックマンのデータが共有されています。今年はそのうちの2校(明大ー青学大)が全日本大学野球選手権の決勝で当たって、計6人がドラフトで指名されましたよね。
この結果を見てなるほどなと。データリテラシーを持っているのといないのでは、プロに入って以降も大きな違いになるのではないでしょうか」

データが分かることで目指す方向性が具体化されると語った
この情報格差をなくすことは、日本の野球がさらに向上することにつながると林教授は語る。
「例えば、高校生のトップレベルの選手がどんな球を投げているかが分かると、野球界のさらなるレベルアップにつながると思います。
『甲子園レベルに行くにはこの基準まで行かなければいけない』などと、指標が具体化されますので。
例えば、大阪桐蔭の前田悠伍投手(ソフトバンクD1位)がどんなチェンジアップを投げているか、また2020年の甲子園での計測会の時に、山下舜平大投手(現オリックス)の遠投にみんなが驚いた話もありました。
その真っ直ぐがどれぐらいの回転数があって、どう変化したか分かると練習方法も変わるので、選手たちのレベルはさらに上がっていくと思います」
林教授はインタビュー後、ラプソードジャパンの山同建・日本支社長とオンラインセミナーに登壇した。計測やデータの必要性について、全国を回りながら発信を続けている。
(終わり)







