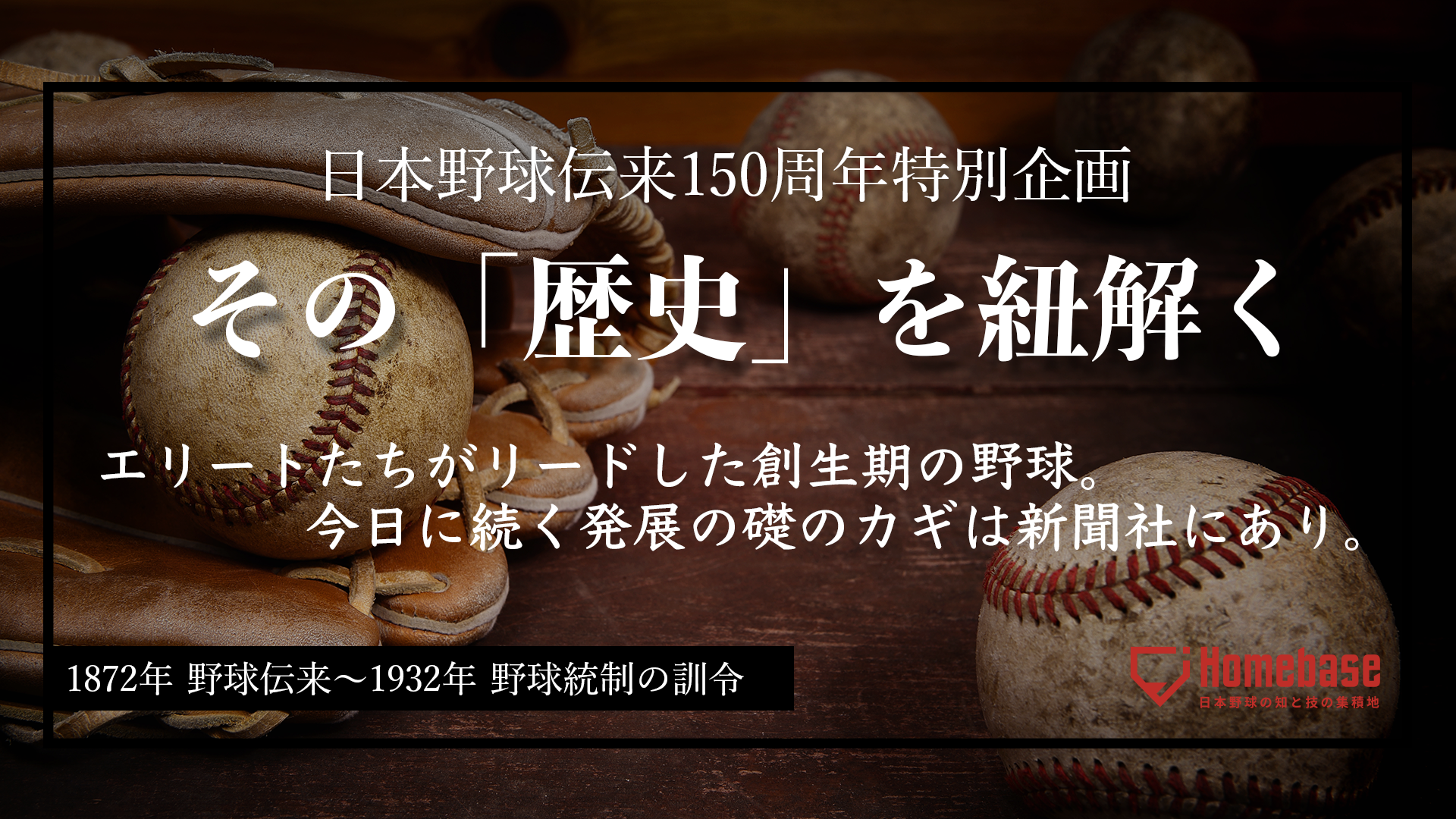アメリカで誕生したベースボールが日本へ伝来し、どのように各地に広がって日本を代表するスポーツへと発展していったのかを解説する連載企画。今回は、日本野球創生期の主な出来事を振り返っていきます。
お雇い外国人教師として来日したアメリカ人、ホーレス・ウイルソンが1872年(明治5年)に第一大学区第一番中学で生徒に野球を教え、翌年から開成学校(のちの東京大学)となった同校に、立派な運動場ができると攻守に分かれて試合ができるまでになりました。
これが「日本の野球の始まり」といわれています。ちょうど150年前の出来事です。
当時の高等教育を受ける若者の多くは、のちの日本をリードするエリートたち。彼らが主導するする形で日本全国に競技が広がったのが野球普及の特徴です。
1878年(明治11年)には、アメリカで鉄道技術を学び、帰国後、工部省鉄道局新橋工場に勤めていた平岡煕が、日本初の野球チーム「新橋アスレチック倶楽部」を結成しました。
平岡はアメリカで生活していた時期、野球チームに所属しピッチャーとして活躍していたといわれています。

平岡の新橋倶楽部は東京の学生たちを指導し、明治10年代の球界をリードしました。明治20年代には都内の学校に野球チームが増えてきて、対抗戦が行われるようになります。
その中で、第一高等中学校(1894年から第一高等学校)が全盛期を迎え、横浜在住の外国人を破ったことがきっかけとなり、日本中に野球ブームが巻き起こりました。
1903年(明治36年)には、初めての早慶戦が行われました。この頃から野球人気は高まりを見せ、1906年(明治39年)の早慶戦は、応援が過熱したことが原因で中止に。
そんな時代背景もあり1911年(明治45年)には東京朝日新聞(現・朝日新聞)が「野球と其害毒」という連載コラムを掲載し、新渡戸稲造、乃木希典ら大学のトップを務めた人物が野球を痛烈批判するという事態にまで発展しました。
それでも野球人気は衰えることなく、大正、昭和にかけて今日まで続く、全国大会が次々と創設されます。年表にあるように、夏の甲子園、春の選抜創設で高校野球の基盤がつくられました。
1927年(昭和2年)には都市対抗野球が創設されています。これらの大会に共通するのは、いずれも新聞社が事業として大会を創設している点です。
いわゆる競技団体が普及を推進する形ではなく、企業がビジネスとして野球大会を創設したことが、大会の発展を加速させたといえます。

また、子どもたちへの野球普及で忘れてはならないのが、1918年(大正7年)の軟式ボールの誕生です。
子どもたちにも安全に野球をプレーさせたいという思いから誕生した日本独自の軟式ボールは、日本の野球のすそ野を広げることに大きく貢献しています。
当初から普及をリードしてきた大学では1925年(大正14年)に東京六大学連盟が発足、早慶戦が復活し、1927年(昭和2年)からNHKがリーグ戦をラジオ中継するなど国民的な野球人気が沸騰しました。
この六大学をはじめとする学生野球の人気沸騰で応援も過熱、さまざまな問題が生じたことから、1932年(昭和7年)3月、文部省より、野球統制の訓令が発令されて、野球は国家権力による厳しい規制を受ける事態に陥ってしまいます。
野球伝来から、ちょうど60年目のことでした。
<日本野球創生期の主な出来事>
1872年(明治5年) アメリカ人教師ホーレス・ウイルソンが学生たちに野球を教え、翌年には試合が行われる
1878年(明治11年) 平岡煕が、日本初の野球チーム「新橋アスレチック倶楽部」を設立
1903年(明治36年) 早稲田大学と慶應義塾大学による初の“早慶戦”実施
1915年(大正4年) 第1回全国中等学校優勝野球大会(現・全国高等学校野球選手権大会=夏の甲子園)を開催
1918年(大正7年) 鈴鹿栄が軟式ボールを考案
1924年(大正13年) 第1回選抜中等学校野球大会(現・選抜高等学校野球大会=春の選抜)を開催
1925年(大正14年) 東京六大学野球連盟が発足
1927年(昭和2年) 第1回全日本都市対抗野球大会(現・都市対抗野球大会)を開催
1932年(昭和7年) 文部省が野球統制の訓令を発令