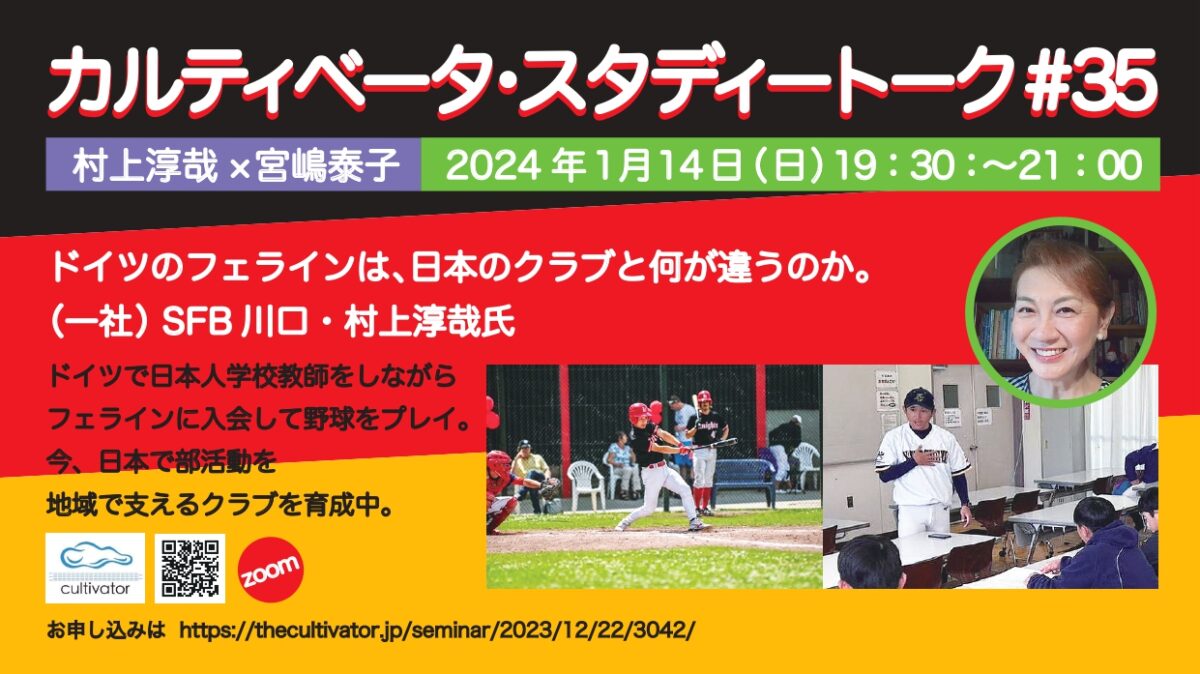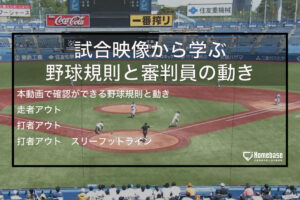明治時代に当時の大学で誕生し、日本でスポーツを普及する上で大きな役割を果たしてきた部活動が今、転換期にある。文部科学省やスポーツ庁が中心になり、「学校から地域」への移行が進められているのだ。
中学校や高校の部活動は、野球も含めて各競技の足元を支えてきた。一方で近年、少子化やニーズの多様化などにより、学校単位では活動を続けられなくなるケースも増えている。顧問を務める教員への過剰な負担も“ブラック部活”として問題となり、サステイナブルな形が模索されているのだ。
「私は横浜市や神奈川県、国の青少年スポーツのさまざまな委員会に出席し、15年前くらいから学校部活動の地域移行の必要性を話してきました」
そう語るのが、テレビ朝日でアナウンサーやスポーツコメンテーターを務めた後、現在はスポーツ文化ジャーナリストとして活動する宮嶋泰子さんだ。

「トップスポーツの取材をするなか、学校の先生も含めて指導者が選手に人前でビンタをする場面などを見て、ハラスメント行為をなくさないといけないと思ってきました。外国では青少年のスポーツをどのように行っているのだろうかと思い、フィンランドに取材に行って番組にしたこともあります。
同時に、日本スポーツ協会の地域クラブ育成委員を20年以上にわたり務め、部活動のあり方と照らし合わせながら見てきました。現在、部活動の地域移行が進められていますが、総合型クラブと中学校の部活動が関係性を持って一緒に活動しているところも15年前くらいからあったので、『部活動の地域移行を早くすればいいのに』という思いがずっとありました」
部活動と総合型地域スポーツクラブは“別物”
とりわけ中学校における部活動は現在、さまざまな課題を抱えている。少子化による部員数の減少、顧問を勤める教員の長時間労働、指導者によるハラスメント……などだ。これらは地域に移行することで解決されるのだろうか。
宮嶋さんに聞くと、視点の異なる答えが返ってきた。
「部活動と総合型地域スポーツクラブの活動を“同じもの”と考えてはいけないと思います。部活動は中学や高校の3学年で行われていますが、総合型地域スポーツクラブに行けば大人から小さい子どもまでいる。そう考えると、部活動とは“別物”として質が変化していかなければいけない。ここが一番重要な点だと考えています」
宮嶋さんによると、文科省が総合型地域スポーツクラブの取り組みを進める上でモデルとしたのがドイツの「フェライン」だ。ドイツ語で「共同体」を意味するこの取り組みこそ、「部活動の地域移行では“質”が変化する必要がある」という宮嶋さんの指摘に通じている。
フェラインを簡潔に言えば、スポーツを媒介とした地域コミュニティのことだ。ドイツには9万件以上あるとされ、日本の小学校、中学校、高校を合わせた数を上回っている(※村上淳哉「ドイツにおける地域に根付く スポーツフェライン(スポーツクラブ)文化」より)。
人生を豊かにする“生涯スポーツ”
2023年10月、宮嶋さんはドイツを訪れた際、フェラインの本質を理解する出来事があった。シニア世代を対象としたマスターズ体操のワールドカップを取材した翌日、マスターズ体操のドイツ大会がフェライン対抗戦として行われていたのだ。
同大会は年齢別に争われ、出場者のなかには70〜80歳の男女もいた。演技がうまくいけば「よし!」と喜び、思うようにできなければ「悔しい!」と感情を表して本気で競い合っている。高齢者と言われる年になってもスポーツに没頭している姿が、宮嶋さんには新鮮に映った。
「この盛り上がりは素敵だなと感じました。日本でも中学校の対抗戦のような大会はありますが、ドイツのように70歳や80歳のおばあちゃんたちが『悔しい!』と言いながら体操をしている光景はそうそうないですよね。そこまで人生を通じてスポーツができる環境があることに、とてもインスパイアされました」
宮嶋さんは現場で取材を40年以上続けるなか、「スポーツを文化へ」という思いを募らせてきた。「Culture(カルチャー)」の語源は「Cultivate(耕す)」から来ており、自身が立ち上げた一般社団法人「カルティベータ」にはそうした願いが込められている。
「カルチャーという言葉は、人生を豊かにするために耕していくという意味です。心身を耕し、友だちや周囲との関係をつくることで人生が豊かになっていく。そうした意味でも、スポーツは文化の大切な一つです」
“部活動文化”から“スポーツ文化”へ
日本人選手のマインドを表す表現の一つとして、「高校野球で燃え尽きてもいい」と口にする球児の存在がある。そうした発想になるのは、「競技スポーツ」として捉えているからだろう。
対して、ドイツの高齢者が80歳になっても本気で取り組むのは、「生涯スポーツ」として楽しみ続けているからだ。ある時期まで「競技スポーツ」として取り組み、年齢を重ねると「生涯スポーツ」に切り替える人もいるだろう。そうした転換が可能なのは、フェラインという環境が整っていることも大きく関係していると宮嶋さんは考えている。
「日本の中学校の場合、“スポーツ文化”ではなく“部活動文化”になっています。でも生涯スポーツで言えば、中学の部活は“入口”にすぎないですよね。今、部活の地域移行が進められていますが、学校から開放することでいろいろ化学変化が生まれるはずです。それをうまく行っていくためにも、海外の事例をたくさん知ることが大切だと考えています」
そうした目的を込めて宮嶋さんは1月14日(日)、前ハンブルク日本人学校の教諭として現地でフェラインに所属し、ブンデスリーガ2部の野球選手としても活躍した村上淳哉さんを招いてオンラインセミナーを開催する。「ドイツのフェラインは、日本のクラブと何が違うのか」がテーマだ。参加費や保護者の関わり方、指導者への報酬、スポーツを行う場所の確保など、日本のクラブで想定されるハードルをドイツのフェラインはどう乗り越えているのだろうか。
埼玉県川口市立青木中学校に勤める村上さんは現在、一般社団法人SFB川口の理事として部活動の地域クラブ移行を進めており、現場の興味深い話も聞けるはずだ。
▼セミナー「ドイツのフェラインは日本のクラブとどう違うのか?フェラインを知る教員が日本で部活の受け皿を作る。」の詳細はこちら