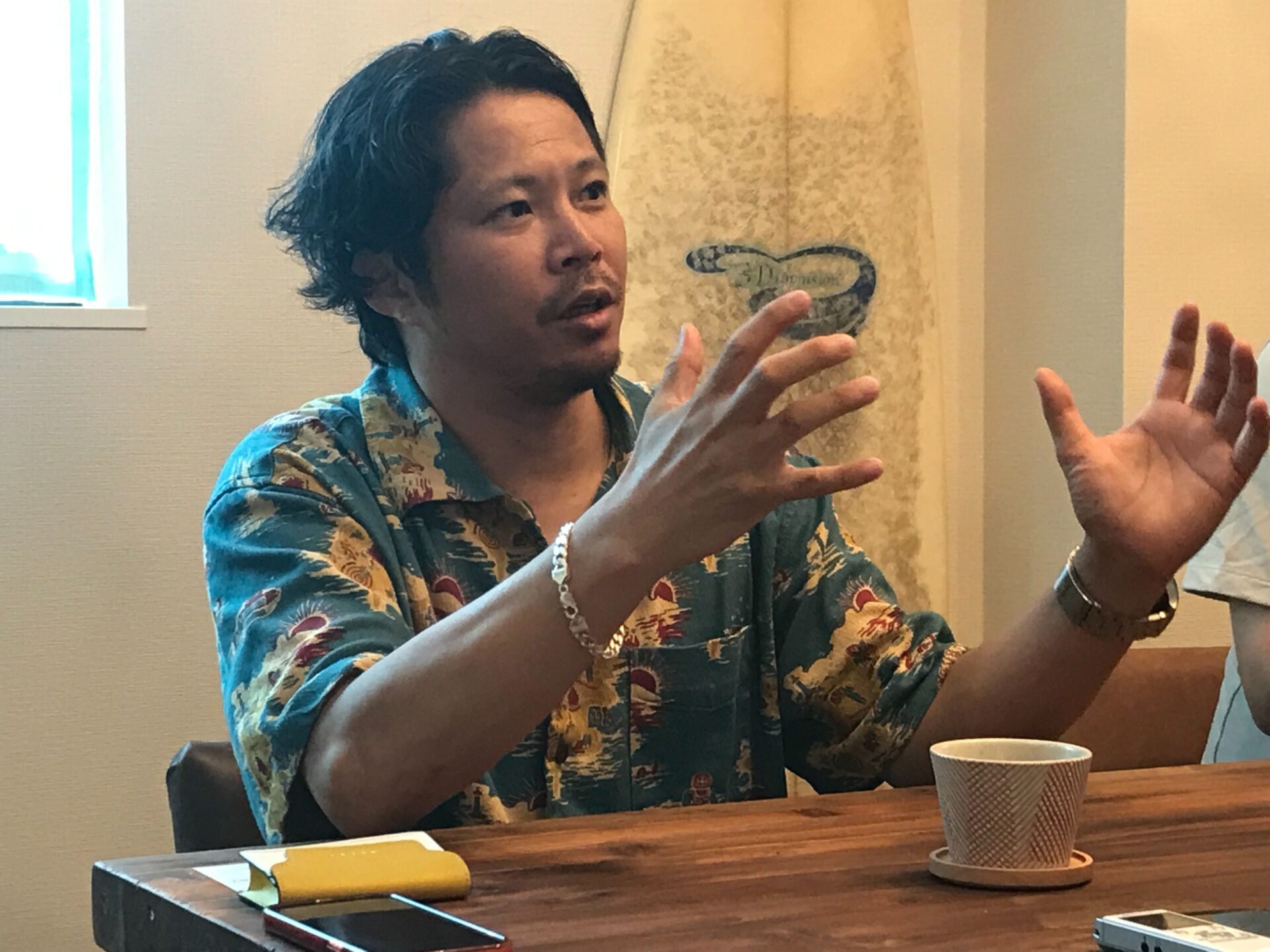野球界には、実際の野球現場とは別の場所から野球界に貢献する人々がいる。日本では、漫画文化が根付いているが、野球を題材にした漫画は多い。漫画を通して、「野球を知る。好きになる。」という普及に貢献している漫画家も多く存在する。人気漫画家クロマツテツロウさんもそのうちのひとりだ。
漫画「野球部に花束を」では高校時代の「野球部あるある」な日常を描いて共感を呼び、実写映画化もされた。「ドラフトキング」ではスカウトが主役という独特の視点からの野球を描いて注目され、実写ドラマが放送されたばかり。新たに連載中の漫画「ベー革」では、昭和のスポ根とは正反対の効率型現代野球を描く。どのように野球と関わりを持ち、どのような思いで野球を描いているのかをインタビューした。
第1回は、クロマツさんの野球歴と『野球部に花束を』に見られる野球観について聞いていく。『野球部に花束を』は、中学で野球をやっていた主人公が高校に進学し、理不尽な指導者や先輩からの圧力、謎の伝統などに四苦八苦しながらも、仲間とともに野球をしていく様子が綴られるコメディ漫画。スーパースターも天才もいない、強くない野球部の日常が共感を呼んだ。
ーークロマツさんは高校の野球部を引退した後美術部に入り、美大を経て漫画家になったという経歴。野球専門誌にご自分で売り込みをされ、菊地選手さんと「野球部あるある」を作ったことが「野球部に花束を」にも繋がりました
いや、なんかもう、暗黒とも言えるあの3年間をなんとかお金に変えてやろうと思っていました(笑) 本当に。野球部の当時の恩師の監督には、すごい怒られるかなと思ったら、結構喜んでました。
ーーご自身の野球のベースからお伺いします。野球とはどんな風に出会ったのでしょうか
僕は8個上の兄が野球をやっていて。ちっちゃい奈良の田舎なんですけど、 学校の通学路に、その少年野球チームの監督が住んでいたんです。
通るたびに「テツ!! 野球やるぞ!」みたいに窓から叫ばれる(笑)本当はサッカーやりたかったんですけど、もう野球やるしかなくなった感じですね。
ーー野球を見てはいたのでしょうか
父が阪神ファンだったので、自宅のテレビではプロ野球が結構流れていました。でも見ててもやっぱり子供には退屈でしょう。小学校3年までは野球部に入れられたくないっていう方が強かったんです。坊主にしなきゃいけなかったので。
ーーその後は結局、野球を始められたんですね。
そうですね。見学に行ったら、当時、少年野球って結構いい意味で適当だったので。その日は練習試合で登録してない選手を出したりしてくれて、僕、代打でいきなり打席に立たされたんです。その時に、6年生のピッチャーの投げた球がすごくて、空振り三振したんですけど、あ、これめっちゃ面白いかもしれんって思って、はじめたんです。
ーー当時の少年野球の指導は、のびのびとした指導だったんでしょうか
いや最初は優しかったんですけど、入ったらゴリゴリで恐ろしい集団でしたね(笑)まあ僕らの時には、結構普通にどつかれたりってあったんで、そういうことはありました。。
ーー中学で軟式の野球部に入られて、坊主にされたそうですね。中学校の野球部はどんな感じでしたか
小学校の野球は夏ぐらいで終わって、冬はサッカーやってたんですよ。中学に入った時に本当に迷いました。サッカーと野球で。でも、サッカーはすごく先生が怖かったんで、野球にしようと決めました(笑)チームはすごい弱かったですね。公立校だったので、毎年先生が転勤して、監督が変わるんですよ。指導者には本当に恵まれなくて、 野球をちゃんとやってきた人が全然いなかった。3年生の時に、野球部が強い中学校から顧問の先生が異動してきてくれて、そこで初めて、”野球”というものを少し教えてもらえたんです。
それがきっかけで高校でもやろうかなと思うようになりました。適当にやってたけど、 打てたりとか結果が出てた。ちょっといけるかもなと思って、「野球部に花束を」みたいな高校に入りました(笑)

『野球部に花束を』1巻表紙 ©︎クロマツテツロウ/集英社
ーー最初から野球部を希望して入られたんですか
漫画の通りですね。ちょっと迷いました。受験に失敗して、野球をやりたかった高校とは別の高校に入ったんです。あーどうしようかな、知ってる奴らいないし、みたいな感じでした。二次募集で入ったので、野球経験者はみんな声かけられてるのに、僕だけ名前呼ばれなかったんですよ。自分よりしょぼそうな生徒が勧誘されてんのに何で、みたいな感じでちょっと傷ついたりして。
それで、なんとなく練習見に行ったら、もう囲い込みがすごくて、逃げられず、そこからは『野球部に花束を』で描いた通りに強制的に入れられました。
ーーポジションは ショート?
ショートですね。僕は肩は自信あったんですが、送球が苦手で、セカンド志望だったんです。でもすぐに、ショートにコンバートされました。
セカンド用とショート用のグラブって、微妙に違うんですけど、セカンド用のグラブ買ってからすぐショートにされたんで、それを『野球部に花束を』でも描かせてもらいました。むちゃくちゃ大げさに描いてみたのが『野球部に花束を』ですね(笑)漫画では、キャッチャーへのコンバートも描かれていますが、実際には、ありませんでした。
多分、僕が描いてる作品の根底に、「指導者に恵まれなかった」っていう怨念みたいなのがあると思います。やっぱりちゃんと教えてほしかったというのは、すごくありますね。頭ごなしに色々やらされていたのとどれが正しい理論なのか。もう間違いだらけなんです。それを調べる方法もやっぱあんまりなかったので。それが一番しんどかったかもしれないですね。
高校の時にやっとちゃんとした指導者に巡り合えたんですけど、でもその人、バッティングしか教えてくれないんですよ。だからバッティングにはすごく興味を持って、本でプロ野球選手のコマ送りのやつとかを見ながら、理論をちょっと勉強したりとかして、それは楽しくなってきたんです。でも守備のことは全く教えてもらってなかったんで、 めっちゃ守備下手だったんですよね。
ーーでもノックだけはたくさん受ける
そうです。守備もさばき方やとり方って、状況次第でたくさんあるじゃないですか。
でも、ただノックを受けていてもあまり意味がないと思うんです。基本ができていないので、守備ができない。意図を理解して、繰り返し、繰り返しノックを受けてやっと上達すると思うので…。そんなチームだったので、毎年夏はタイムリーエラーで負けるっていう伝統の高校でした(笑)
ーー「野球部に花束を」は、そんな経験から描かれたんですね。
指導の仕方は当時からだいぶ変わってきてます。でも僕は、頭から押さえつけられた経験があるお陰で少しは真っ当な人間にして貰えたかなと思っています。絶対的な監督や先輩に押さえつけられながら、礼儀や人の道なんかを学んだのも事実なので…。その中で下々の一年生たちは結束を深めていく(笑)当時の同級生とは、やっぱり、今でも仲いいですし、野球の結果は出なかったですけど、そういう友達と出会えたっていうのは、大きいですね。
ーー濃密な青春という感じがしますね。指導者がいつも理不尽ばっかりかと思うと、たまにいいことを言ったり
普段、理不尽な分、急にいいこと言われた時のことは強烈に覚えてます。
ーー映画『野球部に花束を』の試写会で先輩とお会いになったとか。わざわざ見にきてくださったんですね。
そうなんです。いきなりトイレで声かけられて見たら奈良にいるはずの先輩がいたんです。びっくりしすぎて、死ぬかと思いました。漫画で出てくる高柳っていう先輩で「俺、あんなティー放るの下手ちゃうやろがい!」って言われて「はい!すいません!全部ウソです!」って返しました(笑)殺されるかと思いましたが、来てもらえて嬉しかったですね。
ーー実写化されるというのは、それだけリアリティがあるということですね
あの映画の飯塚健監督は、 よく現代にあの時代の高校野球の話を撮ろうと思ったっていうのが一番ですね。 飯塚監督に脚本も書いて頂いたんですけど、本当に原作の漫画を大事にしてくださって。感謝しかないです。
ーー連載当時、パワハラだとか暴力だとか言われたりはしませんでしたか
今だったらわからないですよね。もう10年くらい前なので、当時の読者の皆さんはコメディとして楽しんでくれたんだと思います。
ーー読者の方も、野球部でそんな体験をした方が多くいらっしゃったでしょうね
当時、野球漫画って、スーパースターが活躍したり、弱小チームに天才が現れてみたいな話が多かったんです。でも実際には、甲子園行けない選手の方が圧倒的に多いんです。それなら、そこフォーカスしようっていうのが発端だったんですね。「みんな、そろそろちょっと共感したいんじゃないの」みたいな感じでした。僕も若かったっていうのがあるんですけど、野球をしない野球漫画っていう、結果的に反骨精神丸出しのふざけた作品になっちゃいましたね(笑)
体育大会や文化祭だけの話とかありますからね(笑)
ーー野球やってた方は共感できることがたくさんあるわけですね
実際には、試合以外にも緊張するシーンっていうのが多々あるんです。練習試合の審判をやらなければならなくて、大会前なんかは一年生が先輩の運命を握ってしまっていたりするんです(笑)。もう絶対、牽制で刺されたらあかん場面で刺されてしまった先輩にアウトって言わなければいけない!とか(笑)
なんかそういう世界観のコメディが描きたかったんです。
ーー野球をやっていない人でも、見て面白いと思う分かりやすさがありますね。
そうですね。昔の野球部って、なんかちょっと会社の縮図みたいなのがあるのかなっていうのは、勝手に想像していました。社会人になった時「2回目」みたいに感じるっていうか。既に1回、野球部で多少の理不尽や上下関係の厳しさみたいなものは経験できている。
それが読者の方の共感に繋がっているのかなって感じています。
「暗黒」の高校野球時代だったが、今クロマツさんの野球マンガがあるのは、その時代のおかげなのだ。昭和の根性野球の中でも、それを笑いに変えてしまえるたくましさがあるから、人間ドラマとして読者を惹きつける。