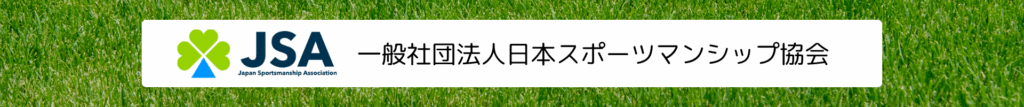
テニスのセルフジャッジに悩む高校生
3月。春のセンバツ高校野球が開催され、日本でMLB開幕戦が開催され、NPBもいよいよ開幕を迎えた。2025年、球春到来である。
私たち大学教員にとっても、春は、卒業生を送り出し、新たな入学生を迎えようとしている、そんな季節である。
そのようななかで、この春、ある高校2年生から日本スポーツマンシップ協会ならびに立教大学スポーツウエルネス学部宛に問い合わせをいただいた。
初めまして。
私は9年間、硬式テニスの選手として活動しております。突然のご連絡で恐縮ですが、テニスの試合における「セルフジャッジ」というルールに対して、不満と疑問を抱いております。
セルフジャッジとは、審判が存在せず、プレーヤー同士で判定を行うルールのことです。このルールはテニスだけでなく、カーリングやアルティメットなどでも採用されていますが、これらの多くはチームスポーツであり、個人スポーツでセルフジャッジを採用しているのはテニスだけかと思います。実際、テニスの試合の現状は、セルフジャッジは適切に行われていません。
私がこのルールに疑問と不満を持つ理由は、ズルが発覚しにくく、自分自身に嘘をつきやすい状況を生み出すからです。教育上、自分自身に嘘をつくことは非常に悪影響だと考えます。
一応「セルフジャッジの5原則」といったものを日本テニス協会が出しているのですが、どうしても本質的な効果がなく、それを詳しく理解し、順守しているプレイヤーはごく一部だと思います。
試合に出始めて6年目となりますが、当初はセルフジャッジに疑問を持たず、純粋にテニスを楽しんでいました。しかし、勝利に執着するようになると、セルフジャッジを正当に行うことが難しくなり、試合中の重要なポイントでズルをしてしまうことがありました。それが癖となり、テニスを純粋かつ正当に楽しむことができなくなりました。
その結果、自己嫌悪からテニスをすることが嫌になり、非常に辛い思いをしました。
また、自分はクリーンなジャッジを行い、正々堂々と戦っているのに、重要なポイントで相手にズルをされて負けたことが何度もあります。その度に、自分の努力を軽んじられたように感じ、悔しい思いをしました。
そこで、「私のような辛い思いをする人を減らしたい」、「スポーツマンシップの大切さを理解し、テニスをする人々に広めていきたい」という目標を掲げて活動しております。
『スポーツマンシップバイブル』を読み、スポーツの本質、社会においてのスポーツマンシップの必要性、スポーツの向き合い方、スポーツマンとしての試合への考え方を学びました。
ぜひ、中村様のテニスにおける「セルフジャッジ」についてのお考えや、スポーツマンシップを浸透させるための方法についてお伺いしたく存じます。さらに、「スポーツマンシップの本質」への理解を深めたいと考えております。
このような問い合わせに対して、キャンパスまで足を運んでいただく形で、彼との対面が実現した。あらためて、プレーヤー自身が審判の役割を担う「セルフジャッジ」を通して彼が直面した苦悩などを伺いながら、ディスカッションがスタートしたのである。
アンパイア、レフェリー、ジャッジ
野球というスポーツにおいては、ゲームを進行するにあたり、各プレーについてジャッジする「審判」が存在するのが原則である。
野球の審判は「umpire(アンパイア)」と呼ばれ、球審・塁審・線審などが存在する。試合の進行と判定を行い、投球に関する「ストライクorボール」、塁上でのプレーに関する「アウトorセーフ」、打球に関する「フェアorファウル」などについて判定する役割を担う。
アンパイアの語源は、フランス語で「一人の父」を意味する「un pér(アンペール)」であるという説が有力である。スポーツが発展する過程で、公平に試合の裁定や仲裁を行う人が必要となり、試合の判定を行う唯一の権威者、対等ではない第三者といった意味を有する「アンパイア」が、ゲームを行う双方の仲裁者としてその役割を託されるようになったといわれている。
一方、サッカー、ラグビー、バスケットボールなどの審判は、「レフェリー(referee)」と呼ばれる。
この「refer」には、「委ねる」、「任せる」という意味がある。
インタビュー(interview)をする人のことを「インタビュアー(interviewer)」、インタビューされる側を「インタビューイー(interviewee)」と呼ぶように、レフェリー(referee)には、「referされた人」、すなわちプレーにおける問題解決を委ねられた人という意味合いを含む。
アンパイアとレフェリー以外に、「ジャッジ(judge)」と呼ばれる審判員もいる。
ジャッジは、ラテン語で「判決を下す」「裁く」「判断する」といった意味をもつ「L. judicare」が語源であり、これは、「法・正義」を意味する「jus」と、「示す・言う」を意味する「dicare」とに分解される。
フィギュアスケートにおける採点者なども一般的にこのジャッジという呼称が使われる。ボクシングやレスリングなどでレフェリーに次ぎ採点・判定を行う副審もジャッジであり、また、ラグビーなどにおける線審も「タッチジャッジ」と呼ばれる。
ちなみに、冒頭の相談にもあったように、育成年代におけるテニスのゲームはセルフジャッジで行われるが、一般的にはテニスでもご承知のように審判が存在する。
トーナメント要項作成への参画をはじめ、トーナメント会場におけるコート設営がテニス規則に即したもののであるかを確認したり、チーフアンパイアやチェアアンパイアを任命・指導したりする「レフェリー」。
トーナメントに必要なコートオフィシャルを招集し必要に応じて教育したり、トーナメント各日のコートオフィシャルの勤務割当表を作成し勤務評価を行ったりする「チーフアンパイア」。
「インorアウト」などの判定やプレーの進行を担うなど、チェアアンパイア、ラインアンパイア、ロービングアンパイアなどといった審判を担当する「アンパイア」。このように、テニスの審判には「レフェリー」と「アンパイア」が混在するというのも特徴的である。
審判という存在に対する尊重
審判は、両チームから文句を言われることの多い、ある意味理不尽なポジションでもある。しかしながら、審判は、グラウンドのなかでプレーを愉しむプレーヤーたちを支え、そのために秩序を保つ役割を担う。
心から野球を愛しているからこそ審判をしようと決意し、プレーヤーたちがプレーを愉しめるように努力をしている方も多い。審判は、プレーヤーたちのなかに違反者がいないかとアラ探しをしている疑り深い人たちではない。優れた審判は、優れたプレーヤーたちにプレーを愉しんでもらえるように自らの役割を果たそうと努め、円滑にゲームを進行するコンダクター(指揮者)のような存在なのである。
全日本野球協会(BFJ)の国際事業委員会副委員長で、全日本大学野球連盟審判部長を務める小山克仁氏は、日本スポーツマンシップ協会のスポーツマンシップコーチの資格も取得してくれている同志でもある。
その小山氏は、国際大会における「アンリトンルール」の大切さを説く。審判は、単にルールを司るだけでなく、競技の伝統や慣習などといった「ルールブックには明記されていない約束事」をも意識しながらプレーヤーとゲームを制御しようするという。だからこそ、プレーヤーもそうしたアンリトンルールをしっかり理解する必要があるというわけである。
現代のスポーツにおいては、リクエスト、VAR、TMOなどといったビデオ再生によるリプレー検証が採用され、誤審が明らかになるケースも増えてきている。審判も、私たちと同様に完璧な人間というわけではない。
しかし、それでもやはり、審判は公平に正しい判定をしようと努めてくれている存在であることを忘れてはならない。
審判がどちらか一方に偏って判定する可能性よりも、コーチ、プレーヤー、応援する関係者たちが自分たちの望む結果を得ようとしてひいき目にプレーを見ていることの方が実際には多いはずだ。そして、審判を尊重し、肯定的な態度でゲームに臨むことは、勝利に向けて戦う上でも有効に働くことは少なくないはずである。
2019年に日本で開催されたラグビーワールドカップの決勝戦でレフェリー(主審)を務めたジェローム・ガルセス氏は「審判は選手と良い関係を築くこと、ゲームを持続させていくことが大事」と話し、アシスタントレフェリー(副審)として大会に参加したカール・ディクソン氏も「審判にとって重要なことは相手とコミュニケーションをとること、そして、相手の立場に立って、相手を尊重すること、もちろん自分自身も試合を愉しむことだ」と述べている。
日本トップリーグ連携機構の代表理事会長で、Jリーグ・Bリーグを設立したスポーツビジネス界のレジェンドである川淵三郎氏も、「私も審判の判定が常に正しいとは思っていません。人間ですから、間違った判断を下してしまうこともある。選手も同様で、人間がするスポーツである以上、当然ですよね。だから、面白いと思うんです」と述べている。
ちなみに、審判への尊重というと絶対服従のように感じるかもしれないが、抗議してはいけないということでは決してない。必要に応じて、判定に対して疑問を呈したり抗議したりすることが認められていることも多い。ただしその際にも、感情的に口汚くののしったりするのではなく、審判を尊重して丁寧な姿勢に抗議することが必要だといえよう。
「自分がされたくないと思うようなことを、他人に対してしてはいけない。」
こうした原則は、審判に対しても例外ではない。自分が審判だとしたらどうかと考えることも重要だ。これは審判との関係性に限ったことではなく、自らと対立する意見に向き合うときこそ、相手の立場を理解しようと努めることが大切である。
審判もゲームの一部である。審判はプレーヤーを尊重し、ゲームをコントロールしようと努力する存在で、ゲームの愉しさを守る後見人のようなものであり、信頼すべき仲間である。私たちも、そうした審判という存在を慮り、その立場について想像力を働かせ、尊重すべきである。
審判を尊重することは、ゲームそのものを尊重することにもつながる。プレーヤーやコーチにとっても、審判を尊重するスポーツマンであることが求められている。
ジャッジとの向き合い方を考えよう
本稿冒頭でご紹介したある高校生は、セルフジャッジで自らに有利な判定を下してしまうクリーンではない相手に苛立ちを感じていたこともあれば、自ら有利な判定を下してしまい、それがクセになってしまった時期もあった。その結果、自己嫌悪に陥り、テニスを嫌いになりかけてしまった経験があるという。
そんなときに彼は、『スポーツマンシップバイブル』と出逢い、スポーツマンシップの概念を理解することで、自分自身がコントロールできるところに集中するという考えに至るようになったと明かしてくれたのである。
セルフジャッジのあり方。
審判との向き合い方。
愛しているスポーツを嫌いになりかけてしまったという経験をもつ高校生の言葉は重い。
彼が語る「セルフジャッジの課題を乗り越えてよきテニス界をつくっていきたい」という想いは、セルフジャッジの問題に限らず、そして、テニスや野球に限らず、すべてのスポーツにも通じるといえよう。私たちも視野を広げて、野球以外の競技から学ぶべきこと、スポーツの世界以外からも気づけることを増やしていきたいものである。
私たちも今後、日本スポーツマンシップ協会で資格をとってくれたスポーツマンシップコーチのみなさんや、協会でインターンシップをしてくれている大学生たちの力も借りながら、高校生の彼とともにこうした問題に向き合い、議論し、どんなアクションができるかを考えていきたいと考えているところである。
あらためて、今後の展開について愉しみにしたい。そして、こうした出逢いの機会をいただけたことに感謝したい。

中村聡宏(なかむら・あきひろ)
一般社団法人日本スポーツマンシップ協会 代表理事 会長
立教大学スポーツウエルネス学部 准教授
1973年東京都生まれ。慶應義塾大学法学部卒。広告、出版、印刷、WEB、イベントなどを通してスポーツを中心に多分野の企画・制作・編集・運営に当たる。スポーツビジネス界の人材開発育成を目的とした「スポーツマネジメントスクール(SMS)」を企画・運営を担当、東京大学を皮切りに全国展開。2015年より千葉商科大学サービス創造学部に着任。2018年一般社団法人日本スポーツマンシップ協会を設立、代表理事・会長としてスポーツマンシップの普及・推進を行う。2023年より立教大学に新設されたスポーツウエルネス学部に着任。2024年桐生市スポーツマンシップ大使に就任。







