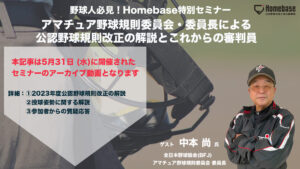心技体と表現されるように、技術の向上、身体の鍛錬と同様に、心すなわちメンタルを充実させることも、競技力の向上には必須の要素である。近年では、野球に限らず、あらゆるスポーツのトッププロが個人のメンタルトレーナーを雇う事例も多く耳にする様になった。とはいえ、時間の限られているアマチュアの指導現場においては、まだまだメンタルの部分への指導は“後回し”なのが現状だろう。しかも、総じてより効率的に“進化”していく筋力トレーニングや技術論に比べ、メンタルにおいては時事性や、個々の素養によって、求められる方向性も変わってくる。しょうがない、という言葉で過ごせるものではないが、頭を悩ませている指導者の方も多いことだろう。
「どうしても、指導の順番が後になってしまうものだというのは私自身も思います。ただ、メンタルは選手たちのベースになるものでもあるので、指導者の方たちにはぜひ学んでほしいものではありますね」
そう語るのは、多くのトップ選手たちの指導経験を持ち、メンタルトレーニングの最前線で活動を続けている、トレーナーの高畑好秀氏だ。メンタルは、選手たちの“ベース”。だからこそ、指導者にも知見も深めてほしいものだという。
「どこに重きを置くか、ということも重要ですが、どうしてもアマチュア野球の現場においての指導については“結果重視”になりがちです。高校野球は特に、甲子園という明確な目標があるがために、勝つための指導をしがちだと思います。本質は決して間違っていません。ただし、バランスは必要ですね」
選手のパフォーマンスを引き出すのは“楽しむ”力
メンタルの指導におけるバランスとはーー
勝利主義の側面も残しつつ、よりスポーツの“本質”と向き合わせることだ。
「どのようなときに高いパフォーマンスが発揮できるかというと、一番はのびのびとプレーできることが一番なんです。トップ選手でも、よりよい結果を追い求めるあまり、また自分が不調に陥ったりというときに、この本質から頭が離れてしまいます。そういったときに『そのような取り組みをして、楽しくプレーできているか?』『なんのために、そうありたいのか』のように、整理をさせることがひとつポイントだと思っています」

(提供:本人 指導者や保護者の方に対しての座学の様子)
不思議なもので、結果を出せることに楽しさを見出していたはずの“本質”が、時間と経験を重ねるごとに、どこか“義務化”した考え方へと変換されてしまう。それは、時間とともに、自分の置かれる立場が変わったり、負けられない試合を迎えたりといった要素が重なるからだ。ただ、本質を失った中でのプレーは、“スポーツ”ではない。
「勝って結果を得ることと、楽しめるという本質のバランスをとってあげることが指導者の役割だと思います。高校野球における甲子園のように、勝利をかけた試合から生まれるドラマが多くの感動を呼んでいるのも事実です。悔しくて涙を流す光景がひとつの風物詩になっていますよね。これ自体は悪いものでは決してないのですが、試合が終わって、笑顔で終わるようなシーンがあっても、いいと思うのです」
比較するわけではないが、この春に日本代表・侍ジャパンが世界一へと輝いた、WBCはその最たる例だったかもしれない。結果が出ずに苦しんでいた選手はいたものの、ベンチでは前向きで、野球そのものの競技を全身で楽しむ様子が多くの注目を浴びた。結果もついてきたが、おそらく、今年あの姿を見せた侍ジャパンのメンバーであれば、仮に負けてしまったとしても、次につながるなにかを見せてくれていたはずだ。
効率化が求められる現代と向き合いながら
冒頭にも記載したとおり、時代的な難しさもある。トレーニングの現場や技術論もそうだが、最新鋭の技術等は総じて“効率的”であり、“最短距離”を走るものだ。それが故に、遠回りをすることを拒む若者も多く、また、自身の選択が求められる場面で、効率化を理由にして楽な方へと逃げてしまいがちだ。
「メンタルを“理由”に逃げる選手たちも少なくありません。のびのびやらせよう、と自主性を重んじた結果、人間は弱いですから、楽な方に行ってしまうんですね。明確な目標は持たせつつ、楽しませながら、足りないものはなんなのかを見極めて伝えてあげる。それがいまの時代に必要なことかもしれないですね」
(続く)