ラプソードを使った計測と動作解析で野球指導を行うコシコン西山陽一郎さん。映像とデータを駆使する西山さんへのインタビュー第2回は、ラプソードで一番重要なことや、普段使っている野球の概念がデータにどう現れるのかなどを教えてもらった。
ー実際にラプソードを使いこなせてない例をご覧になったことはありますか
測って終わりのところは多いです。そういうところの選手は、ほとんど球速しか見ていないことが多いですね。
ラプソードで重要なのは「自分との比較」。最初に測った時と比べて、もう一回測って、 その変化を見るのが一番重要になってくるんですね。例えば変化球でこういう取り組みをして、どう変わったかを見る。他との比較じゃなくて、自分と比較するというのが、ラプソードを使う一番重要なポイントになるんです。それをしないで、1回測って回転数が何回転でスピードがどれぐらいで、というのを見るだけなら、安いスピードガンで事足りる。ラプソードを使いきれていないと感じます。
ーラプソードとトレーニングの組み合わせでは、どんなやり方を指導していますか
ラプソードは色々トレーニングをした効果測定というイメージです。あとは、やはり選手に映像を見せて、理解してもらうと一番効果的だと思っています。体の使い方とか色々知識がある僕らは、こうした方がいい、した方が絶対うまくなるというのはわかるんですが、選手自身がなかなか理解しきれない。ですので、映像を使って比較して「ここをこうしないといけない」というのを、選手に認識させた上で、 「そのためにはこういうトレーニングが必要」とか、「ここをこういう風に動かす意識を持ってトレーニングをする」と進めていくのが重要かなと思っています。
ー第1回でバックスピンがかかった球は伸びがあるという話がありましたが、重い球や軽い球といった従来ある野球用語で、データで見られたり言語化できるようになった例はありますか。
例えばラプソードで、どれだけ球がホップしているかというのは、ある程度測定できます。球に伸びがあるとやはり回転数は高いし、綺麗なバックスピンをしている。それから千賀選手など強力なフォークの選手は、フォークだけれどもジャイロ回転して落としているとか。そういうのはわかってるんです。でも重い球とか軽い球とかというのは、今一つ実証されていない感があります。
あとプロの球団に入ってデータ分析を専門にしている人に聞くと、 プロ野球選手はラプソードのデータが異常値の人の方が活躍すると言います。例えばジュニアの層だったら、回転数が多い方が打ち取る確率は高いんですが、プロでは当てはまらない。本当は150キロだったら2300~2400回転してる人が多いのに、1900回転の人もいたりして難しいんです。
高校生で甲子園に行くとか、大学野球である程度活躍するというのは、多分データの数値自体を上げていけば、それなりにできると思いますが、その先はラプソード云々じゃなくなるようなところがある。 プロの人と話しても、データがいいのか悪いのかが結局わからない、という選手がすごく多い。だからデータもなかなかプロ野球選手になると難しい、というのが実感としてありますね。

ープロの場合は、トラックマンを使用してデータを共有している球団も多いですね
ベイスターズに行かれた小杉陽太さんは、プロ野球では、トラックマンのデータは出るんですが、それを解釈して選手に伝える人がいないとおっしゃってました。今小杉さんは何とかして、データと選手の間に入ろうとしていますので、ゆくゆくはもっと選手も活用できるようになってくるとは思っています。
プロでは、本当に高校生以下の数値の人もいるんです。でも、肉眼ではすごく速いんですよ。あとは、軌道がストレートととても似ていたりする。でも、その軌道がストレートと似てるかどうかは、やはりデータだけではなかなかわからないですね。いい方法があればとは思ってるんですが。大学生ぐらいまでであれば、 今のデータのシステムとか、色々なトレーニングが有効に活用できるという感じです。
ー例えば、「球威を増したい」という時には、どうされるんですか。
僕の場合は、普通のオーソドックスなウエイトトレーニングとかはもちろんやるんですけど、今よくやってるのは、プライオボールという少し重いボールを使って、胸郭の動きを出していくと、結構球威自体は上がっていく傾向があると思います。
ーその球威というのは、数字に現れるんですか
球威というよりは球速になりますね。
ー球速が上がると球威も上がるということでしょうか
そうですね、ウエイトオンリーでも球速自体は速くなるんですが、色々データを取っていくと、 簡単に言えばしなるような動きで投げた方が、バッターから見ると結構いきなりボールが出てくるように見えるんですね。で、しなるようにするには、どうしても胸郭のところの動きが必要になってくるんで、そこをトレーニングすると、 やっぱり同じ球速でも球が伸びて見えるという形になってきます。
ー力を上手く乗せられている球は球威があるのかなと思うのですが、それは数字に表れるというよりは、実際に打席で感じるようなものなのでしょうか
そうですね、なかなか実際の測定の数字には表れづらいかなという感じがありますね。
ーでも、それは指導して上げていける部分ではある
はい。だから選手に「こういうフォームはどうか」と色々試してもらう。打席に立ってもらって、実際にどう見えるかを検証する。バッターやキャッチャーから見て「伸びが少ない」となったら、少しずつ色々な要素を組み替えていきます。球を速くするだけであれば、 ある程度一発でこういう方法がいいっていう形でうまくいくんですが、「見え方」を変えるには、結構色々試して、いい落としどころでフォームを固めていくというやり方になりますね。
ー西山さんが、球の質がいいと思うのは、どういう球ですか
まず回転数がものすごく高いとやはり伸びてきます。あとは、ストレートと変化球で、残像を残す組み合わせだと、 ストレートがより速く見える。例えば遅いカーブを投げた後に、ストレートを投げると速く見えるので、ストレート自体の回転数がいいか、もしくは色々な変化球を混ぜてバッターに錯覚を起こさせて、ストレートを速く見せたりする、そういうのがバッターから見ると球の質がいいかなと。
それから、例えば130キロだと、普通であれば大体2000から2100回転ぐらいが通常なんですが、130キロだけど2400回転ぐらいしてると、 違和感に感じるので打ちづらい。そういう球は、やはり球の質がいいと表現するのかなと思います。
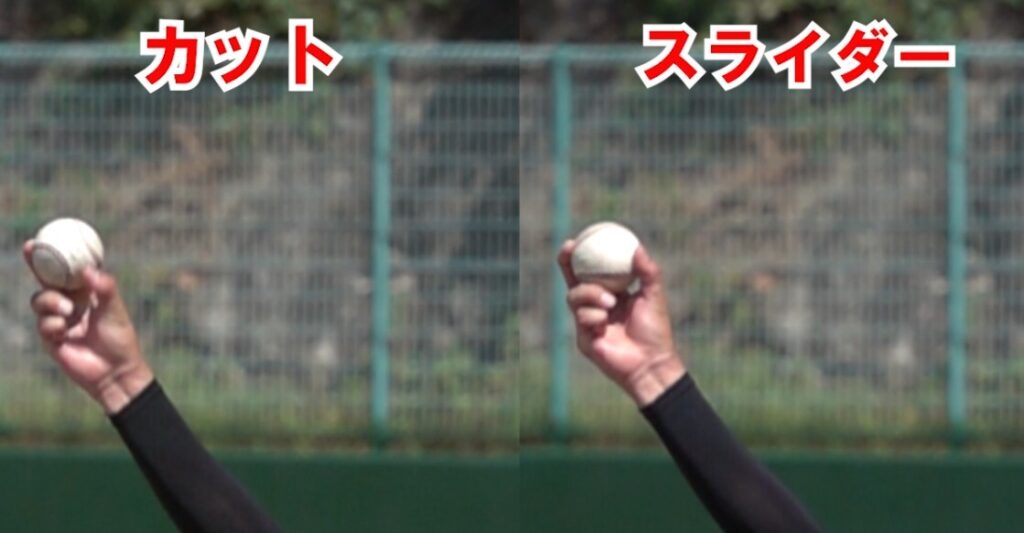
ー指導の上で気をつけていること、大事にしていることはありますか
基本的には選手が自分で「改善したい」とか、「どこか変えなきゃいけない」という状態になるまで待ちます。やはり選手が問題意識を持たないと、基本的にはアドバイスしてもほとんど変わらない。選手から僕がやってることを求めてきて初めて成立するので、特に高校生とかは無理に変えようとはせず、相手が「変えたい」となった時にアドバイスするのを心がけています。
ー自分で問題意識を持つ、考えるというのは大事な部分ですね
大学生とかプロになってくると、自分から問題意識を持ってる人が多い。話を聞きに来る時点で既に問題意識があるので、そのままこっちの考えを言うんですが、 やっぱり中学生、高校生とかは無理にやらないことが重要かと思います。
ー西山さんはMetaGateという活動にも参加されていますね。そちらはどういう思いで始められたのでしょうか
MetaGateの方は、先ほど名前を出した、DeNA二軍の投手コーチの小杉陽太さんと一緒にやっています。基本的に引退された直後で体がまだ動ける方に依頼して、色々な角度からデータを取ったり映像を撮影させてもらったりしています。実際目で見える動きとその人がイメージしている感覚的な動きに、ギャップがどれくらいあるか。映像で見た腕の振りと、本人の腕の振りのイメージのすり合わせというように検証して、一般の方に、これぐらいギャップがありますというのをお伝えするような活動が主ですね。
ー色々な方にそれをやってもらって、動画のデータベースのような形で提供している
そうです。
ーオンラインサロンもあるんですね
オンラインサロンに入っているのはほとんど指導者の方です。
ー野球指導について、この先こういうふうにしていきたいとか、こうなりたいというようなご希望はありますか
僕自身の仕事は、結構色んなところに行ってしまったので、今は学校を絞って、そこの生徒と共有する時間を長くして、その選手たちと一緒に甲子園に行けたらいいなと思います。
ーありがとうございました







