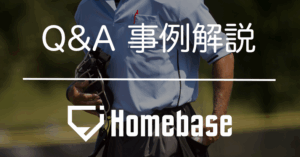2021年7月、全国高校野球選手権神奈川大会4回戦で、強豪校・東海大相模高校を相手に、終盤まで互角に渡り合い旋風を巻き起こした公立の進学校・川和高校野球部。率いたのは一般企業から高校野球の指導者へと転身した伊豆原真人さんだった。練習時間も限られる公立の進学校でどのようにして、生徒たちを導いて行ったのか。後編の今回、目標として掲げた「甲子園」を目指す中で感じたことを中心に語っていただいた。
「甲子園を目指す」。そう公言して指導にあたってきたという伊豆原さん。強豪校ひしめく神奈川県下で、野球エリートの集まりではなく練習時間も限られる公立の進学校が目指した「甲子園」とは、どんなものだったのか。
「もちろん、本当に全国大会である甲子園を目指すという意味もありますが、それだけではないと僕は考えています。どちらかというと、甲子園へ行くと目標を定めたことで、そのために何をしなくてはいけないのかを考えて、行動に移すことに意味があると思っています。自分自身を律して、何かひとつ今の自分を超えていく。その積み重ねみたいなものが「甲子園を目指す」という言葉には含まれていると思っています」
甲子園という大きな目標に向かって、己と向き合い、試行錯誤しながら自己を律して鍛錬していく。そのことが甲子園への道を作り、実際の甲子園には届かなくとも、その過程もまた甲子園であると伊豆原さんは考えているのだ。
「全国大会には届かなかったかもしれないけれども、自分たちの甲子園には手が届いたんじゃないかって話を生徒たちにはしています。言葉のやりとりみたいなところもあるので、良いか悪いかはわかりませんが、僕はそういうことがすごく大事だと思っているので、そこを目指していこうと。生徒たちには『勝ち負けだけじゃないんじゃないか』という話しをしてきました。いろんな学校がありますが、それぞれの甲子園があっていいんじゃないかなと思います」。
高い目標に向かって共に考え、共に進む。しかし、ただ目指すというだけでは、誰もついてこない。指導者生活をスタートした早い段階でプレーヤーとしての自らの経験則が役に立たないことを認識した伊豆原さんは、自らの中にない生徒たちを成長させる知見を外部に求めた。広くアンテナを張り巡らせて、生徒たちの野球能力向上に役立つと判断したものは貪欲に取り込み、生徒たちの指導に還元して行った。
具体例として、投球や打撃でボールがどのような動きをしているかを測定し、数値化する機器「ラプソード」を導入した際の話をしてくれた。
「子どもたちには『ホームランって、どういう打球になっている?100メートル先にボールを飛ばすためにはどうしたらいい?』って聞くと、みんな体の使い方のことばかり答えるんです。でも、実際に仕事をするのはバットなので、『バットがどういう仕事をするかを考えないとボールは飛ばないよ』という話します。『ボールに対してどういう角度で、どれくらいの初速で打ち返すことが必要なの?理想の数値はいくつになる?』と続けていくと、その初速を生み出すためにはどういうスイングが必要で、どういう筋力が必要なのかという話になってくる。結果から逆算していくと、自分の目標とするべき数値がわかっていくんです」。

話を聞いていて、授業を受けている気分になったが、中学時代に教わった連立方程式を思い出した。打撃向上という方程式の答えを導き出すために、生徒と対話しながら、X、Y、Zの中身を生徒自身が埋めていくことで、実際にどういうトレーニングをしていけばいいのかという、具体的な取り組みの話しへと進んでいく。ラプソードで測定された現時点での自身の数値を認識し、理想とする数値へ近づけるための練習を提示することで、選手たちは練習の意図を理解し、納得した上で自らの能力向上に力を注いでいく。やらされる練習ではなく、目標の数値を目指して、自らで行う効率的な練習。その積み重ねが、公立の進学校を県大会で旋風を起こすチームにまで、成長させて行ったのだろう。
「全部を知る必要はないと思いますが、やはり知識と考え方、『こういうものがあるんだな』と理解するところが大事だと思います。野球部員でいられる時間は実質2年半しかないので、求める答えに対して逆算で積み重ねていかなければいけない。生徒それぞれもゴールはどこまでなのかっていうことも考えながら、基準を作ってあげることを大事にしていくというのはありますね。川和高校の野球部に入ってくる子たちは、野球の強豪校に入るような子たちとは違って、野球との関わり方が比較的浅い状態で入ってきます。考え方もそうですし、練習量も。本気でやる野球を知らないんですよね。そこを実感させてあげるところから始めています」
川和高校野球部監督の最終年となった昨年度、生徒たちの成長を実感する印象的な出来事があった。
「去年度の卒業生が入部してきた2020年は、最初3ヶ月休校で直接会ったのは6月になってからでした。以降2年間は冬の土日練習も規制されてできない状態で、練習量が少ない中でやってきました。甲子園も独自大会となった年で、先輩から何かを学ぶような時期もほとんどなくて、生徒たちは何も知らない状態の中、平日練習も90分が週3日とかで『正直難しいな』と思っていたんですが、子どもたちが自分たちで連絡を取り合って、メニューも自分たちで組んで、各々の場所でできる自主練習を自分たちで考えて、かなりの練習量をこなしていたんです。それを卒業する3月に聞かされて『なんで言ってくれないの』って聞いたら『自分たちで決めて動いていたことなので』と、当たり前だと思って、子どもたちが独自に動いていたんです。それを聞いた時に『この子たちすごいな』って実感しました。」
毎年のように生徒たちが入部し、毎年のように送り出す。2年半というわずかな期間の中で、日々成長する姿を実感できることを、指導者としての喜びだと話した伊豆原さん。この話をしているとき、その表情から自然と笑みがこぼれていた。
「自分は『青は藍より出でて藍より青し』っていう言葉が好きなんですが、こちらが想像している遥か上を超えていく瞬間っていうものが、やっぱりあるんですよね。野球の技術的なこともそうですし、精神的なところでもそうです。夏(甲子園)に向けてやるんだと自分で決めているからこそ、高校野球での3年間で大きな成長を遂げて『大人』になっていくというふうに思いますね」

ゼロから歩んできた高校野球指導者としての13年間で、間近で大きく成長する生徒たちを見続けてきた伊豆原さん。時代の移り変わりと共に、指導を受ける生徒たちの姿勢や考え方に、変化を感じる部分はあったのか。
「生徒自体は『毎年違う』というのが正直なところです。近年ではコロナもあって、生活環境にも大きな変化がありましたが、子どもたちの本質は多分変わっていないんじゃないかと思います。子どもたちはすごく純粋で、いくらでもなんでも彼ら自身の中に取り込んでいける状態で高校に入ってくる。中学もそうですが、高校でもステップアップしていくんだと思っています」
子どもたちの本質は変わらない。ならばそれを指導する大人側、指導者たちの変化をどう感じているのか。
「僕らは部活動中に『水を飲むな』と言われてきました。良い悪いとかではなく、そういう科学的根拠の少ない根性論があった時代でした。ただ、そこを経験したからこそ、そういうことを否定できると思っています。論理的・理論的な部分を絶対値にして指導をしていかなければいけないと思いますし、ようやくそういう風潮になってきたというのは感じています」
これまでの既成概念を捨てて、『ゼロから始めたい』と、野球指導に取り組んできた伊豆原さんの考え方に時代が追いついてきたと言えるのではないだろうか。
神奈川県内での教員人事異動に伴い、10年間指導してきた川和高校の監督を退任。現在は教員として別の高校で教壇に立ちながら、自身の息子が所属するボーイズリーグのチームなどで、主に中学生の指導に当たっている。自身のTwitterに「高校野球指導者としては休憩中」と記されていたことを尋ねると、ニッコリ笑いながらこう答えてくれた。
「休憩は休憩なんですが、あまり休憩している感じではなくて、むしろ今の方が勉強しているなって、野球に関しては言えるかなと思っています。高校野球から離れるということではなくて、1年なのか3年なのか、ひょっとしたら半年なのかわかりませんが、間違いなく(高校野球の指導者に)戻ると思います」
経験も実績もないまま高校野球の指導者を目指し、教員になったのが28歳、そして野球部の監督になったのは33歳と遅かった伊豆原さん。自身の経験を踏まえて、生徒たちには『真っ直ぐに行くことが全てではない』と常々話してきたというが、再び高校野球の指導者に戻った時、どんなチーム作りをしていくのか。野球指導者として歩む道のりは、まだまだ続いていく。