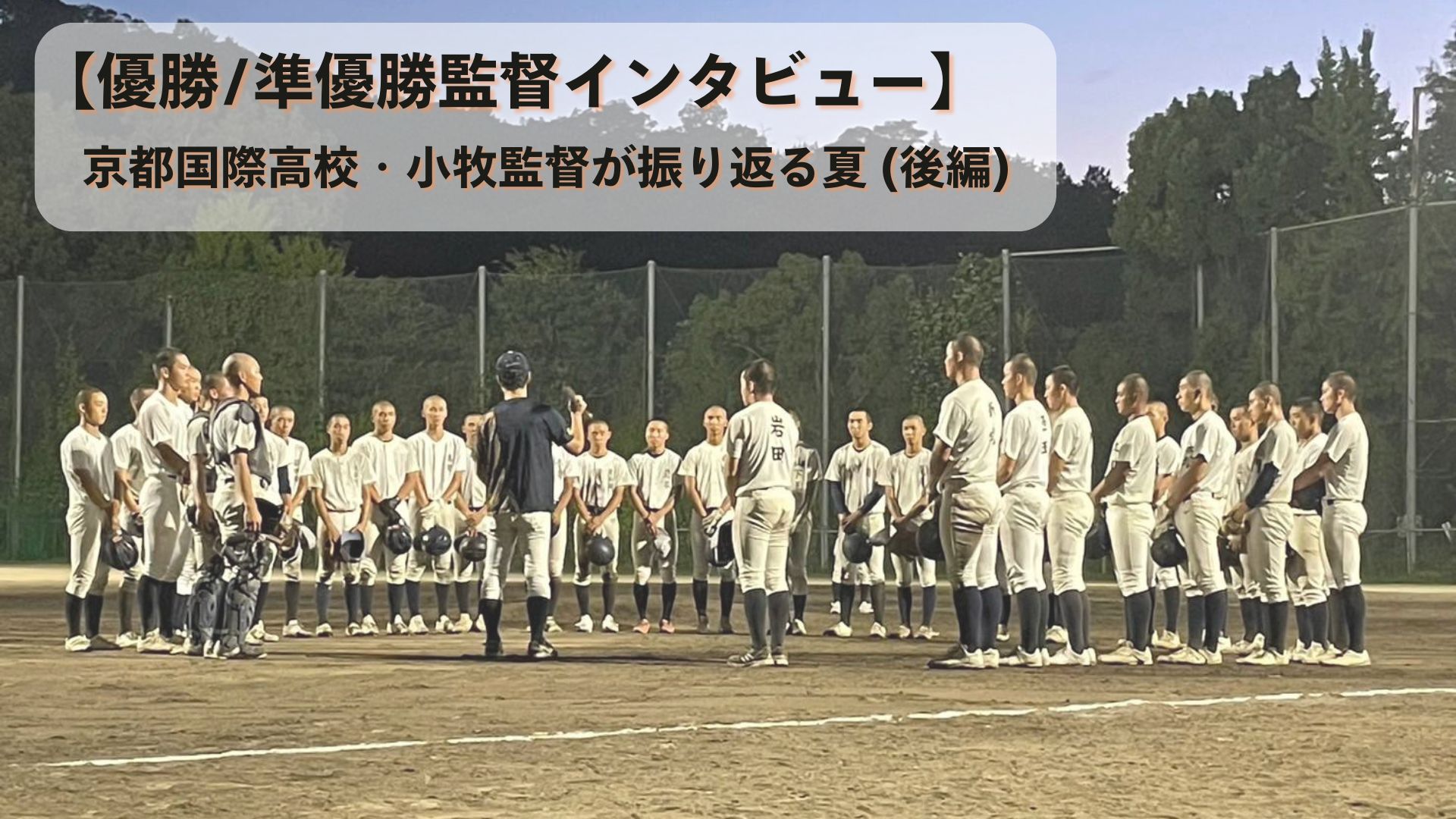※本記事は前後編の後編。前編を読む
練習量多寡は今のアマチュア野球界で度々議論される。
長時間練習は本当に身になるのかどうか。拘束する時間も含めて、今の野球界で見直されている感がある。
しかし、この夏、京都勢68年ぶりの夏の甲子園制覇を果たした京都国際はそうした議論とは無縁の学校だ。
「こっちとしては100%のパフォーマンスが出せる状態で大会に挑みたかったんですけど、少しの時間でも練習したいというのが選手たちにはあるみたいで。
甲子園期間中だと9時から15時までを練習時間にしていましたけど、結局、19・20時になると選手は出てきて練習をし始めていました」
京都国際の指揮官・小牧憲継はそう語る。
甲子園期間中も選手たちに聞いてみたところ、気がつけば練習場に体が向いているのだという。監督や指導者は命令をしていないというのにだ。
世の中には不思議な空間がある。その場に行けば自然とそういう行動に出るというよう場所だ。
例えば、神社仏閣に行くと、ポイ捨てされたゴミを見ることはないだろう。それは掃除が行き届いているのではなく、その場の空気が人の行為・行動を整えてしまうのだ。京都国際のグラウンドにもそういった空気がある。その場に行けば練習をしようという気になるのである。

とはいえ、小牧監督が就任した当初から、今のような空気があったわけではない。韓国系民族学校のルーツを持ち、今や日本人の生徒が70%以上を占める学校は京都府内において、それほど知名度があったわけではなく、入学してくる部員のレベルも高くなかった。
かといって、選手を勧誘しても有望選手が来てくれるようなチームではない。そんな事情から小牧監督が目指したのは選手一人一人を育てるという指導方針だった。
小牧監督はいう。
「学校のいろんなバックボーンがあってなかなか選手が来てくれなかったので、どうやったら認めてもらえるかなって考えた時に、今いる選手たちを1人でも多く上の世界に送り込めたら、周りの中学校のチームの方たちも認めてもらえるんじゃないかなと。それが始まりだった」
もともとは甲子園を目指すため、その成果を上げることの一つとしての育成だったが、時が経つにつれて、そんな思いは消えていったという。そして、ある選手の入学から一気にチームは変わった。その選手とは曽根海成選手(広島)だ。
内野手としてユーティリーティ性のある曽根は京都国際を卒業後に育成枠でソフトバンクに入団。支配下指名を勝ち取り、2017年にジュニアオールスターのMVPを獲得したほどだ。今は広島に移籍して11年目のシーズンを迎えている。
「曽根はスカウティングをして獲った選手なのですが、曽根を見ていた時に、ある学校の指導者から『曽根を欲しがっているようじゃ甲子園は無理』と言われたんですよね。
でも、当時のうちのチームからして、キャッチボールができるだけで十分な選手だった。だから来てもらいたかったんですけど、実際、曽根は本当によく練習をする選手でした。どんなきつい練習にもついてきたし、それがプロに行っても可愛がられているのかなと思う」
あんな選手でもプロに行けるのか。なかでも、ジュニアオールスターでMVPを取ったことのインパクトは大きく、そこから選手の流入において変化が生まれたのだった。
甲子園を目指す学校としてではなくプロに行けるかもしれない。今や11人のプロ野球選手を輩出しているが、小牧監督の中では指導方針の腹は決まった。
甲子園を目指すために、評判を良くすることが狙いだった選手育成が、いつからか「選手育成が第一」となっていたのだ。
小牧監督はいう。
「現実問題、グラウンドが狭くチーム練習もできないのでどうしたらいいんやろうっていうのがあったので、そこで僕自身が吹っ切りました。
逆に甲子園を目指さない。個の能力だけを徹底的に磨いていい大学に獲ってもらう、社会人、プロに行けるそういう集団であってもいいんじゃないかなと。甲子園出場のことは僕自身忘れていました。
もちろん、ゲームになったら勝ちたいですし、ピッチャー対バッターの対戦では、それぞれが打ちたいし、抑えたいというのが野球選手の本能やと思うんですけど、甲子園に行くっていうよりかは、甲子園の地区大会が選手の品評会な。スカウトに見てもらう場所であるという感覚はありました」。
もっとも、選手育成に振り切れた理由には環境面もある。
練習グラウンドの校庭は左翼と中堅70メートルしかなく右翼は65メートルと歪な形をしていて試合ができる環境ではない。
加えて、2021年に甲子園初出場を果たすまで、校庭は砂利でできており、全国の高校野球部に当たり前のようにある内野の黒土は存在していなかった。
しかし、この環境の不備が逆に育成に役立った。全体練習はできることに限りがあり、個人練習に時間が割かれた。加えて、砂利で練習することが内野手の技術向上に役立った。

小牧監督は自嘲気味にいう。
「(砂利は)どう跳ねるかわからないんですよね。普通のバウンドが1球も来ないんで、だから脱力していかにどう跳ねるかわからないバウンドに反応していくかが求められました。
グローブを下から上に動かして捕るとか。特別なことをするというより、練習していく中で無意識に体が覚えていくという練習をしていました」
まるで中南米のアカデミーのような話だ。グラウンドがボコボコなところでやるから上手くなる。実は小牧監督は、それをよく理解していたのだ。
「キューバやドミニカ共和国のショートってかっこいいじゃないですか。子どもらはすぐに言い訳してイレギュラーするみたいな顔をするんですけど、ドミニカの野球場は瓦や砂利、石ころの上で野球やっていて、ここはまだ土っぽいやろと、納得させていました。
当時はまだ参考文献とかもないですし、ドミニカの野球を真似るといっても、見よう見まねですけど、トレーニングなどは参考にしていました」
そうして選手が育ち、評判が評判を呼び選手が集まり出した。そして、2021年には春夏甲子園。夏はベスト4にまで上り詰める快挙を果たす。その活躍を見て入学してきたのが今年の3年生で、キャプテンで遊撃手の藤本は福岡からやってきた選手だ。
ある程度こなれた選手で、スケールはそれほど高くなかったが、それが上手く作用し、これまでとの方針とはまるで異なり「甲子園で勝つこと」を目指して結果を逃したのが今年のチームだった。
何もないところから選手育成を目指し、それが結果として繋がった。もともと、上の世界で活躍する選手の育成を目指してきたチームだったから、練習を自ら進んでやる空気はこの頃から生まれはじめた。
年度によって違いはあるにせよ、個別で練習に取り組む空気感はそうして醸成され、今の形になったということである。京都の新鋭校の初載冠はそうして実現したのだった。
「そういう文化・風土だけは後輩に失ってもらいたくないですね。日本一という大きな財産を3年生が残してくれましたけど、それ以上に京都国際は練習してなんぼやっていう。そこを追求する姿勢だけは後輩に代々受け継がれていってほしいと思います」

ただ、一つ悩みがある。小牧監督は今でも育成を第一にして個人の成長を第一に考えているが、甲子園の活躍であの舞台を活躍することを目指す選手が増えてきたのだという。
甲子園で勝つことの意義は感じているが一方で、勝利に固執することで、選手のスケールを小さくしてしまう可能性も小牧監督自身が危惧するところでもあるのだ。
「僕は個々の能力を見出して、1人でも多く上の世界で活躍できる選手を育てたい。このスタンスだけはやっぱり曲げたくない。選手たちが勝つことを求めたいって言ってきたときに、どうしていくべきか。
今回、勝たせてもらって人間としても大きく育ったのを見ると、(勝つことは)すごい経験だなと思います。そのさじ加減、塩梅が難しいです。
新チームについては今の3年生より各ポジションにスケールの大きい選手がいるんです。この子たちが1年後に今の3年生と同じ気持ちでやってくれたら絶対上回ると思います。
この子たちがどういう成長を見せてくれるのか、今回はチーム力で本当に高校野球のお手本のような野球でした。今度は逆にプロ予備軍みたいなチームを作り上げてみたいなっていう僕の欲通しい野望もあります」。
勝利と育成の狭間で揺れることは高校野球の強豪が通るべき道なのかもしれない。
一つの優勝がさらなる期待を呼び、勝つためのチーム作りを余儀なくされる。
育成集団・京都国際が甲子園で結果を残して、これからどの道に進んでいくのか。個人的にはこれからが楽しみなチームである。
(取材/文:氏原英明、写真:京都国際高校提供)