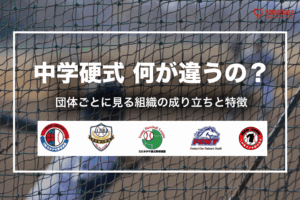地域に古くからあったチームがなくなり、地元に野球がなくなってしまう絶体絶命の危機――。そこで立ち上がった保護者たちが、再び地元に野球熱を復活させるというような夢物語を実現しているのが、三重県で活動するKスラッガーズだ。2020年に新たに立ち上げ、いまでは40人を超える選手たちを抱えるチームの信念とは。
子どもたちのために、という強い思いを持って
三重県の中心に位置する津市と、その北に位置する鈴鹿市を拠点とするKスラッガーズは、2020年に発足して今年3年目を迎えたばかりの少年野球チームだ。チーム名の『K』は活動拠点の鈴鹿市郡山町、津市河芸町に由来し、「選手たちみんながホームランを打てるような強打者に育ってほしいから」という意味で、『スラッガーズ』と名付けられた。2022年9月10日時点で40名を超える子どもたちが所属し目を輝かせながら、毎週末に野球に取り組んでいる。
「子どもたちのために、子どもたち目線になってできればという思いでチーム運営をしています」

(写真:チーム提供)
そう語るのは、創立時から監督を務める瀬川さん。今年の2月にはベストコーチングアワード2021の最高位・トリプルスターを獲得するなど、いまの時代に合わせた指導を心がけ、日々の活動に取り組んでいる。
前チームの解散からスタート。できることを着実に
発足のきっかけは、旧チームの解散だった。
「元々、地元の小学校に長く続いていたチームがあったのですが、近年は人が足らず、合併や休部が避けられない状況でした。我々が発足した年に、ついに廃部となってしまったことを受け、当時所属していたメンバーで、新しくチームを立ち上げたんです」
いまなお全国各地においては、地元の小学校とチームが連携している形が大半だ。Kスラッガーズが拠点とする地域もまさにそういった地域だった。一度、うまくチームが回らなくなると、地元での選択肢が少ない地域は特に、野球を“避ける”ことへとつながってしまう。子どもたちには野球以外の選択肢もたくさんある時代――。地元のチームの衰退はそのまま野球人口減少へとつながってしまうのは当然のこと。瀬川氏は当時、息子が前チームに所属していたこともあって“親コーチ”として携わっていた。
「正直、前の体制に対する不安・不満もありました。『これでは来てくれる選手は増えない』と思っていて、どうやったらたくさんの子どもたちが楽しく野球に取り組めるかを考えて、自分達で新しくチームを立ち上げようと決めたんです」
同じ思いを持った保護者たちも歩みをともにし、チームを発足。前述のとおり、「子どもたちのために」を心に強く誓って運営をスタートした。

(写真:チーム提供)
「いろいろなことに取り組みました。選手を集めるために一番取り組んだのは、ホームページの充実と、SNSでの発信ですね。我々の地域で、しっかりとしたホームページがあるようなチームがなかったというのもありますし、自分も親の立場で考えて、そのチームがどんな指導方針で活動しているのかがわからなくては、なかなか子どもを預けられませんから。チラシも用意して、地域のお店などでたくさん置いてもらいました」
ホームページ、チラシについては、どこかに外注したりせず、瀬川氏自身が一から勉強して開設。「いまでは専門的なソフトもある程度使えるようになりました」。こまめな更新が行われているSNSと、活動方針が明確なホームページが、いま40人以上の選手を抱えるチームの原動力のひとつになっている。ぜひ、Kスラッガーズのホームページを見てみてほしい。
選手たちの本音が覗ける野球ノート。野球への思いを持ち続けて次のステージへ
一度人気がなくなってしまった地域で、再び人気を復活させることは容易ではない。同じような状況に陥り、事実上野球が途絶えてしまっているような地域も存在するのが野球界が抱える現状だ。新たな良い流れを生み出すためには、“情熱”だけではなく、いまの時代にあった手段と、いまの子どもたちに指導をする知識が必要となってくる。
Kスラッガーズにおいては、前者がSNSであり、ホームページだった。後者においては、いまの子どもたちを知るために、選手たち個人と監督で交換日記のようなやりとりをするための“野球ノート”を通じて、コミュニケーションをとっている。
「古くからあるコミュニケーション手段ではありますが、いまの時代だからこそ、良い取り組みだと思いましたね。一部やらない選手もいますが(笑)、毎週末には30冊近くのノートが私のところに集まります。それを読むと、『こんな風に感じていたんだな』と知ることもできますし、私自身もどう返答してあげようかという勉強になります。いまでは趣味のような取り組みになりました」

(写真:チーム提供)
コミュニケーション方法が多用化する時代だからこそのアナログな手法。このような手間のかかる取り組みだからこそ、選手たちの本音を知ることができるのかもしれない。
最後に、Kスラッガーズの掲げる指導方針を紹介しておこう。
『「ナイストライ!」を合言葉に子供たちがチャレンジと失敗を繰り返すことができる環境づくり』
『指導者が心から野球を楽しみ、子供たちの「野球が楽しい!」を育てる』
『今結果を出すことより積み重ねを大切にしているか、何が出来るようになったのかを見つける指導』
『学童野球はゴールではなく、子供たちの野球人生のスタートであり基礎である事を理解する』
挑戦すること、楽しんでもらうこと、未来を見据えること――。この指導方針には大事なものが詰まっていると感じる指導者も多いことだろう。
瀬川氏は言う。
「次のステージで何人が野球を続けてくれるかが私たちのステータスだと思っています。野球の楽しさを知って、中学校に行ってもやりたいと思うか、が自分たちの腕の見せどころです」
未来ある子どもたちの可能性を広げるために、いまにあった手法に取り組んで、地元に再び“野球熱”を生んだKスラッガーズ。ぜひ、チーム運営のひとつの参考にしてほしい。
(了)