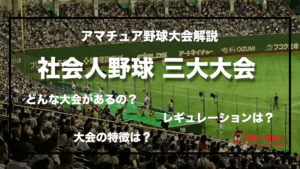夏は全国大会シーズンである。7月には社会人野球の都市対抗野球が東京ドームで行われ、8月は全国高校野球選手権大会いわゆる「甲子園」が開催されている。野球シーズンはプロ野球で春から秋にかけてのイメージがあるが、例年、7・8月は学生が夏休みということもあり、多くの大会の全国大会や上部大会に当たる大会が全国各地で開催されている。
Homebase事務局では、これらを整理する中で各大会の位置付けや歴史、実施背景を改めてまとめることとした。
今回は、「公益財団法人日本学生野球協会(以下、学生野球協会)」に目を向ける。日本のアマチュア野球界は、全日本野球協会(BFJ)に加盟する3つの大きな野球組織から構成されている。社会人野球や硬式の少年野球などの連盟が集まる「公益財団法人日本野球連盟」、軟式野球の連盟である「公益財団法人全日本軟式野球連盟」、そして公益財団法人日本高等学校野球連盟(以下、高野連)・公益財団法人全日本大学野球連盟(以下、大学野球連盟)を傘下におく「学生野球協会」である。一般的な知名度としては、高野連が圧倒的に有名だが、この日本学生野球協会(以下、学生野球協会)が日本の学生野球を取りまとめているのである。しばしば、選手の商業利用問題で話題になる日本学生野球憲章もこの組織が制定している。
国民的なスポーツとなっている高校野球の聖地「甲子園」で行われる2大大会
高野連の大会といえば、多くの人が全国高等学校野球選手権大会(以下、選手権)や選抜高等学校野球大会(以下、センバツ)といったいわゆる「甲子園」を思い浮かべるだろう。これは間違っていない。硬式野球部の部員たちは、この春と夏に行われる甲子園を目指して学生生活の多くの時間を割きながら白球を追っていくのである。選手権は、朝日新聞社と高野連が主催する文字通り高校の日本一を決める選手権という立ち位置で全国47都道府県の高校が49代表を目指して県大会から一発勝負のトーナメントを戦う日本の夏の風物詩的な存在の大会だ。2022年は3547校がエントリーした野球界でも、1番規模の大きな大会である。
対して、センバツは、春に毎日新聞社と高野連によって主催され、全国大会の出場校が32校と一気に「選抜」される。2022年のセンバツでは選考基準についても話題となったが、基準は第88回大会(2016年)からは以下の通りとなっている。
国民的なスポーツとなっている高校野球の聖地「甲子園」で行われる2大大会
高野連の大会といえば、多くの人が全国高等学校野球選手権大会(以下、選手権)や選抜高等学校野球大会(以下、センバツ)といったいわゆる「甲子園」を思い浮かべるだろう。これは間違っていない。硬式野球部の部員たちは、この春と夏に行われる甲子園を目指して学生生活の多くの時間を割きながら白球を追っていくのである。選手権は、朝日新聞社と高野連が主催する文字通り高校の日本一を決める選手権という立ち位置で全国47都道府県の高校が49代表を目指して県大会から一発勝負のトーナメントを戦う日本の夏の風物詩的な存在の大会だ。2022年は3547校がエントリーした野球界でも、1番規模の大きな大会である。
対して、センバツは、春に毎日新聞社と高野連によって主催され、全国大会の出場校が32校と一気に「選抜」される。2022年のセンバツでは選考基準についても話題となったが、基準は第88回大会(2016年)からは以下の通りとなっている。
運営委員会で選出された選考委員が、下記の出場校選考基準にもとづいて厳正、公平な会議を開き出場校を選出、当該校の承諾を得て決定する。
(1) 大会開催年度高校野球大会参加者資格規定に適合したもの。
(2) 日本学生野球憲章の精神に違反しないもの。
(3) 校風、品位、技能とも高校野球にふさわしいもので、各都道府県高校野球連盟から推薦された候補校の中から地域的な面も加味して選出する。
(4) 技能についてはその年度の新チーム結成後よりアウトオブシーズンに入るまでの試合成績ならびに実力などを勘案するが、勝敗のみにこだわらずその試合内容などを参考とする。
(5) 本大会はあくまで予選をもたないことを特色とする。従って秋の地区大会は一つの参考資料であって本大会の予選ではない。
センバツでは、一般選考枠の他に21世紀枠というものがある。2001年の第73回大会から設けられた「少数部員、施設面のハンディ、自然災害など困難な環境の克服・学業と部活動の両立・近年の試合成績が良好ながら、強豪校に惜敗するなどして甲子園出場機会に恵まれていない・創意工夫した練習で成果を上げている・校内、地域での活動が他の生徒や他校、地域に好影響を与えている」学校を選手するための枠という特徴的な選出枠を持っている。また過去には、前年優勝校枠や一般選考から漏れた補欠1位校からデータで出場校を決める希望枠、東日本大震災からの復興を目指す東北地方から1校多く選出する東北絆枠など、さまざまな選考方法をとったことがある。
【過去に設けられたことがある枠】
◆前年優勝校枠
1925年〜1932年:前年優勝校は地方大会に出場しなくても無条件で全国大会に出場することができる。
◆希望枠
2003年〜2008年:一般選考の補欠校にもセンバツへの「希望」を残す狙いで、神宮大会枠を得た地区を除く地区の補欠1位校が対象。投手を含めた守備力のデータに従って決めることが通例だった。
第75回大会→被塁打、与残塁+失点、失策、第76回以降が被塁打、与四死球、失点、失策。第75回大会では明治神宮大会を除く直近5試合で各項目の1試合9イニング平均値を計算し、最初に被塁打数の多い3校、次に与残塁+失点の多い3校を除外し、残った3校のうち最も失点の少ないチームを選出
第76回大会→明治神宮大会を除く直近4試合で各項目の1試合9イニング平均値を計算し、順位を得点化、合計がもっとも多い学校が選出
第77回大会以降→非公開
◆東北絆枠
2013年:通常の東北代表枠や21世紀枠などとは別に、東日本大震災からの復興を目指す東北地方の学校の中から一般選考の中に含めつつも、何かキラリと光るものを持っているチームを選抜する。
超ハイレベル!あまり知られていない高校生の「もう一つの甲子園」
先述の2大会は、メディアでも多く取り上げられており多くの方がご存知だろう。しかし、実は高野連はもう一つ全国大会を主催しているのをご存知だろうか。それが、「もう一つの甲子園」と呼ばれる全国高等学校軟式野球選手権大会だ。毎年、兵庫県立明石公園第一野球場を中心に行われるこの大会は、2022年で67回目を数える。大会自体は47都道府県を16地区に分け、硬式野球の選手権と同じく全ての試合をトーナメントで戦い、各地区大会を優勝した16チームが全国大会へ参加する。開催時期に関しても、甲子園での選手権が終了後の8月下旬に開催されるなど、硬式と軟式の違いはあるものの日本一を決める選手権という意味でも同じ扱いとなる。軟式野球ということもあり、投手のレベルが高いとなかなか得点に結び付かなくなり、投手戦になることが多い大会でもあり、2014年の岐阜県・中京(東海地区代表)対 広島県・崇徳(西中国地区代表)の試合がサスペンデッドゲームとなり、2日目・3日目も15イニングずつ(延長45回)を終えて0-0と互いに譲らず、史上初の「再々サスペンデッドゲーム」になり、4日目の試合で延長50回表(この日の5イニング目)に中京が3点を挙げ、3-0で勝利した試合は大きく話題にもなった。
【全国高等学校軟式野球選手権大会出場枠地区分け】
◆単独出場枠(4)
北海道、東京、大阪、兵庫
◆代表地区枠(12)
東東北:岩手、宮城、福島
西東北:青森、秋田、山形
北関東:茨城、栃木、群馬
南関東:埼玉、山梨、千葉、神奈川
北信越:長野、新潟、富山、石川、福井
東海:静岡、愛知、岐阜、三重
近畿:滋賀、京都、奈良、和歌山
東中国:岡山、鳥取、島根
西中国:広島、山口
四国:香川、愛媛、徳島、高知
北部九州:福岡、佐賀、長崎、大分
南部九州:熊本、宮崎、鹿児島、沖縄
今年は、8月24日から熱戦が繰り広げられ、バーチャル高校野球で軟式野球選手権の準決勝・決勝の3試合が、配信されることが決まっているので、ぜひご覧いただきたい。
大学野球の「聖地・明治神宮野球場」 と東京ドームを使用する大学日本一決定戦
そんな高校球児たちが、冬を超え、活躍の舞台を移すのが大学野球である。大学野球連盟には、全国に26連盟が加盟しており、大学数は372校と高校の10分の一の数となっている。(2022年5月時点)大学野球と言われると、高校のトップレベルの選手だけが進む世界だと思われているが、それは違う。部員数は各大学100名近くいるところが多く、推薦入試の選手だけでなく、一般入試から入部する選手が多くいる。大学野球の中でも人気の高い東京六大学野球は、甲子園でよく聞くような強豪校の選手が多く在籍するが6校全てで一般入部を受け入れており、実際にレギュラーをとるような選手も多く存在する。
大学野球連盟では、トーナメントの大会ではなくリーグ戦が主な戦い方となっており、2ヶ月ほどにわたる総当たりのリーグ戦を開催し、優勝校を決めるやり方が浸透している。このため、高校野球に比べ、ベンチ入りの選手の人数が多く、チームとしての総合力が強さに直結する。現在、大学野球連盟には26の地区連盟が所属しているが、この全ての連盟が年間を通して2つの大会を目指しリーグ戦に取り組んでいる。6月に行われる全日本大学野球選手権大会と11月に明治神宮と学生野球協会が主催する明治神宮野球大会である。両大会がメイン会場を明治神宮野球場としており、大学球児にとっての「聖地」となっている。
全日本大学野球選手権大会は、その名の通り他競技のインカレに相当する日本一を決める選手権大会である。26連盟の各リーグ戦の優勝校27代表(九州大学野球連盟のみ北部リーグと南部リーグが存在)が、顔を揃えトーナメントにより日本一を争うのである。準々決勝までは明治神宮野球場と東京ドームを使用し、準々決勝以降は明治神宮野球場のみを使用する。大学の日本代表の活動は主に夏の期間となるため、この大会で活躍した選手が追加で代表に招集されることもよくあるため、注目が集まる。
明治神宮と学生野球協会が主催する秋の風物詩 大学の部は引退を告げる試合に
秋に学生野球協会が明治神宮と主催するのが明治神宮野球大会だが、こちらは少し珍しい大会でもある。1970年に明治神宮鎮座50年を記念して行われた奉納野球が始まりのこの大会は、学生野球協会が主催とある通り、高校の部と大学の部がある。高校は、新チームとなった後の秋季大会の上部大会として実施され、翌年のセンバツに繋がる位置付けの大会となっているが、地区大会の優勝校は、センバツへの出場確率は優勝の時点でかなり高いものとなっているため、名誉とオフシーズンを見据えた大会という見方が強い。しかし、大学の場合、秋の日本一そして最後の大会という要素もあり、白熱した戦いが繰り広げられるとともに戦いの終わりにさまざまな想いが入り混じる大会でもある。
大会自体は、明治神宮球場をホームグラウンドで使用している東京六大学野球連盟及び東都大学野球連盟はリーグ戦優勝校に出場枠が与えられ、その他の連盟は各リーグ優勝校による複数連盟間での代表決定枠を争う形で本大会は11チームで構成される。
この大会は、なんと言っても高校と大学の試合が同じ球場で同じ日に見られることが1番の特徴で熱心な野球ファンが集まる。また11月の試合のため、プロ野球のドラフト会議も終わっており、大学生の指名選手の活躍が見られることもあって、厳しい寒さの中でも大勢のファンが駆けつけるのも特徴だ。翌年のセンバツ出場が有力と見られる高校の部と秋の大学日本一を見届けられる大学の部、ぜひ一度明治神宮野球場に足を運んでみて欲しい。
学生野球は、プロほどの完成された実力はないが、技術的に大きく伸びる瞬間を目の前で見ることができる点や限られた期間の中で自分のパフォーマンスを出し切るためにプレーする姿など学生野球ならではの魅力は多い。実際に甲子園が、見る人の心を揺さぶるのは選手の背景にそれぞれのストーリーがあるからこそだ。大学野球は高校野球とプロ野球に比べると人気は高くないかもしれないが、レベルはとても高くプロで活躍する大卒選手の多くは大学在学の期間で大きく伸びた選手も多い。そんな選手たちを間近で見られる学生野球。ぜひ、追いかけてみて欲しい。