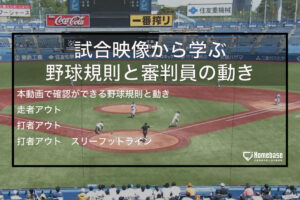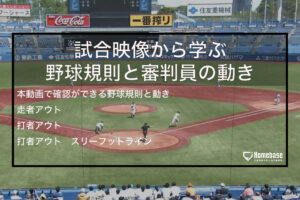野球を含め、さまざまなスポーツの試合を行う上で欠かせない「審判員」。試合を陰ながらまとめ、進行し、数々のドラマを見届けている審判員には、プレイヤーとはまた違った魅力とやりがいがたくさんある。
審判員として20年のキャリアを持つ、山口智久氏が語る審判員の“リアル”。第二回は甲子園大会における印象的なジャッジとその試合を中心に迫る。(写真:山口さん提供)
-山口さんのキャリアの中で、印象的だった試合を教えてください。
質問に関する答えとしては適切ではないかもしれませんが、雨の日の試合での降雨コールドゲームの判断は非常に難しいものです。
昨夏の全国高等学校野球選手権大会(甲子園大会)、大阪桐蔭高校 対 東海大菅生高校の試合はとても判断が難しい試合でした。結果としては降雨コールドゲームとなり、大阪桐蔭高校の勝利となったわけですが、その決断に至るまでには大変悩みました。
その試合は第一試合で、私は球審を務めることが事前に決まっていました。前日の天気予報では雨が試合中に降り始めることが予想されていました。
しかし、大会期間中に雨天中止が多くあった影響もあり、あらためて試合前に予報を確認したタイミングでは、なんとか第一試合は成立できそうだということで、予定通り試合が開始されました。
しかし、予想よりも早く雨が降り始め、6回に差し掛かるタイミングで雨脚が強くなってきてしまいました。高校野球の降雨コールドゲームの条件は7回が成立するかどうかです(公認野球規則では5回で成立)。
甲子園大会の場合、審判幹事という方と大会本部の方がバックネット裏におり、試合運営等のアドバイスをいただくこともあります。しかし、試合が始まってからは現場の審判員の裁定が最終判断になります。
その試合の審判員のことをクルーと呼びますが、そのクルーで話し合いを重ねた結果、8回表途中で試合を中断し、32分間の中断後に降雨コールドゲームになることが決定されました。
降雨コールドゲームという判断については、試合成立前に中止として再試合にした方が良かったと話す方もいれば、屋外競技である以上、野球は降雨コールドゲームもルールの一部であるという方、後々になって高校時代の思い出になれば良いのではという方など様々です。
しかし、自分の中ではなんとか高校野球の集大成である「夏の甲子園」という舞台で、最終回まで試合をやってもらいたいという思いが正直な気持ちでした。
雨が強くなり、打者が振ったバットが滑って飛んでいってしまうことが起き、普通のショートゴロの打球が途中の水溜まりで止まってしまうようになりました。
その日の天気予報などを考慮すると、一度試合を中断したら再開はできないかもしれないとの思いもありましたが、選手の安全面や怪我の恐れもあり、試合を中断することを決意しました。

-甲子園という特殊な環境下での審判員で学んでいること、感じたことがあれば教えてください。
高校野球の選手として甲子園出場は叶いませんでしたが、今こうして審判員としてグラウンドに立つことができることは非常に嬉しく思います。
全国の審判員の方々が、甲子園大会での審判員の立ち振る舞いやジャッジを見に来られるような憧れの舞台です。他の試合と比べて多くのプレッシャーも感じています。
地方大会での試合に比べて観衆の数も違いますし、テレビを通して試合をご覧になる方もいます。圧倒的に見られているという意識が強くなりますが、その分やりがいも感じています。
夏の大会の試合では、試合後は熱中症の症状などで意識や体力が消耗され、フラフラになることもありますが、どんな状況でも諦めずに最後まで全力でプレイする姿や勝利したチームの選手が嬉しそうに校歌斉唱する姿を見ると、この試合に立ち会えて良かったと強く感じます。
-甲子園というのはやはり、特別な場所ですね。
全国の審判員の方々の多くが目標にしている舞台であると感じます。各地から審判員が派遣される制度がありますが、高校時代に選手として甲子園出場し審判員として戻ってくる方、高校時代に叶えられなかった甲子園の舞台に審判員として初めて立つ方など様々な方がいます。
そのすべての方々は、審判員として責任感と誇りを持って甲子園球場のグラウンドに立ち、的確なジャッジをされています。