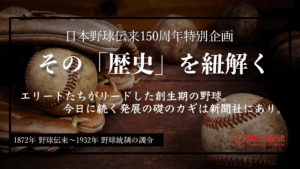中学校や高校の部活動は、教員免許を持った教員、学校職員が指導に当たることがほとんどです。
一方、学童野球や中学生のクラブチームなどは外部の指導者が指導を行っており、保護者や地域に根ざしたベテラン指導者、プロやアマで豊富な野球経験のある指導者など、経歴はさまざま。
特に指導者の人材確保が難しい学童野球では、ボランティアによる指導者や選手の保護者が交代で監督を務めるケースも多く見られます。
小中高の世代を問わず「勝利至上主義」や「暴力行為」など、指導者に関わる問題は数多く起こっています。野球離れを加速させる原因として、指導者の資質の問題は大きいと言わざるを得ません。
高校野球の現場に携わる伊豆原監督も、指導者育成の重要性を強調します。
「評価者と指導者は違います。選手をうまくする、強くするのが指導力であるのに、チームの勝ち負けが指導者の優劣につながるような捉え方が多い。
指導者の野球歴だけに縛られている面もあります。肩書きや野球歴にとらわれる文化を何とかしなくてはいけない。指導そのものとは別の基準で指導力の優劣が付けられているのが一番の問題だと思います」
罵声や暴力など球界の旧体質を根絶するには、野球界の考え方や文化を変える必要があるでしょう。2020年11月にBFJが野球界で初めて創設した「指導者ライセンス制度」は内容の充実度も重要です。
ライセンスはあくまでも入り口でしかなく、指導者をどう育成するか。資格認定を悪用する事例もあるため、制度の充実を早急に進める必要性に迫られています。
アマチュア野球では、長年、同じ土地で指導し続けているベテラン指導者も数多くいます。
積み重ねてきた経験値への敬意を払うと同時に、時代の変化に伴った新しい価値観への評価ができるよう一歩を踏み出すためには、何が必要なのか。これこそが野球への再評価につながります。
ベテラン指導者にも変わる勇気が必要です。技術偏重になりがちですが、「小学生には技術的指導より野球を好きであることが圧倒的に大切なのです」と伊豆原監督も言葉に力を込めます。
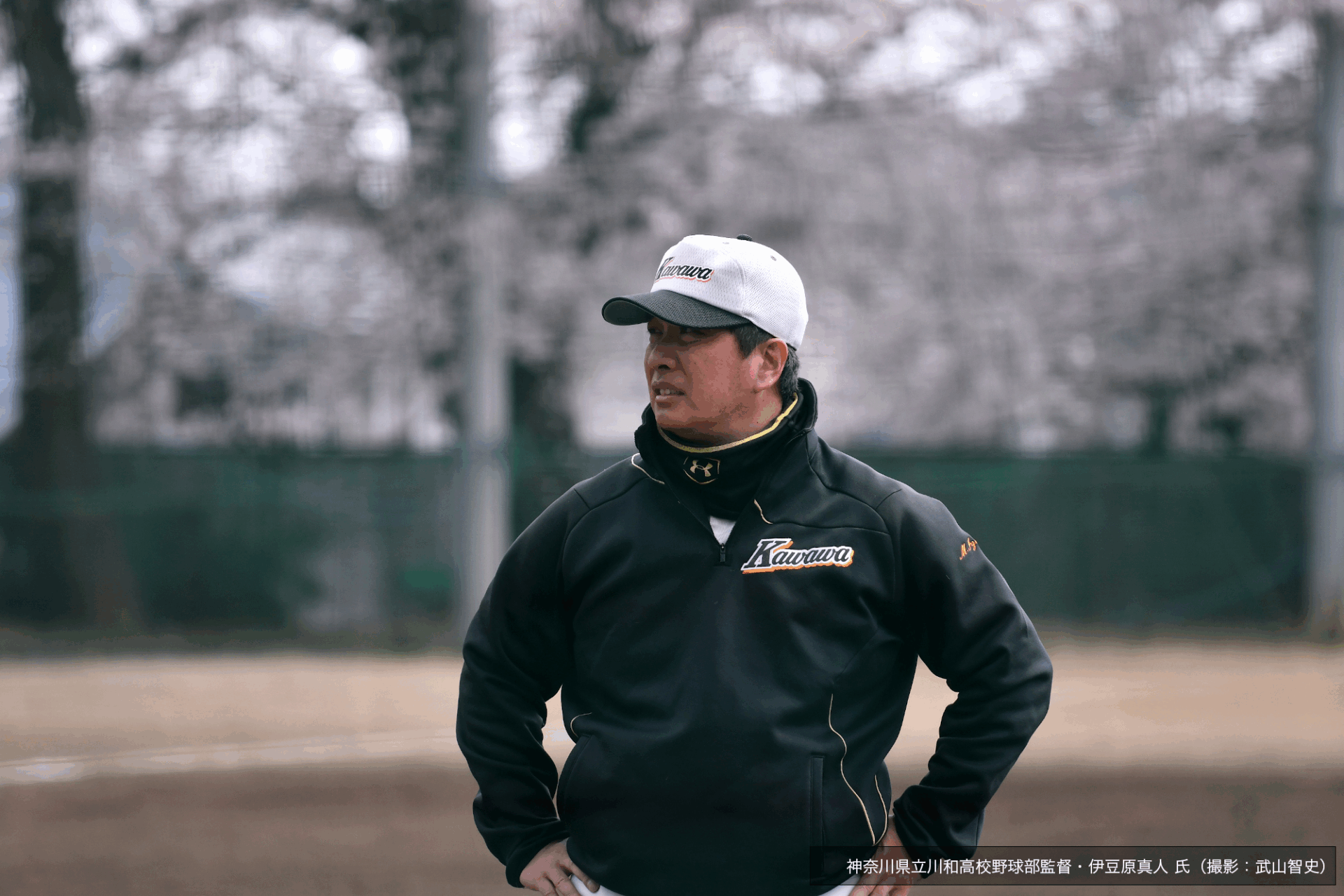
野球は日本に文化として根ざしてきた良歴史あるスポーツ。プロ選手など一流のトップアスリートだけに帰着するようになれば、野球はいずれ、選ばれなくなるでしょう。
「現代の親には、野球をやって利益になることはあるのか?という考え方をする人も多い。小学生時代から野球をやることでいかに心豊かになるか、きちんとアプローチする指導ができたら、自然と野球人口も増えてくると思います。
子どもがまず楽しいと思うこと。教養として素晴らしいものだと大人が発信していけることが大切だと思います」
学童チームにも外部の指導者を招へいできる環境を提供することも必要になるでしょう。日本学生野球協会の規約上、異団体の指導者間の交流は困難。
せめてアマチュアでは垣根を取り払い、自由に指導者間交流ができるようになれば、学童野球の指導法も変わってくることが期待されます。
具体策として、伊豆原監督は全軟連の社会人野球経験者と学童野球の連携を提案します。
「社会人野球出身者とはなかなか交流が持てないのが現状ですが、学童野球に助力する形で、BFJで研修してライセンスを持ってもらい、幼稚園児を一緒にサポートしてもらえたら。土日2日間のうち1/4でも、プログラムを作って一緒に動いていただけけるスタンスが取れるといいと思います」
教える側の人材不足は大きな課題。人材を確保し、サイクルを作ることができれば地域に根付いていきます。
社会人野球で現役を終えた40、50代の経験者が47都道府県には数多くいるものの、高校野球の指導者とのつながりはあまりないのが現状だそうです。
「そういう方と連携して、学校教育の中の野球に入りやすくする。外部スタッフの地域クラブ化の話もそうですが、常に自分のテリトリーの中で探していては無理。
企業のスポンサードを容認することも検討しないと。給与の保障もある世代の方に出向という形で、例えば土日どちらか半日だけでもサポートしていただける企業があれば、学童の指導者、お父さん監督も勉強になります。
暴言やパワハラ的な指導も減っていくのではないでしょうか。その代わり、学校や自治体でその企業の冠大会をやるなど、ギブアンドテイクしていく。地域化するには資金がどうしても必要になりますから。地方には地元企業の名士も多数いらっしゃいます」
金銭ではない形のギブアンドテイク、「学生野球憲章」に抵触しない方法を模索しています。
スポンサーを地域に求めて宣伝し、野球の持続化の可能性に賛同してもらうムーブメントを起こす。地方の地場産業、地元の銀行、企業は地域貢献に熱心で、そういう人材を採用する素地もあります。
さまざまな進め方でアプローチする多様性は重要です。地域をいかにうまくまとめていくか。
実際、賛同してくれている都筑区の学童チームは1/3程度。「組織化と聞くと抵抗感を抱く人も多いようですが、『みんなで盛り上げていこう』といった有機的な連合のようなつながりがあってもいいのでは」と、伊豆原監督は提案します。

野球界には長い歴史があります。過去を知っている人の言葉には重みがあり、重鎮のひと言の影響力は絶大です。長い指導歴を誇る指導者には、「総監督の立場でいろんな学童チームに入ってアドバイスしていただきたい」と伊豆原監督。
BFJで名誉職として功績を称える表彰制度を作り、地域のスーパーバイザーをオフィシャル化していくのも一つの方法ではとも。野球界は「組織・肩書き社会」から脱却する変革期に来ています。
伊豆原監督が自主的に活動している「キッズベースボール体験会」には昨年12月から、今年の1月、2月でのべ50人が参加。
特別な告知はせずほとんど口コミだけでこれだけ集まったそうです。野球そのものの魅力が廃れたわけではないことが分かります。
2月下旬には埼玉県与野市でも同様の「キッズベースボール体験会」が行われ、42人が集結。
野球に興味を持っている子が多い半面、学童野球チームに入ることに躊躇している小学生が少なからずいるということも分かりました。
その与野市では連盟に所属しないチームを発足することが決定しました。小学生で大会に出なくても、中学や高校で十分野球はできます。
新たな小学生野球のモデルケースとなるかもしれません。群馬、大阪、兵庫と他県にも賛同してくれるつながりができ、地域によって環境や活動が違っても、根底の理念が共有できればすそ野は広がっていきます。
昭和時代には、学童野球をどう普及させるか、という考え方はそもそも根本にありませんでした。
野球は改めて普及する必要のない、子どもたちにとって当たり前にある身近なスポーツだったからです。多様な選択肢のある現代では、野球の魅力を削いでしまうようなマイナス面をなくす努力が必要です。
「高校野球はやはり認知度が一番高い。教育的側面もありますが、公立高校の人間が動くのが一番早いと思っています。組織ではなく、地域の方たちとみんなでいろんな意見を出してやっていきたい。
鎖じゃなくてゴムぐらいの柔軟に変化できる緩い連携。先生だけでなく、いろんな方が入っていくのが大切です」。野球界の団体間連携のために、高校野球の現場から変えていくんだという、強い使命感と熱意が伝わってきます。
都筑区の小中高では、指導者同士の技術連携講習会に以前から取り組んでいます。高野連の規程により高校の指導者が中学生に直接指導できない代わりに、まずは指導者間で様々な情報交換を行ってきました。
伊豆原監督を中心に、今後も指導者間のスキル上達など積極的な団体間での交流を推進していけるモデル地域としての役割に期待がかかります。
「都筑区には野球の強豪私学がないので先導しやすい部分もあります。都筑区は地方で言う中核都市ぐらいの規模。一つの市としてのまとまりとしてはちょうどいい土地です。
これからも自治体単位でモデルになれるような取り組みをしたいと思っています。お世話になった分を還元したいですね」
タッチポイントを増やし新規の子どもたちに野球の魅力を伝えながら、指導者の指導力向上を実現させる。横浜市都筑区の有識者が目指す二本柱への画期的な取り組みは、野球のすそ野の活性化につながっていくでしょう。
(取材・文/斎藤 聖己)