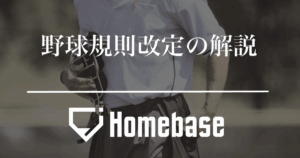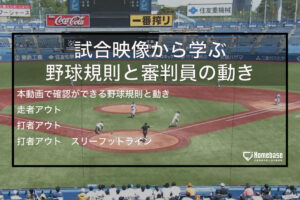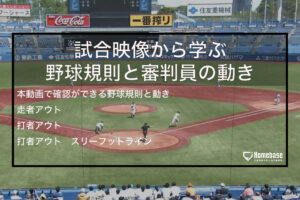現在、東京六大学野球連盟には20人の審判員が在籍している。(2022年春季リーグ開幕時点)現役時代に選手としてプレーをしていた方もいれば、そうではない方もおり、年齢も20代から60代までと幅広く登録されている。
そんな中、今回は東京大学大学院を卒業し現在は研究員として働いている審判員歴6年目を迎える瀧口耕介氏にインタビューを実施した。
イップスを発症し野球部を退部。大学の先輩に声をかけられ審判の世界へ
-審判員を志したきっかけや、影響を受けた方などがいらっしゃれば聞かせてください。
東京大学の先輩で青木さんという方がいます。青木さん(東京六大学野球連盟審判員 青木秀憲さん)は現在、私の母校でもある開成高校の野球部の顧問をされております。
実は、私自身が高校野球をやっていた頃から顧問をされていました。当時から青木さんは審判員の魅力について部員へ話すことが多かったと記憶しています。
私は東京大学に進学後、野球部に選手として入部しました。しかし、1年生の頃にイップスを発症してしまい思うようにプレーができなくなり、野球部を退部することになりました。
その後、青木さんから「審判員であれば今後も野球に触れ合う機会があるよ」ということでそれを機に審判員を志すことになりました。
東京六大学野球連盟の規定上、在学中は同連盟での審判員はできないということで、最初は東京都高野連の審判員として経験を積みました。そして、大学を卒業したのち東京六大学野球連盟で審判員を始めました。
審判界にもSNS発達の影響 ジャッジも見られているという意識に
SNSなどの発達により、ジャッジの際の画像や映像が世間に回るようになりました。1つの良い行動やミスジャッジがすぐに拡散されます。
もちろん、すべてのプレーに対して正確なジャッジをしなければなりませんが今まで以上に多くの方に見られているという意識を持つようになりました。
その一方、多くの方に見られているという意識の中で、審判員の間でも更なるスキルアップに励もうというモチベーションにも繋がっております。
-審判でしか経験できないことはたくさんあると思いますが、その中でも印象的なことはありましたか。
選手と同じグラウンドレベルで野球に携われることです。私自身、選手として神宮のグラウンドに立つことはできませんでしたが、今こうして神宮のグラウンドに立ち、アマチュア野球最高峰の東京六大学の試合に審判員として携わることができています。
こういった経験は審判員でなければできませんし選手の道を諦めた後でも、神宮のグラウンドに立てる機会があるので審判員をやっていて良かったと思います。
また、審判員であり、一野球人として、現在東北楽天ゴールデンイーグルスに所属している早川選手(2020年ドラフト1位 早稲田大学卒)の試合で主審をしたことは非常にいい経験になりました。
その年のナンバーワン投手とも言われる選手の投球を真後ろから見られるのは、審判員だからこそ可能なことかもしれないですね。もちろん、トップレベルのプレーをジャッジをさせてもらうにふさわしい審判員になれるよう日々レベルアップする必要を感じています。
予測と準備の大切さ
-プレーヤーから審判員へと変わる中で、意識していることや気を付けていることはありますか?
1点目はボールをちゃんと見てジャッジをすることです。初歩的なことですが、ボールを見ずに焦ってジャッジしても良いことはありません。
私自身まだ経験が浅いこともあり、ベテランの審判員の方のようにはうまくいきませんがそういったことを常に心がけています。
また、プレーに対して正対し一呼吸を置いてジャッジすることも意識しています。そうすることで焦ってジャッジをすることも減っていきます。
2点目はプレーの予測をすることです。1点目と共通することでもありますが、次に起こるプレーを想定することで心の準備ができて目の前で起こるプレーに対して慌てることなくジャッジすることができます。

-少年野球などでは、大人が驚くようなプレーが起こることもよくありますが、その際に意識した方が良いことはありますか。
先ほどとは逆のことをお伝えする形にはなりますが、予測しすぎないことも大切になります。もちろん予測することは必要ですが、その予測を超えるプレーに遭遇することもあります。
このシチュエーションではこのプレイが起こるという決めつけをせずにジャッジすることが少年野球の審判員では必要なことかもしれません。
連盟の審判員の先輩からは「審判員自身がプレーに驚いてはいけない」とよく言われています。自分の中では、自分の想定していなかったプレーが起こると誰しも慌ててしまうので事前にあらゆる可能性を頭に入れておくべきだと考えています。
自分がジャッジミスをした試合は非常に印象的です。今後同じプレーが起こった際にはこう動こうといったように、振り返る機会が自ずと増えるため、その分印象に残ります。
-試合を円滑に行う審判ならではの発想ですね。審判員としてジャッジをする中で選手や指導者の方に意識をしていただきたいことはありますか。
審判員の同僚とはヤジは控えていただきたいという話になることはよくあります。
上のステージに向かうにつれて、ヤジは減ってくるかと思いますが特に少年野球などでは指導者によるヤジが目立つケースがあります。もちろん審判員は正確なジャッジをするよう心がけています。
ジャッジに対し汚い言葉で罵るようなことはしないでいただきたいです。審判員も人間ですし、されたら嫌な気持ちになることもあります。指導者はもちろんのことですが、選手の皆さんにも気を付けていただきたいです。
また、選手に関してはまだ精神的に幼い高校生辺りまでは見逃し三振の際などに文句を言ってしまう子もいます。そういった言動を見かけた際には指導者がその選手に対してしっかり指導をすることも大事だと思います。
選手自身にも責任はありますが、その様子を見過ごしてしまうのは指導者としても良くないことだと思います。